- 子どもが勉強しない心理
- 親の心構え
- 不登校におすすめの学習方法
「また今日も勉強しない…」
「不登校のままで、将来どうなるのか不安…」
子どもが学校へ行かずに、家でも勉強している様子がないと、このままで大丈夫だろうかと心配になりますよね。
しかし、今すぐ勉強させなくては!と焦る必要はありません。
今回は、不登校で勉強しない子どもの気持ちと、親としての接し方について解説します。
この記事は以下の専門家によって書かれています。
執筆・編集責任:吉田克彦(合同会社ぜんと代表 公認心理師、精神保健福祉士)
医学監修:友常祐介(社会医学・産業衛生指導医、労働衛生コンサルタント、医学博士)
勉強しない理由とは?子不登校の子どもの心理
不登校の中には、勉強を理由にあげる子どももいます。
文部科学省の調査によると、小中学生の不登校の原因に以下があります。
- やる気が出ない 32.3%
- 不安・抑うつ 23.1%
- 生活リズムの不調 23.0%
- 学業不振や宿題の未提出 15.2%
- いじめや友人関係 13.3%
出典:令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果 概要
不登校の子どもが勉強しないのはさまざまな理由が潜んでいるので、紐解いていきましょう。
やる気がおきない
不登校の子どもが勉強しない理由の1つは、心身ともに疲れていてやる気がおきないことです。
不登校の子どもは、少なからず学校に通わないことに罪悪感をおぼえています。それでも、通えないほど心が疲れているのです。
不登校の原因は「やる気が出ない」が最も多いのは、限界までがんばってきたことが、無気力や意欲の低下につながっているのでしょう。
まずは、ゆっくり休むことが大切です。
見守りつつ、子どもの気持ちが落ち着くのを待ちましょう。
勉強の必要性がわからない
不登校の子どもは将来に不安を覚えています。
その一方で、勉強の必要性がわからないと思っていることも多くあります。
特に将来の目標が見えない中では、勉強が将来にどう役立つのかイメージしにくいこともあるでしょう。
毎日学校へ通うと意識せずとも授業がひらかれて勉強することになりますが、不登校の場合は、勉強する意味や目的がわからないと、やる気を持つことが難しくなります。
勉強のやり方がわからない
勉強をやる気があっても、不登校の場合は自分で学習をすすめていく必要があります。
教科書を開いてみても、どこまで理解できるのか、何からすればよいか、すべて自分で判断して勉強を進めていくことは難しいことです。
「わからない」ことが積み重なっていくと、勉強自体が嫌いになってしまうこともあります。
子どもが勉強にやる気でてきたら、勉強方法について親や学校などさまざまな場所で相談できるようにしましょう。
勉強への苦手意識
もともと勉強が嫌いな場合は、不登校かどうかに関わらず勉強したくない気持ちを持っています。
勉強してもうまくいかないという思い込みや、過去にテストや授業で失敗した経験から勉強が嫌いになっていることもあります。
「自分はダメだ」という思いが強くなると、勉強する気持ちになれませんよね。
今の学年にとらわれずに、簡単だと思えるところから勉強を始めて、苦手意識を減らしていきましょう。
環境や生活リズムの影響
不登校の子どもは、登校時間に縛られないため、起床時間が遅くなりがちです。
夜更かしにより、昼夜逆転した生活になることも多く見られます。
勉強しようと思っても、睡眠不足で集中力や記憶力が低下して、勉強しても覚えられないという悪循環になります。
また、勉強机が片付いていなかったり、気が散るものがたくさんあったりすると、勉強を始めるまでに時間がかかることもあるでしょう。
まずは、集中して勉強できる環境と生活リズムを整えることが大切です。
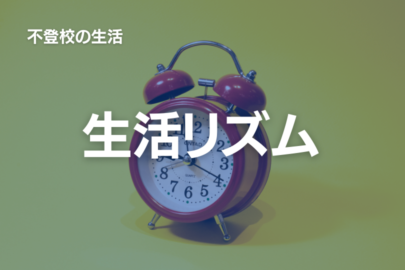
不登校の子どもが勉強しないときの親の心構え
不登校で勉強しない子どもの側にいると、子供の将来が不安な気持ちでいっぱいになりますよね。
つい、勉強しなさいと言ってしまいたくなる気持ちもあるでしょう。
子どもの話をじっくり聞く大切さ
不登校で悩む子どもにとって、親が話を聞いてくれることは大きな安心感につながります。
特に、子ども自身の気持ちを言葉にする場を作ることが大切です。
話しをする中で、子どもと親の考え方に違いもあるでしょう。
しかし、子どもの気持ちを理解しようとする気持ちは伝わるはずです。
子どもは自分の気持ちをうまく伝えられないかもしれませんが、話すことで自分の感情を整理でき、少しずつ前向きな気持ちになれることもあります。
まずは、子どもの心に寄り添うことから始めてみてください。
「勉強しなさい」と言わない勇気
多くの親にとって、「勉強しなさい」と言わないのは勇気のいることです。
しかし、不登校の子どもに対して勉強を強制することは、逆効果になる場合が多いです。
「親は何もわかってくれない…」と心を閉ざしてしまうかもしれません。
また、子どもが少しでも前向きな行動を見せたときには、その努力をしっかりと認めてあげてください。
なにもしていなくても、ありのままのあなたが大切だよと伝えていきましょう。
小さな成功体験を増やす工夫
不登校の子どもが勉強に向き合うためには、成功体験を積み重ねることが欠かせません。
小さな成功体験は、勉強に限ったことではありません。
近所の山へ山頂までハイキングしてみる、日帰り旅行を自分で計画していってみるといった体験は、
子どもに「自分にもできる」という自信を与えます。
外に出かけることは、リフレッシュにもなります。
もし、外に出かけることが難しい場合は、オンラインでの活動がおすすめです。
料理やプログラミングなど、興味が持てることで始めると長続きしやすく、
おなじ興味を持つ人との繋がりができるメリットがあります。
学校以外の居場所や人との交流は、毎日の生活の中にハリをもたらすでしょう。
小さな成功体験を繰り返すことで、子どもの自信と意欲が少しずつ回復していくでしょう。
不登校の子どもにおすすめの学習方法
不登校で勉強していない期間があったからといって、決して手遅れではありません。
心が落ち着き、自分のペースを取り戻した後の方が効率よく学べることもあります。
子どもの状況に合わせて、家庭の中で取り入れられる学習方法をまとめました。
- 自主学習(市販の教材)
- オンライン教材
- オンライン型個別指導
- 家庭教師
- フリースクール
- 教育支援センター(適応指導教室)
どの方法が最適かは、お子さんの気持ちや性格、家庭の状況によります。
「焦らず、寄り添う姿勢」を大切にしながら、お子さんが少しずつ「学ぶ楽しさ」を感じられる道を一緒に探しましょう。
1.自主学習(市販の教材)
家庭学習は、そんな子どもの「安心感」を第一に考えた方法です。
まずは心を落ち着けながら、楽しく学ぶ時間を持つことが何より大切です。
メリット
- 価格が安い
- 自分のペースで進められる
- 無料教材や市販ドリルなど気楽に始められる
デメリット
- 自己管理のため継続が難しい
- わからないことを質問できない
- 学びが偏りやすい
2.オンライン教材
通信教育は、わかりやすい教材と自分のペースで学べます。
メリット
- 自分のペースで学習できる
- 添削指導など、学習成果をしっかり見てもらえる
- 楽しみながら学べる教材がある
デメリット
- 添削結果が届くまでのタイムラグがある
- 継続するには子ども自身の意欲が必要
すらら公式サイトはこちら→https://surala.jp/

3.オンライン型個別指導塾
オンライン学習塾は、教室特有のプレッシャーを感じることなく学べます。
メリット
- 専門の先生から分かりやすい指導を受けられる
- 外出せずに自宅で受けられる
- リアルタイム授業と録画授業を選べる柔軟性
デメリット
- 受講回数を増やすと料金が高い
- リアルタイムは決まった時間に限定される
4.家庭教師
家庭教師は、子どもに寄り添いながら指導してくれるため、心の不安を和らげつつ学習できます。
メリット
- 一対一の指導で個別対応が可能
- 得意・不得意に合わせた学習ができる
- 勉強以外の悩みも相談しやすい
デメリット
- 料金が高い
- 教師との相性が合わないと逆効果になることも
5.フリースクール
フリースクールは、学校という枠組みに縛られず、自分らしく学び過ごせる場所です。
メリット
- 学校の勉強以外の教育が受けられる
- 交流や活動の中で成長ができる
- 不登校経験者と交流できる
デメリット
- 料金が高い
- 活動内容が合わない場合、居場所として感じにくいことも
6.教育支援センター(適応指導教室)
教育支援センターは、子どもの「戻りたいけどどうしていいか分からない」という気持ちに寄り添い、復帰を支援する場所です。
メリット
- 専門家が子どもの心理面・学習面を支援してくれる
- 無料または低価格
- 同世代や不登校の人と交流できる
デメリット
- 学習のサポートは少ない
- 学校復帰を目標としているためプレッシャーになることも
- 活動内容が合わない場合、居場所として感じにくいことも
まとめ
不登校で勉強していない期間があると、焦りを感じるのは親として自然なことです。
ですが、子どもたちの未来は、これからの選択肢次第で大きく広がります。
一歩ずつ進める環境と親の温かいサポートがあれば、子どもは自分のペースで再び学びの道を歩み始めます。
今はそのスタート地点に立つ準備期間です。
「大丈夫、一緒に進んでいこう」というメッセージを届けることが、何よりの励ましになります。

