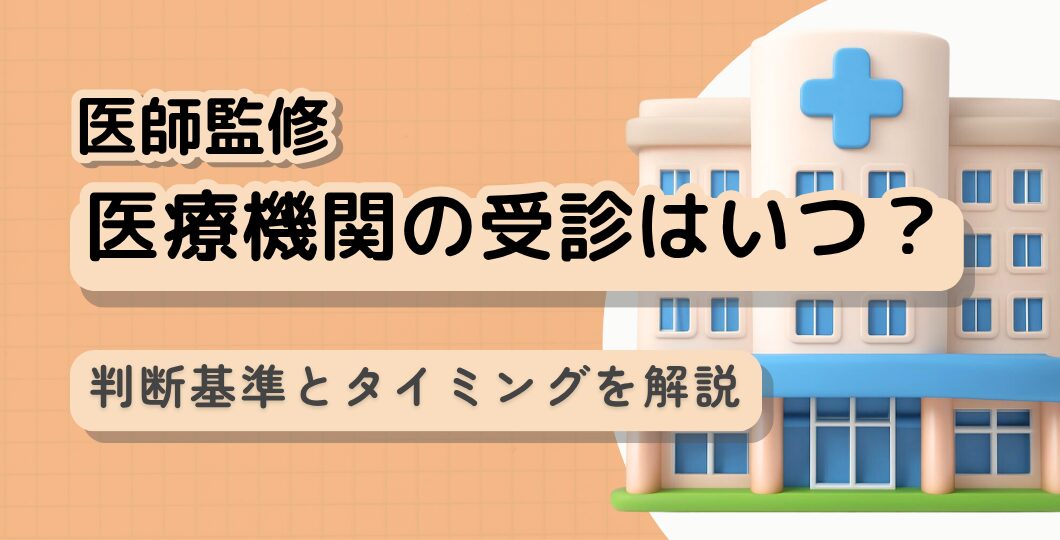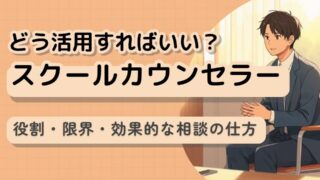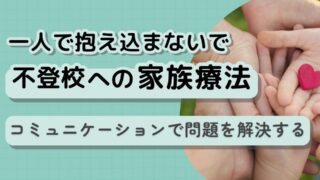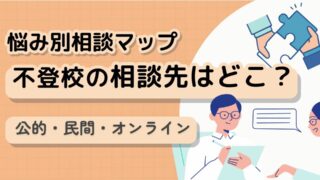「学校に行きたくない」と言う子どもの心の中に、何が隠れているのでしょうか?
不登校の背景には、身体的な不調や精神的ストレス、発達障害や起立性調節障害(OD)などが関係する可能性があります。
子どもは自分の不調をうまく言葉にできないことが多く、「学校が嫌だ」という言葉が、実は身体や心からのSOSである場合も少なくありません。
こんなサインに要注意です:
- 2週間以上続く頭痛や腹痛、食欲不振
- 無気力や気分の落ち込みが続く
- 自傷行為や希死念慮が見られる
このような場合、病院での受診が必要かもしれません。
- 不登校の子どもが病院に行くべきサイン
- 受診先の選び方
- 医療機関で確認できること
早期に適切な診断と対応を行うことで、子ども自身が元気を取り戻し、安心して未来に向かって歩み出すための第一歩をサポートしましょう。
執筆・編集責任:吉田克彦(合同会社ぜんと代表 公認心理師、精神保健福祉士)
- 不登校の家族支援25年以上、3000家庭以上の支援実績
- スクールカウンセラー歴20年以上。小学校、中学校、高校(全日制、定時制、通信制)全ての校種で勤務経験あり。
→詳しいプロフィールはこちら
なぜ不登校と病院が関係するのか?
不登校の背景には、身体的な不調や精神的ストレス、特定の疾患が隠れていることがあります。
子どもは自分の不調を言葉で上手に伝えられない場合があります。
「学校に行きたくない」という理由が、実は身体や心のSOSである場合も少なくありません。
特に、頭痛・腹痛・食欲不振・不眠などの身体的症状や、気分の落ち込み・無気力が続く場合、病院受診で状況を確認することが重要です。
また、不登校の原因として、朝起きられない(起立性調節障害)や発達障害(ADHD・ASDなど)が関与しているケースもあります。これらは専門的な診断と支援が必要です。
専門家として病院を受診をすすめるたった一つの基準
筆者はこれまで25年以上、不登校のお子さんご自身と保護者さんのカウンセリングを行ってきました。
保護者さんからの相談では「病院に連れて行った方がいいのでしょうか」という質問をよく受けます。
その際に、私は次のように答えます。

病院に行かないとできないケアが必要な場合は、病院受診をおすすめします。
病院に行かないとできないケア
問診や血液検査などの医学的検査
体調不良の原因が、精神的なものなのか内臓疾患なのかを確認するために必要な検査を行います。
(注:10年以上前の事例です。)
小学生男児が、毎朝学校に行く時間になると微熱が出るようになりました。
学校に登校で来た日も、休み時間になると保健室で体温を測ると微熱がありました。
あまりに微熱が続くため、養護教諭が「内臓疾患の疑いがあるから病院で検査をした方がいい」と保護者に病院受診をすすめました。
かかりつけの小児科から総合病院に紹介状を書いてもらい精密検査を実施しましたが、以上が見られませんでした。
そこで改めて、「内臓に異常がないならメンタルの問題だから、カウンセラーに相談した方が良い」と筆者のところに相談に来ました。

この事例では、保護者へのカウンセリング2回と養護教諭とのコンサルテーション1回を行い、男児が発熱もおさまり、元気に生活するようになりました。
病院受診をして「内臓疾患の疑いはない」と分かったからこそ、スムーズにカウンセリングができました。
この事例のように、微熱などの身体症状がある場合に、きちんと病院で診察を受けることが大切です。
処方薬を使った薬物治療
病院に行くことで、お薬を処方されることがあります。
お薬を飲むことで、気分が安定したり、イライラが治まるなどの効果も期待できます。

「病院に行ったけれど薬は飲ませていない」というご家庭をよく耳にします。しかし、病院に行った以上は、お薬も含めてトータルで治療をするので、処方されたお薬を飲まないというのはおすすめしません。
依存性や副作用などの不安がある場合は、勝手に服薬をやめるのではなく、ちゃんと医師に相談をしましょう。納得のいく説明をしてもらえたり、別な薬に変えてもらうこともできます。
入院治療
医学的検査を踏まえて、このままでは命の危険があるような場合に入院治療が必要となります。
特に以下の状態の場合は注意が必要です。
- 自傷行為や暴力行為がひどい
- 食事がとれず痩せている
- 幻覚や幻聴、妄想などが目立つ

医療機関でない民間機関で、寮生活で不登校を改善を目指す相談機関はありますが、おすすめしません。
不登校の子どもが病院に行くべきサイン

身体の症状が続いている場合
2週間以上、以下の身体症状が続く場合は受診を検討しましょう。
- 頭痛・腹痛・吐き気
- 食欲不振・体重減少
- 不眠・昼夜逆転
- 身体のだるさ・無気力
特に、朝起きられない、立ちくらみやめまいなどがある場合は、起立性調節障害(OD)が疑われます。
この疾患は自律神経系の問題であり、不登校につながることがあります。
起立性調節障害の場合の対応
起立性調節障害(OD)が疑われる場合、小児科で以下の検査や治療を受けられる可能性があります:
- 血液検査(貧血や甲状腺疾患)
- 睡眠検査
- 血圧を上げる薬物療法
気分の落ち込み・無気力の継続
「以前は好きだったことに興味を示さなくなった」「笑顔が減った」と感じた場合、要注意です。
趣味や友だちとの交流を避けるようになった場合、うつ症状や発達障害による二次障害(例:ADHDによる自信喪失)が関与している可能性があります。
【関連記事】
【スクールカウンセラーが解説】ADHD(注意欠陥多動症)と不登校の関係
不登校と子どものうつ病の関係と対応を正しく理解しよう:公認心理師が解説【医師監修】
自傷行為・希死念慮が見られる場合
リストカットや命に関わる発言が見られる場合は、すぐに医療機関に相談してください。
これは本人から発せられる重要なSOSであり、早期対応が不可欠です。
どんな病院に行けばよいのか?

まずは小児科・かかりつけ医に相談
身体症状がある場合、かかりつけの小児科で相談することが基本です。
小児科医は成長過程を把握しており、身体的な異常だけでなく心理的問題にも気づきやすいです。
必要に応じて心療内科や精神科への紹介をしてくれます。

児童精神科や心療内科の数が少なく、予約が取りにくい場合があります。
予約を待っている間に状況が悪くなることもありますので、まずはかかりつけの小児科に相談をすることをおすすめします。
必要なら紹介状を書いてもらうと、スムーズに進みますよ。
中学生以上の場合は心療内科・精神科も選択肢
気分の落ち込みや情緒不安定が続く場合、中学生以上では心療内科・精神科への相談も視野に入れましょう。
ただし予約待ち期間が長いこともあるため、早めに相談することが重要です。

初回の診察まで半年以上待つこともあります。大規模病院などでは、1~2年待ちのところもあります。
予約を入れることも大事ですが、待っている間にできることもあります。
医療機関で確認できること・できないこと
- 身体的症状の診断・治療
- 精神疾患(うつ病など)の診断と薬物療法
- 起立性調節障害や発達障害への対応
- 入院しての治療
医療機関でできないこと(期待できないこと)
- 学校との調整(スクールカウンセラーなどとの連携が必要)
- 家庭環境改善(心理カウンセリングなど外部支援機関を利用)
病院受診時の準備とフォローアップ
受診時に準備すべき情報
不登校の受診の場合は、聴診器やレントゲンなどの情報よりも説明の内容が重要になります。
診察時間は限られています。
また緊張しているために「あぁ、もっとちゃんと説明すればよかった」と後悔することもあります。
後悔しないように、受診する際には事前に以下の情報を準備しておきましょう。
- 症状の経過(発症時期・頻度)
- 学校での様子(友だち関係など)
- 母子手帳・健康診断結果
診断結果後の対応とフォローアップ
医師から処方された治療計画を理解しつつ、必要なら心理療法やスクールカウンセラーとの併用も検討しましょう。
家族間で情報共有しながら進めることが大切です。
本人の治療だけでなく、家族へのサポートも重要
お子さんが不登校になり、お子さんではなくご家族が病院受診をする場合もあります。
お子さんを心配するあまり、ご家族が不眠や食欲不振などの場合は、病院受診も検討しましょう。
また、ご家族のメンタルヘルスが安定したり、病気が改善することで、お子さんの不登校が改善される場合も少なくありません。
病院受診をした方が良いかどうかわからない場合は、私たちの無料相談で一緒に考えましょう。
家族支援の重要性
不登校児童生徒への支援には家族全体へのアプローチも欠かせません。
親自身がストレスを抱えすぎず、専門家から助言を得ることで子どもの回復を促進できます。
地域資源との連携
教育支援センターや相談窓口では、不登校児童生徒への個別指導やカウンセリングを提供しています。
これらを活用しながら学校復帰を目指すことも有効です。
さまざまな相談機関がありますので、状況に合わせて使い分けましょう。
よくある質問
Q子どもが病院受診を拒否します。どうすればいいでしょうか?
保護者の方だけ受診できる病院が多くあります。
まずは、事前に電話などで問い合わせて「受診させたいのだが、本人が拒否するかもしれない。」と伝えてみましょう。不登校の相談に強い病院は、そのような問い合わせに慣れているので、具体的に答えてくれます。
Q病院に問い合わせる際に、どんなことを話せばいいでしょうか。
聞かれたことを答えれば大丈夫です。わからない時や、答えたくない時は、正直に「それは答えにくい」と伝えればよいです。
基本的には、以下の内容をメモで準備しておけば大丈夫です。
・基本情報:お子さんの学年、性別、家族構成
・これまでの経緯:不登校になった時期、きっかけ、
・現在の状況:就寝時間、起床時間、食欲の有無、暴力や暴言の有無など
Q子どもに薬を飲ませることに抵抗があります。
「一度薬を飲むと、一生飲み続ける必要があるのでは」「薬物依存になるのでは」「副作用があるかも」などと、心配です。
「一度薬を飲むと、一生飲み続ける必要があるのでは」「薬物依存になるのでは」「副作用があるかも」などと、心配です。
正直に医師に質問をして、説明をしてもらいましょう。
基本的には病院に受診をする以上は医師の指示に従って、必要な薬の服用はすべきです。
処方された薬を飲まずに「飲んでます」とウソをつくのは、絶対にNG。
適切な治療にならず、お子さんのためになりません。
Q病院に初診を申し込んだら、一年以上先しか予約が取れませんでした。
その間、何をすればいいでしょう。
その間、何をすればいいでしょう。
お子さんの状況に寄りますが、初診を待っている間に出来ることはたくさんあります。
スクールカウンセラーに相談するのもいいですし、他の病院に聞いてみることもできます。
お悩みの場合は、まずは私たちの初回無料相談で一緒に考えませんか。
適切に医療機関を利用して、子どもの生活の質を向上させよう
お子さんが不登校になった時に、病院受診も選択肢の一つに入れておきましょう。
実際に受診が必要かどうかは、状況によって変わってきます。
選択肢として準備しておくことで、冷静に対応できます。
お子さんにとって必要な支援を考えていきましょう。