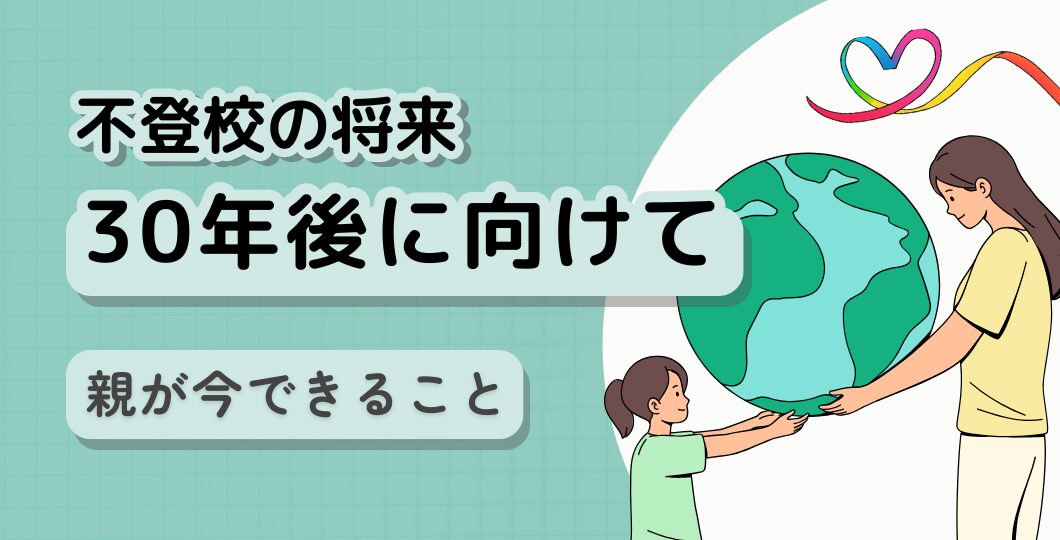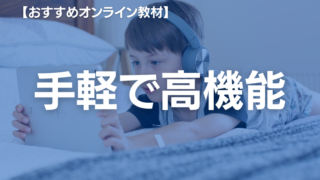お子さんの不登校に直面し、毎日不安や焦りを感じていらっしゃるのではないでしょうか。
「このまま学校に行けなくなったらどうなるの?」「将来に影響はないの?」そんな心配は当然のことです。
しかし、少し視点を変えて、30年後のお子さんの姿を想像してみてください。幸せな人生を送るために本当に必要なものは何でしょうか?
実は、それは「学校に行くこと」そのものだけではないのです。

私は、不登校のご家族へのカウンセリングを25年以上続けています。
その経験から、不登校のお子さんの将来を考える上で、必要な保護者のマインドを紹介します。
この記事を読むことで、不登校のお子さんへの接し方の柱ができるはずです。
執筆・編集責任:吉田克彦(合同会社ぜんと代表 公認心理師、精神保健福祉士)
- 不登校の家族支援25年以上、3000家庭以上の支援実績
- スクールカウンセラー歴20年以上。小学校、中学校、高校(全日制、定時制、通信制)全ての校種で勤務経験あり。
→詳しいプロフィールはこちら
再登校がゴールではない4つの理由
不登校支援の本当のゴールは、登校再開のみを目指すのではなく、30年後に満足した人生を送れる力を育むことです。もちろん、お子さんによっては学校復帰が最適な選択となる場合もありますが、それだけが唯一の道ではありません。
- 無理な復帰は心身の二次被害を招くことがある
- 学力・体力・人間関係のバランスが将来の自立に重要
- 成長の場は学校以外にもある
- 長期的視点で見ると親子とも安心感が増す
例えば、登校に固執して無理に学校へ通わせたケースでは不調が悪化し高校を中退する事例がある一方で、
在宅学習で自分の強みを伸ばし専門職に就いた例もあります。
これらはあくまで一例であり、お子さん一人ひとりに合った道があります。大切なのは「今」だけでなく「将来」を見据えた支援なのです。
不登校の子どもの自立を支える三本柱:学力・体力・人間関係
お子さんの将来の自立と社会参加に必要なのは、「学力」「体力」「人間関係」の三本柱です。
学校に行くことだけが解決策ではないことを理解し、これら三つの要素をバランスよく育むことが大切です。
【学力】”広義の学び”を不登校の子どもに家庭で伸ばすコツ
学びは教科書や学校だけにあるわけではありません。
日常生活の中にこそ、不登校の子どもにとって貴重な学びの機会があります。
なぜなら、子どもたちは体験を通して五感で学び、知識を定着させるからです。
料理をきっかけに興味関心を広げたAさん
Aさんは、学校を休むことになり、お昼ご飯を準備することになりました。
料理を始める中で、最初はゆで卵の茹で時間の硬さの違いに興味を持ちはじめました。他にも、分量の計算(算数)、調理過程の変化(理科)、食材の産地(社会)など、様々な学びが得られます。
また、興味のあるテーマについて調べる習慣をつけることで、自ら学ぶ力が育まれます。
小学生:遊び×学びで土台づくり
小学生の不登校支援では、机に向かう勉強だけではなく、遊びを通した学びが重要です。
遊びや生活体験の中にこそ、学びの芽がたくさん隠されているからです。
例えば、公園での遊びは体力や社会性を育み、絵本を読むことは想像力や語彙力を豊かにします。
家庭での料理やお手伝いも、学びの貴重な機会です。
遊びや生活を通して、知的好奇心を刺激し、学ぶことの楽しさを体験させてあげましょう。
中学生:主体的な学びと生活リズムの確立
中学生の不登校支援では、自分の興味や関心に基づいて主体的に学ぶ姿勢を育てることが重要です。
将来の進路選択に向けて、自分に必要な知識やスキルを自ら獲得していく必要があるからです。
例えば、興味のある分野の本を読んだり、オンラインの講座を受講したり、地域の活動に参加したりすることも立派な学びです。
将来の目標を持つことが、自主的な学びの大きな原動力となります。
お子さんの興味関心を引き出し、自分で目標を設定し、学びを進めていくサポートをしましょう。
高校生:将来を見据えた専門的な学び
不登校を経験した高校生は、将来の社会参加に向けて、より専門的な知識やスキルを身につけることが重要です。
大学進学や就職など、具体的な進路選択が近づいてくるからです。
例えば、学校の授業だけでなく、インターンシップに参加したり、資格取得を目指したり、ボランティア活動に取り組んだりすることも有効です。
社会とのつながりを意識した学びを通して、将来のキャリアを具体的に描けるようにサポートしましょう。
【体力】不登校の子どもの心と体のエネルギーを満たす仕組み
「睡眠・栄養・運動」の基本習慣が学習効率とメンタルの安定を底支えします。
不登校支援において、この土台づくりは非常に重要です。
体調不良は学力低下や社会参加回避のリスク因子となるためです。
実際に、睡眠時間が7時間から8時間に増えたことで、頭痛の頻度が週4回から1回へと大幅に減少したケースもあります。
体調の改善が心の余裕を生み、学習への意欲にもつながるのです。
これはあくまで一例であり、お子さん一人ひとりの変化のペースは異なります。
小学生:笑顔あふれる!遊び運動&バランス食
不登校の小学生の健康は、遊びを中心とした適度な運動とバランスの取れた食事が基本です。
心身の発達が著しいこの時期に、健康的な生活習慣を身につけることは、将来の健康な生活を送る上で非常に重要だからです。
例えば、毎日外で元気に遊ぶ時間を作ったり、好き嫌いなく色々な種類の食べ物を食べるように促したりすることが大切です。
家族みんなで食卓を囲み、楽しい食事の時間を共有することも、心身の健康に繋がります。
遊び、運動、食事を通して、不登校のお子さんの健やかな成長をサポートしましょう。
中学生:ぐっすり眠って元気チャージ!睡眠と生活リズム
不登校の中学生にとって質の高い睡眠は、心身の成長と学習意欲を維持するために不可欠です。
成長ホルモンが多く分泌される睡眠時間は、体の成長だけでなく、脳の休息や記憶の定着にも重要な役割を果たすからです。
例えば、毎日同じ時間に寝起きする習慣をつけたり、寝る前にスマートフォンやゲームの使用を避けたりする工夫が大切です。朝食をしっかり食べることも、体内時計を整える上で重要です。
規則正しい生活リズムの中で、十分な睡眠時間を確保できるようにサポートしましょう。
高校生:自分で守る!健康管理と心のケア
不登校を経験した高校生になると、自身の健康管理能力がより一層求められます。
進路や人間関係など、ストレスを感じやすい時期でもあるため、心身のバランスを保つことが重要だからです。
例えば、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠を心がけるとともに、ストレスを感じた時の対処法を身につけることも大切です。
悩みがある場合は、信頼できる人に相談することも有効な手段です。
自身の心と体の状態を理解し、主体的に健康管理ができるようにサポートしましょう。
【人間関係】不登校の子どもに必要な”上手な距離感”が社会を生き抜く鍵
友達の数よりも”距離の取り方”のスキルが、将来の対人ストレスを減らします。
不登校支援において、この視点は非常に重要です。
過剰な同調や依存は燃え尽きを招きやすいからです。
例えば、苦手な同級生との間に「半径2mルール」を設けて適度な距離を保ちながら、好きな友達とは「週2回のオンライン通話」という形で良好な関係を維持している子もいます。
自分に合った距離感で人と関わる力が、社会を生き抜くために重要なのです。
これはひとつの例であり、お子さんに合った関わり方を見つけることが大切です。
小学生:はじめの一歩!コミュニケーションの基礎
不登校の小学生にとって、基本的なコミュニケーション能力を身につけることは、社会生活を送る上での第一歩です。
友達や先生との関わりを通して、相手の気持ちを理解したり、自分の気持ちを適切に伝えたりする力を養う必要があるからです。
例えば、挨拶をしっかりする、相手の目を見て話を聞く、感謝の気持ちを言葉で伝える、などが基本となります。遊びを通して、協力することや順番を守ることの大切さを学ぶことも重要です。
家庭や少人数の安心できる環境での関わりを通して、コミュニケーションの基礎をしっかりと身につけられるようにサポートしましょう。
中学生:多様な立場での関わり
不登校の中学生には、家族以外の多様な人間関係を築く経験が重要です。
段階的に社会との接点を増やしていくことが効果的です。
異なる価値観や考え方を持つ人々と関わることで、広い視野と柔軟な対応力を身につけることができるからです。
例えば、まずはオンラインでの交流から始め、少人数の活動、地域の活動などへと徐々に参加範囲を広げていくことで、様々な立場の人と協力したり、意見を交換したりする経験を積むことができます。
時には意見が対立することもあるかもしれませんが、建設的な話し合いを通して解決する力を養うことも大切です。
お子さんのペースに合わせて、様々な活動への参加を促し、他者との関わりを通して社会性を育んでいきましょう。
高校生:自分で考えて、伝える。対話と自己主張のバランス
不登校を経験した高校生は、自分の考えや意見をしっかりと持ち、適切に表現する力を身につけることが将来の社会参加に向けて重要です。
社会に出た際に、他者と協力しながら課題を解決したり、自分の権利や主張を守ったりする必要があるからです。
例えば、少人数での討論や共同作業など、自分に合った形での活動を通して、論理的に思考し、自分の意見を分かりやすく伝える練習をしたり、相手の意見を尊重しながら建設的な対話を進める力を養ったりすることが大切です。
自分の考えを持ち、自信を持って他者とコミュニケーションできる力を身につけられるようにサポートしましょう。
学校は「手段の一つ」──不登校からの回復3つのリアルケース
不登校の状況から回復するためのアプローチは一つではありません。
お子さんの個性や状況に合わせた支援方法を選ぶことが大切です。
ここでは、実際のケースをご紹介します。
これらはあくまで参考例であり、すべての子どもに同じ道筋が合うわけではありません。
ケース① 在宅プリント学習で再起動した不登校支援の例
安心できる環境で成功体験を積み重ね、自己効力感を回復させることが大切です。
外的ストレスが低い環境ほど「できた!」という経験を蓄積しやすいからです。
実際に、2年間の在宅学習を経て、中学校に入学してからは皆勤賞を獲得し、大学の教育学部へと進学を果たした例もあります。
安心できる環境での小さな成功体験が、自信を育み、次のステップへの原動力となるのです。
このケースはひとつの例であり、お子さんに合った段階的な復帰プランを考えることが大切です。専門家のサポートを受けながら進めることもおすすめします。
8月は入会金(11000円)が無料!!まずは無料の資料請求を
→ 無学年制教材!アニメによるインターネット教材【すらら】資料請求
ケース② いじめ休養から安全基地づくりで回復した例
“安全基地”を確保した後、段階的な外出を通じて社会復帰に成功した例があります。
PTSD様の症状は、安全が確保されない限り改善しにくいからです。
具体的には、まず週1回の図書館通いから始め、次にフリースクールへの参加、そして定時制高校への転入というステップを踏みました。安全な環境で少しずつ社会との接点を増やしていくことで、自信を取り戻していったのです。
このアプローチは一例であり、お子さんの状況や回復のペースに合わせた段階的な支援が重要です。
ケース③ 集団が苦手でも才能を伸ばした不登校支援の成功例
得意分野に専念し、専門的な進学ルートを通じて自立を開始しました。
強みにフォーカスすることで、自己肯定感とキャリア形成を同時に促進できるからです。
例えば、3Dモデリングを独学で学び、ゲーム会社でのインターンシップを経験し、専門学校の特待生として進学した例があります。
「集団が苦手」という特性があっても、自分の強みを活かす道を見つけることで、社会での自立を実現できるのです。
このケースから学べるのは、不登校であっても「できないこと」ではなく「できること・好きなこと」に焦点を当てた支援の大切さです。
不登校支援の行動ガイド:学年別3本柱チェックリスト
9項目のセルフチェックリストを活用することで、最優先の課題を即座に特定することができます。不登校支援のための具体的な指針となります。
課題を可視化することで迷いが減り、行動の第一歩を踏み出しやすくなるからです。
例えば、「体力-中学生」の項目で1つしかチェックがつかなかった家庭では、朝の散歩と就寝30分前のスマホOFFというルールを2週間続けたところ、寝付きの時間が15分早くなるという効果が見られました。
小さな習慣の積み重ねが、大きな変化につながるのです。
お子さんの状況に合わせて、無理のないペースで取り組むことが大切です。
不登校の子どもを持つ親御さんの願いと自己肯定感のバランス
お子さんの将来のために何が最善かを考える中で、親としての願いとお子さんの自己肯定感のバランスを取ることが大切です。
「友達を増やしてほしい」気持ちは自然
お子さんに友達をたくさん作ってほしいと願うのは、不登校の子どもを持つ親として自然な気持ちです。
友達との関わりを通して、社会性や協調性など、生きていく上で大切なことを学ぶことができると考えるからです。
実際に、友達との楽しい思い出は、子どもの心を豊かにし、成長の糧となります。
しかし、友達の数だけが重要なのではなく、質の高い人間関係を築けるようになることの方が大切です。
不登校の子どもにとって、無理に多くの友人を作ることよりも、少数でも安心できる関係を築くことが重要な場合が多いです。
こだわり過ぎが招く落とし穴
登校することなど一つのことにこだわりすぎるのは危険です。
不登校支援において、多様な選択肢を視野に入れることが重要です。
うまくいかなかったときの逃げ道がなくなり、小さな良い変化を見落としてしまうからです。
例えば、学校でいじめを受けていたにもかかわらず、家庭からは登校を無理強いされたために「生きている意味」がなくなってしまったケースがあります。また、家庭では生活リズムも安定しており、勉強もできていたにもかかわらず、「学校に行くこと」にこだわりすぎて、「全然できていない」と自信を喪失してしまったケースもあります。
お子さんの状況に合わせた柔軟な対応と、小さな成長を認める視点が大切です。段階的な学校復帰も、完全な在宅学習も、フリースクールの活用も、すべてはお子さんに合った選択肢です。
よくある不登校に関する質問:保護者の不安を解消するために
- Q不登校になると将来の進学や就職に影響しませんか?
- A
必ずしもそうとは言えません。学校教育で得られるものは、他の方法でも獲得可能です。
大切なのは「学力」「体力」「人間関係」の三本柱をバランスよく育むことです。実際に、不登校を経験しながらも、自分に合った学び方を見つけ、社会で活躍している方は多くいます。
高校は通信制や定時制、単位制など様々な選択肢があり、大学入試においても、高校卒業程度認定試験(旧大検)などの道があります。 不登校の子どもの様子を見守るだけで、いつまで待てばよいのでしょうか?明確な「待つ期間」はありません。大切なのは「待つ」だけでなく「見守りながら支援する」姿勢です。お子さんの状態を観察し、「学力」「体力」「人間関係」のどの部分から支援を始められるか考えましょう。
小さな変化を見逃さず、根気強くサポートを続けることが重要です。完全に回復するまで何もしないのではなく、お子さんが安心できる環境の中で、少しずつ挑戦できるチャンスを提供していくことが効果的です。
専門家のサポートを受けながら進めることで、より適切な支援が可能になります。ぜんとカウンセリングでは、お子さんの状況に合わせた段階的な支援プランをご提案しています。
- Q不登校の子どもを持つ親として家庭で何をすればよいですか?
- A
まずはお子さんの心身の安全基地となることです。その上で、三本柱に沿った支援を考えましょう。
例えば、興味のある分野の本や教材を用意する(学力)、一緒に散歩する習慣をつける(体力)、家族以外との安心できる交流の機会を作る(人間関係)などが具体的な支援になります。
何より大切なのは、お子さんの小さな成長を認め、励ますことです。ぜんとカウンセリングでは、保護者の方が家庭でできる具体的な支援方法についてのアドバイスも行っています。
フリースクールや適応指導教室などの支援機関を利用するべきですか?お子さんの状況や性格によって最適な選択は異なります。フリースクールや適応指導教室は、学校とは異なる環境で学びや交流の機会を提供する貴重な場ですが、すべての子どもに合うわけではありません。
まずはお子さんと十分に話し合い、見学などを通して雰囲気を確かめることをおすすめします。無理強いせず、お子さんのペースを尊重することが大切です。
費用や通いやすさなども含め、総合的に検討する必要があります。ぜんとカウンセリングでは、お子さんに合った支援機関の選び方についてもアドバイスしています。
30年後「当時はいろいろあったな」と笑い話になるために
30年後の自立を見据え、学力・体力・人間関係を家族で育てる旅を今日から始めましょう。
不登校支援は長期的な視点を持つことが何よりも大切です。
3本柱はどこから着手しても相互に波及し、成長の好循環が生まれるからです。
例えば、学力の補強から始めたことで自信がつき、体力改善につながり、最終的に友達作りへと波及した家庭のように、一つの分野での成長が他の分野にも良い影響を与えることがあります。
こうした相乗効果は、様々な不登校支援のケースで見られています。
お子さんの「今」だけでなく「将来」を見据え、それぞれの家庭に合ったペースで、一歩ずつ前に進んでいきましょう。不登校は人生の通過点に過ぎません。
大切なのは、お子さんが自分らしく生きる力を育むこと。
私たち「不登校なんでも相談室」は、公認心理師と医師による専門的な知見を活かし、その道のりをしっかりとサポートします。親御さんの不安や悩みも含めて、一緒に考えていきましょう。
不登校でお悩みの際は、ぜんとカウンセリングにご相談ください。医師が監修し、公認心理師が執筆する専門的な情報と、温かい支援であなたとお子さんの未来をサポートします。