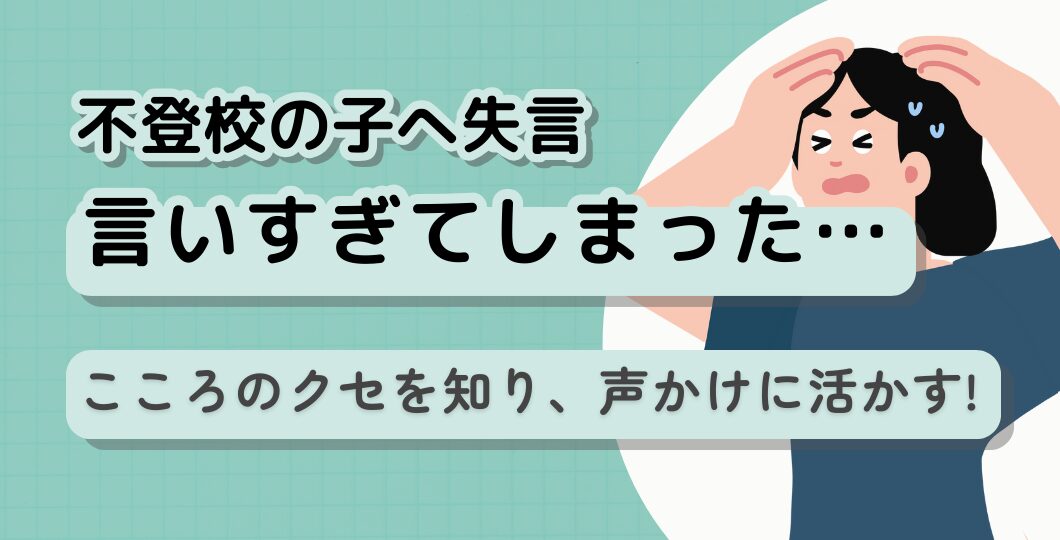「子どもが落ち込むから言うまいと決めていたのに、また言ってしまった」
「もっと優しく声掛けをしたいのに、ついつい厳しい言葉が出てしまう」
子どもが学校に行かない状況が続くと、ついつい発言もネガティブになってしまうことがあります。
何度言っても変わらないから無意味だとわかっているのに、子どもを前にするとついつい小言を言ってしまう。
お子さんの不登校について、保護者さんとカウンセリングをしていると、このようなお悩みを頻繁に聞きます。
このような発言の背景には、人間ならだれでも抱えている「こころのクセ」が影響しています。
この記事では、不登校の子どもを持つ保護者が陥りやすい「6つの心のクセ」を紹介します。
「こころのクセ」が普段の声掛けにどのような影響を与えているか、
そして、どうすればそのクセから抜け出しやすくなるかをご紹介します。
執筆・編集責任:吉田克彦(合同会社ぜんと代表 公認心理師、精神保健福祉士)
- 不登校の家族支援25年以上、3000家庭以上の支援実績
- スクールカウンセラー歴20年以上。小学校、中学校、高校(全日制、定時制、通信制)全ての校種で勤務経験あり。
→詳しいプロフィールはこちら
カウンセラーは見た!人が陥りやすい思考のクセ6選
1. 0か100か思考(All-or-Nothing Thinking)
0か100か思考の特徴
この思考は、物事を「白か黒」「成功か失敗」でしか捉えられなくなる思考です。
「失敗したらすべて意味がない」と考え、過度に完ぺきを目指してしまいます。
0か100か思考のによる発言の例
「また学校に行けなかった…やっぱりうちの子はダメなんだ」
「1回だけしか登校できないなら、学校に行かないほうがまし」
「放課後しか学校に行けないなんて、意味がない」
どうして危険?
「完璧じゃなければ失敗」と感じてしまうと、子どもの小さな進歩や努力が見えなくなります。
「今日は布団から出られた」「少し笑顔が増えた」…その一歩を認める視点が大切です。
「また行けなかったの?」「ちゃんとしないとダメじゃない!」など、できた部分を無視した厳しい声かけになります。
その結果、子どもは自信を無くしていき、失敗を恐れて小さな挑戦をしなくなってしまいます。
どうすれば抜け出せる?
“全部かゼロか”ではなく、「今日は○○ができたね」と部分的な変化を言葉にする習慣を意識してみましょう。
「今日はここまでできたね」「少し休めたね」など、完璧でなくても良いことを伝える言葉を意識してみましょう。
2. 過度の一般化(Overgeneralization)
過度の一般化の特徴
過度の一般化とは、1つの出来事を根拠に、未来全体を否定的に見てしまう思考を指します。
過度の一般化の具体例
「このままずっと学校に行けないままだと思う」
「こんな調子じゃ、将来は引きこもりになるに決まってる」
「あなたは、いつもそうなんだ」
「みんなに笑われるよ」
どうして危険?
子どもは日々変化していきます。
学校を少し休んだだけで未来を決めつけることはできません。
未来を決めつけることによって、この後紹介する「こころのフィルター」も加わって、決めた方向に進んでしまうこともあります。
どうすれば抜け出せる?
「今日はどうだった?」と1日単位の事実に注目して話してみると、不安が少し和らぐこともあります。
「今日はこうだったけど、明日は違うかもしれないね」と、可能性を残す言葉を意識することも大切です。
3. 心のフィルター(Mental Filter)
こころのフィルターの特徴
ネガティブな面だけに意識が集中してしまう思考
具体的な例
「昨日は笑ってたけど、やっぱり今日は布団から出なかった」
「先週1週間は調子よかったけれど、今日は機嫌が悪いし、やっぱりだめだ」
どうして危険?
良い変化も「例外」として片付けてしまいがちです。“昨日の笑顔”は、未来への大切な兆しかもしれません。
「笑顔だったけど、結局○○はできなかったじゃない」のように、良い点を打ち消すような声かけにつながり、子どもの自己肯定感を削いでしまう可能性があります。
どうすれば抜け出せる?
その日の終わりに「今日よかったことを1つだけ振り返る」時間を作ってみましょう。ポジティブな視点が少しずつ育ちます。「昨日は笑顔が見られて嬉しかったな」と、良かった点を素直に伝える言葉を大切にしましょう。
4. マイナス化思考(Disqualifying the Positive)
マイナス化思考の特徴
良い出来事を「意味がない」と否定してしまう思考
具体的な例
「1日登校できても、どうせまた行けなくなるんでしょ」
「『気にしなくていいよ』と言っていたけれど、本当はイヤそうな表情をしていた」
どうして危険?
登校できたという事実そのものを認められず、自信や達成感が育ちにくくなります。
「そんなのたまたまよ」「今回だけできても意味ないでしょ」など、子どもの頑張りや成果を素直に認められない声かけになりがちです。
どうすれば抜け出せる?
「今日は登校できたね」と“できたこと”だけを切り出して肯定する声かけが有効です。
たとえ一度きりでも価値はあります。
「登校できたこと、すごいね」「○○できたね、良かったね」と、できた事実そのものを具体的に言葉にして認めることが大切です。
5. 結論の飛躍(Jumping to Conclusions)
結論の飛躍とは
根拠がないままに、悪い未来を決めつけてしまう思考
具体例
「どうせこの子はこのまま引きこもるに違いない」
「学校に行けないと将来就職もできない」
どうして危険?
未来の予測は誰にもできません。不安が膨らみすぎると、「今」できる支援や関わりが見えなくなってしまいます。
根拠がないままに「あなたはどうせ無理だから」「将来が心配だわ」といった、不安を煽るような決めつけの声かけをしてしまうことがあります。
どうすれば抜け出せる?
「まだわからない」「今日はまだ途中」と“保留”の視点を持つことで、焦りすぎずに済みます。
「今はまだ分からないね」「少しずつ見ていこうか」と、焦らず見守る姿勢を示す言葉を意識しましょう。
6. 感情的決めつけ(Emotional Reasoning)
感情的な決めつけとは
不安や悲しみといった感情を「現実の証拠」だと思ってしまう思考
具体的な例
「私は不安でたまらない。だからこの子の将来はもうだめなんだ」
どうして危険?
感情は確かにリアルですが、「現実=感情」とは限りません。
気持ちが強いほど、現実判断がゆがんでしまうこともあります。
不安な気持ちから「もうお先真っ暗だわ…」「こんな状態でどうするの!」など、感情的な言葉で子どもを追い詰めるような声かけにつながることがあります。
どうすれば抜け出せる?
不安な気持ちを紙に書き出してみる、信頼できる人に話してみる、「不安=悪い未来」とすぐに結びつけないよう意識することが大切です。
自分の感情に気づいたら、一呼吸おいて。「ママも不安なんだ」とI(アイ)メッセージで伝えるなど、感情をそのままぶつけない工夫も有効です。
声かけを意識することで、子どもが元気になる
ここまで紹介した「心のクセ」は、不登校に直面した保護者であれば誰でも経験しうる自然な反応です。公認心理師の視点からも、まずこの「気づき」が変化の大きな一歩になると感じています。
だからこそ、まずは「あ、今自分はこんな風に考えているかも」と気づくことが何よりの第一歩。
思考のクセに気づけると、自分を責めることが減るだけでなく、子どもの小さな成長を見逃さなくなり、声かけや関わり方の選択肢も自然と増えていきます。
自分自身に問いかけてみましょう
最近、「どうせ」「また」「このままじゃ」などの言葉をよく使っていませんか?
子どもの良い変化を「たまたま」「意味がない」と思っていませんか?
不安や焦りといった感情に引っ張られて、未来を悲観していませんか?
- 小さな変化を一緒に喜ぶ(例:笑顔になれた、朝ごはんを食べられた)
- 未来を決めつけず、今の小さな一歩を大事にする
- 「今日は〇〇できたね」と肯定的な声かけを意識する
- 不安な気持ちを書き出す/話す/ひとまず保留にしてみる