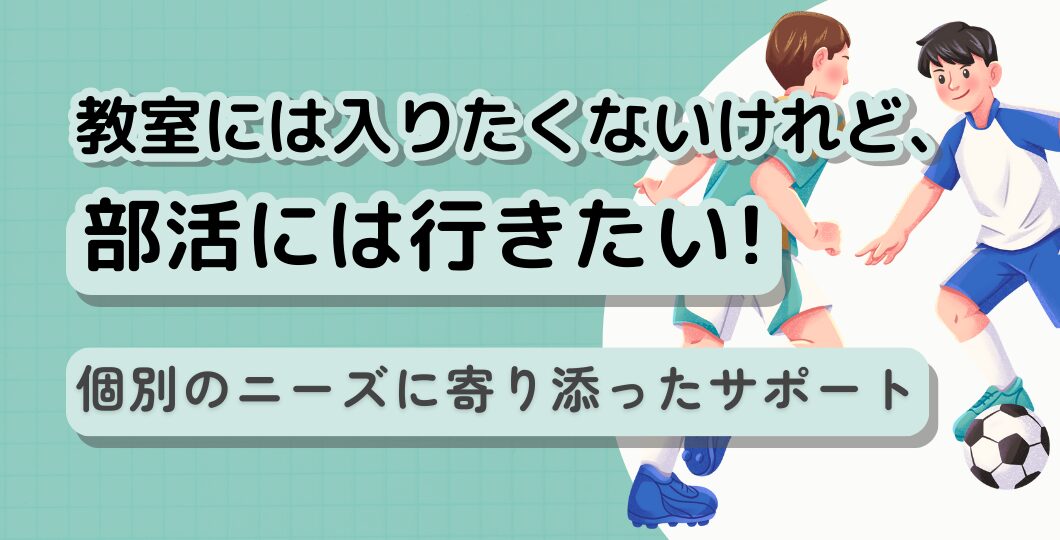不登校の子どもが「学校は行けないけど、部活だけは行きたい」と話すことがあります。
この状況に、戸惑いや心配を感じる保護者の方も多いのではないでしょうか。
部活動に行きたいという気持ちは、子どもなりに「やってみたいことがある」「人と関わりたい」という前向きなサインでもあります。
一方で、学校生活のすべてに安心感を持てていない背景があることも少なくありません。
この記事では、不登校の子どもが部活にだけ参加したいとき、保護者や学校がどのように受けとめ、どのようにサポートしていけばいいのかを具体的に解説します。
「今の子どもにとって何が大事か」「どう関わればよいか」のヒントとしてお読みいただければ幸いです。
執筆・編集責任:吉田克彦(合同会社ぜんと代表 公認心理師、精神保健福祉士)
- 不登校の家族支援25年以上、3000家庭以上の支援実績
- スクールカウンセラー歴20年以上。小学校、中学校、高校(全日制、定時制、通信制)全ての校種で勤務経験あり。
→詳しいプロフィールはこちら
子どものニーズの理解
まず、子どもが部活にのみ興味を示す理由を探ることが重要です。部活動が子どもにとって以下のような意味を持っています。
部活に行きたい理由
- 自分の得意分野や情熱を発揮できる場
- 友達との絆を感じられる場
- 学業のプレッシャーから解放される場
子どもと率直に対話し、学校生活全般への不安や問題点を理解することが、適切なサポートの第一歩となります。ただし、不登校の子どもの状況は個々に異なるため、一人一人のニーズや特性に合わせた柔軟な対応が求められます。
学校との連携
次に、学校側と連携し、子どもが部活動に参加しやすい環境を整えることが重要です。以下のような点を学校と協議しましょう。
学校との検討事項
- 子どもの状況を踏まえた上で、部活動への参加をすること
- 部活動の日程や活動内容の中で参加する場合としない場合を調整して、子どもの負担を軽減すること
- 部活動の顧問や部員が部活だけ参加する子の事情を理解し、適切にサポートすること
学校側と連携する際には、部活動への参加が最終的な目標ではなく、あくまでも学校復帰へのステップであることを共有しましょう。子どもの状況に応じて、学校側と協力しながら、段階的に学校生活への完全な復帰を目指すことが重要です。
個別の再登校計画
部活動への参加を足がかりとして、徐々に他の学校活動への参加を促していくことが大切です。ただし、不登校の子どもの状況は多様であるため、画一的な再登校に向けた計画ではなく、一人一人に合わせた個別計画が必要です。以下のようなステップを参考に、子どもと相談しながら、無理のない範囲で学校生活への復帰を進めていきましょう。
子どものペースを尊重し、柔軟にプランを調整していくことが肝要です。
心理的サポートの重要性
不登校の子どもは、学校生活全般に対する不安やストレスを抱えていることが多いです。
心理的なサポートを提供することが不可欠です。以下のような方法が考えられます。
不登校の子への心理サポート
- 子どもの意向を尊重しながら、必要に応じてカウンセリングを検討する
- 学校の教職員やスクールカウンセラーと定期的に情報共有し、子どもの状況を把握する
- 家庭内で子どもの気持ちを受け止め、安心して話せる環境を作る
ただし、心理的サポートの方法は子どもによって異なります。
カウンセリングに抵抗を感じる子どももいれば、学校との面談が負担になる子どももいるでしょう。
子どもの個性やニーズに合わせて、柔軟にサポート方法を選択していくことが大切です。
家庭でのサポート
保護者は、家庭でも子どものサポートに努めることが重要です。以下のような方法が有効でしょう。
家庭でできるサポート
- 子どもの頑張りを認め、褒めること
- 学校生活への復帰を急がせず、子どものペースを尊重すること
- 家族で一緒に過ごす時間を大切にし、子どもの安心感を高めること
子どもの自尊心を支え、自己効力感を高めることが、学校生活への復帰の鍵となります。ただし、保護者自身も不安やストレスを抱えている場合があります。必要に応じて、周囲のサポートを求めることも大切です。
まとめ
不登校の子どもが「部活は行く」と言う場合、それを学校復帰へのきっかけとして活用することが大切です。
子どもの状況は一人一人異なるため、画一的なアプローチではなく、個別のニーズに寄り添ったサポートが求められます。
保護者と学校、そして専門家が連携し、子どもの気持ちを尊重しながら、ゆっくりと学校生活への復帰を目指していきましょう。
子どもの「部活は行く」という意思を大切にしつつ、その背景にある思いにも耳を傾けることが、不登校の子どもへの理解と支援につながるのです。
引用参考文献
更新情報
24/04/24 新規記事掲載
25/10/13 最新情報を追加