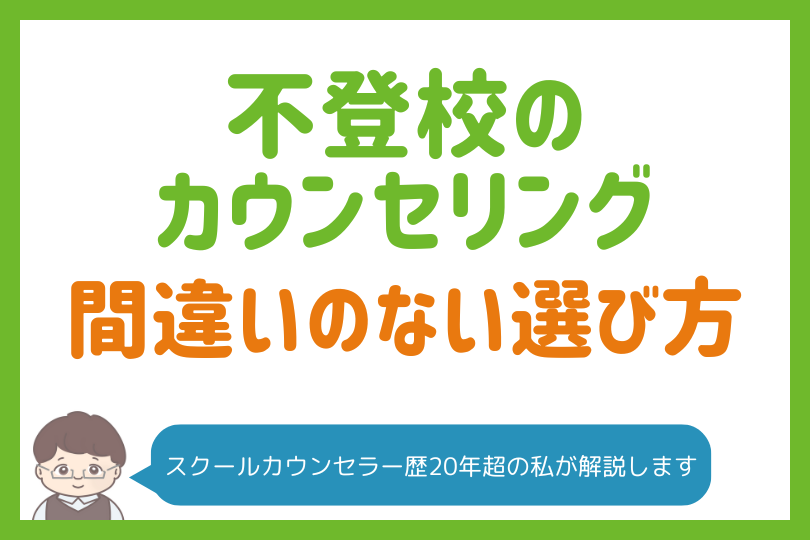- カウンセリングに対するよくある誤解と本当の役割
- お子様の状況に合わせた3つのアプローチの選び方
- なぜ「親の関わり方を変える」ことが有効なのか
- 信頼できるカウンセリングを見つけるための具体的なポイント
子どもが学校に行き渋るのを見ると、
「出口の見えないトンネルの中にいるようだ…」
「自分の育て方が悪かったのだろうか…」と、ご自身を責め、一人で抱え込んでいませんか?
先の見えない不安の中、お仕事との両立も大変ですよね。
しかし、そのお悩みは決して一人で抱え込む必要はありません。専門家との「カウンセリング」が、状況を好転させるための一助となることがあります。
この記事は、公認心理師が執筆し、医師が監修しています。
カウンセリングへのよくある誤解を解き、お子様とご自身に合ったサポートを見つけるための具体的な選択肢を、丁寧に解説します。
この記事が、みなさんの「漠然とした不安」や「どうすればよいかわからない迷い」などが軽減して、生活が少しでも楽になるお役に立てればうれしいです。

この記事を読むことで、不登校のカウンセリングについて理解できます。
執筆・編集責任:吉田克彦(合同会社ぜんと代表 公認心理師、精神保健福祉士)
- 不登校の家族支援25年以上、3000家庭以上の支援実績
- スクールカウンセラー歴20年以上。小学校、中学校、高校(全日制、定時制、通信制)全ての校種で勤務経験あり。
→詳しいプロフィールはこちら
不登校でお悩みの保護者様へ。こんなお気持ちを抱えていませんか?
お子さんが学校に行きたがらなくなったとき、ご家族が混乱するのは当然のことです。
まずは「悩んでいるのは自分だけではない」と知ると、次の一歩を踏み出たすことができます。
以下のようなお悩みは、カウンセリングを通じて整理し、軽くしていくことを目指せるものです。
「子どもへの接し方が分からない」という迷い
不登校などの問題が起きると、お子様への最適な接し方が分からなくなります。
これは特別なことではありません。
いつもは考えずに自然と出来たことでも、一度考え始めると混乱してしまうことがあります。
特に、子どもの心は日々変化しており、「これさえすれば解決する」という絶対的な正解が存在しないので、考えれば考えるほど、沼に入ってしまいます。
親として良かれと思ってかけた言葉が、かえってお子さんを追い詰めてしまう経験や、子どもの反応を気にするあまり何も言えなくなってしまうことは、決して珍しくありません。
「自分のせいでは?」という出口のない罪悪感
お子様の不登校をご家族のせいだと責める必要は全くありません。
不登校は、お子様の気質、友人関係、学校環境など、様々な要因が複雑に絡み合って起こる現象だからです。
特定の誰か一人の「せい」にできるほど、単純な問題ではありません。

それでも、ご自身を責めてしまうお気持ちは、痛いほどよく分かります。
責任感が強いご家族ほど「自分にもっと何かできたはず」と考えてしまうのです。
「この子の将来は?」という将来への漠然とした不安
一人で考え込んでいると、ネガティブな情報ばかりが目につき、最悪のシナリオを想像してしまいがちです。
例えば、以下のようなご相談にも将来への漠然とした不安が関係しています。
中学2年生の娘がいます。周りのお友達は高校受験の話をし始めているのに、うちの子は何ヶ月も学校へ行けていません。手つかずの教科書が積まれていくのを見るたび、『このままで、一体どこの高校へ行けるのだろう』『この欠席日数で、受け入れてくれる学校はあるのだろうか』と、心臓が締め付けられる思いです。私自身の不安が、娘へのプレッシャーになっていないかと、それもまた怖くなります。
高校に入学したものの、すぐに通えなくなった息子がいます。
一日中、部屋で過ごす姿を見ていると、勉強のこと以上に、その先の『就職』が心配になります。学校という社会にさえ馴染めないのに、毎日会社に通い、職場の人間関係を築くことなどできるのだろうか。このまま社会から孤立してしまうのではないか…と、親としての責任を痛感し、夜も眠りが浅くなります。
小学校高学年の孫がいます。
ひとり親家庭なので、同居する私たち祖父母としても、大切に育ててきました。
休み始めた頃は、友達から遊びの誘いもありましたが、最近ではそれもなくなりました。同年代の子どもたちが楽しそうに話している輪から、うちの子だけがポツンと取り残されていくのを見るのが、とても辛いです。このまま誰とも関わらずに大人になってしまったら、友達も、パートナーもできず、社会でたった一人になってしまうのではないでしょうか。
考えれば考えるほど、言いようのない不安に襲われます。
将来への漠然とした不安は、専門家との対話を通じて「具体的な課題」に分解すると、対処の糸口が見えてきます。
また、専門家でなくても一人で考え込まず他の人に話すことで、客観的な意見が聞けます。
客観的な視点が入ることで、その思考のループから抜け出しやすくなることが期待されます。
まずは誤解を解消!不登校カウンセリングの基礎知識
カウンセリングと聞くと、「敷居が高い」というイメージがあるかもしれません。
しかし、その実態は、心を整理し、次の一手を考えるための「専門家との作戦会議」のようなものです。
もちろん、カウンセリングが魔法の解決策というわけではなく、問題解決に向けた専門家との協働作業です。
まずはよくある3つの誤解を解き、心理的なハードルを下げていきましょう。
誤解①:「心の病気の人が行く特別な場所」
カウンセリングは、心の不調だけでなく、悩みを抱える誰もが利用できる「対話の場」です。
特に不登校の問題では、お子様本人はもちろん、どう対応すべきか悩んでいる親御様自身の相談の場として、多くの方が利用されています。

不登校の相談の場合、お子さんご本人よりもむしろご家族とカウンセリングをした方が効果的な場合が多いです。
誤解②:「ただ話を聞いてもらうだけ」
カウンセリングは、受容的な傾聴を土台としながらも、最終的には「問題解決」を一緒に考えます。
カウンセラーは、専門知識に基づいた質問や情報提供を通じて、相談者自身が気づいていなかった新たな視点や選択肢を発見するお手伝いをします。

カウンセリングの語源は、ラテン語の「consulo(助言を求める)」です。そこから英語の「counsel(助言する)」に派生し、Counselingとなりました。
つまり、ただ話を聞いてもらうだけでなく、「助言をもらってこそカウンセリング」なのです。
誤解③:「親のやり方が責められそう…」
多くのカウンセラーは、犯人探しではなく、未来に向けた「解決策」を探す味方であることを目指します。
カウンセリングの目的は、過去を裁くことではなく、現状をより良くし、未来を築くことにあります。
そのため、「お母様(お父様)もこれまで大変でしたね」と、親御さんの苦労や頑張りを認め、共感することから始まる場合がほとんどです。

実際には「以前、別のカウンセラーに『そんな状態ではダメ、もっと頑張らなきゃ』と言われて、カウンセリングが怖くなりました」というご家族が多くいらっしゃいます。
それは、カウンセリングの問題ではなく、以前のカウンセラーのスキルの問題です。
美容師でも上手な美容師と下手な美容師がいるように、カウンセラーの実力もまちまちです。
ぜひ、もっと実力のあるカウンセラーに相談をしましょう。
どんな選択肢がある?カウンセリングの主な3つのアプローチ
カウンセリングには、様々なアプローチがあります。どれが優れているというわけではなく、お子様の状態やご家庭が今何を求めているかによって、最適なアプローチは異なります。
まずは、どのような選択肢があるのかを知ることから始めましょう。
—
タイプ①:受容と共感(土台を築くアプローチ)
まずは、ありのままの気持ちを受け止めてもらい、安心できる「心の安全基地」を確保することを目指します。
アプローチの特徴
不登校の問題に直面し、心身ともに疲れ切っている親子が、エネルギーを充電するためのアプローチです。カウンセラーが評価・判断せずに深く傾聴し、どんな感情も否定されずに受け止めてもらえる体験そのものが、回復への第一歩となります。
こんな場合におすすめ
親子ともに疲れ果てて、何かを考える気力もない。まずは誰かにこの辛い気持ちをとことん聞いてほしい。
タイプ②:分析と内省(原因を探るアプローチ)
現在の生きづらさや人間関係のパターンに影響を与えている、過去の重要な体験の意味を理解し、整理することを目指します。
アプローチの特徴
「なぜこうなってしまったのか」という問いに対し、ご自身の生育歴や過去の体験を丁寧に振り返ることで、問題の根っこにあるものへの理解を深めていきます。
こんな場合におすすめ
同じような問題で繰り返しつまずいてしまう。自分の心の深い部分とじっくり向き合いたい。
タイプ③:問題解決(「今、できること」を見つけるアプローチ)
過去の原因追及にこだわりすぎず、「これからどうしたいか」「そのために何ができるか」に焦点を当て、具体的な変化を起こすことを目指します。
アプローチの特徴
このアプローチの代表格である認知行動療法(CBT)は、無理にポジティブに考えること(ポジティブシンキング)とは異なります。そうではなく、非現実的で硬直したネガティブな思考を、より現実的で柔軟な思考に置き換えることを目指す、地に足の着いた方法です。
こんな場合におすすめ
気持ちの辛さはあるが、それと同時に、現状を打開するための具体的な行動を起こしていきたい。
なぜ「問題解決型」が、不登校の状況改善に効果的なのか
どのアプローチも重要ですが、特に「見通しが立たない」「何をすべきか分からない」という不登校特有の状況において、「問題解決型アプローチ」が大きな力となることがあります。
その理由を、ぜんとカウンセリングが軸とする「認知行動療法」と「ブリーフセラピー」を例にご説明します。
理由①:親御さんの「無力感」を「自分にもできる」という感覚に変える
「見守るしかない」という状況は、親御さんの無力感を強めがちです。問題解決型アプローチでは、専門家と一緒に「今、ここからできる具体的な一歩」を探します。それは、「自分にも状況を良くするために出来ることがある」という自己効力感につながります。この感覚こそが、親御さんの心を軽くし、家庭内の重い空気を変える原動力となるのです。
—
理由②:「考え方のクセ」をほぐし、親子の悪循環を断ち切る
不登校のお子様を持つ保護者さんは、「学校に行かない=人生の終わりだ」などの、無意識の思考パターン(専門的には「自動思考」と言います)にとらわれがちです。
不登校のご家族に多い自動思考の例
- 今日休んだということは、もう二度と学校には行けないだろう。
- このまま不登校になったら、この子の人生は終わりだ。
- 高校に行けなければ、まともな大人にはなれないに違いない。
- 一日休むごとに、どんどん社会から脱落していく。
- 今、解決しないと、一生この問題を引きずることになる。
- この状態が一日でも続けば、取り返しがつかないことになる。
- このままずっと引きこもりになってしまうに違いない。

落ち着いて考えれば「極端な考えだ」と気が付きますが、問題の渦中にいると、冷静になれずこのような思い込みが頭をグルグル回ってしまいます。
認知行動療法では、こうした考え方のクセに気づき、「本当にそうだろうか?別の見方はないだろうか?」と、より柔軟で現実的な視点を探す練習をします。
保護者さんの視野が広がり、不安が和らぐと、お子様への接し方も自然に変わり、家庭内の悪循環を断ち切るきっかけになります。
—
理由③:うまくいかない原因より「うまくいったヒント」を未来に活かす
ブリーフセラピー(短期療法)は、「問題が起きている時の悪循環」と「問題が起きていない時(例外)」に注目する、ユニークなアプローチです。
例えば、「子どもが全く口をきかない」と悩んでいても、「昨日はアニメの話を5分だけしてくれた」という瞬間があったとします。ブリーフセラピーでは、その「うまくいった5分間」に何が起きていたかを詳しく探り、解決のヒントを見つけ出します。問題の原因探しよりも、未来につながる成功の種を見つけて育てることで、より早く前向きな変化を目指すのです。

「口をきいてくれない」というマイナスばかりを注目するのではなく、「話をした5分」を6分、10分、20分と増やしていく考え方です。
カウンセリングを受ける前:出口のないトンネルの中に
長女が暴れるようになり、私の精神状態も悪くなっていました。実家の母に相談すると『愛情が足りないからもっと甘えさせなさい』と言われ、その通りにしていたのですが、長女はやることもやらずに甘え放題になるばかり。『ちがう。この方向じゃないんだ』と、心の中では分かっていました。友達に相談して一緒に泣いてもらい癒されはしたものの、『この先どうしようか』という具体的な解決策は見つかりませんでした。
カウンセリングでの気づき:「親の対応次第」その意味が分かった
「一番大きかったのは、『結局、親の対応次第なんだ』と心から思えたことです。以前の私は、朝ぐずる娘に『いいから起きて!時間がないの!』と感情的に怒鳴っていました。それを、まず『そうだよね、眠いよね』と一度受け止めるように変えたんです。」
現在:怒鳴り声が消え、家庭に笑顔が
私の対応を変えただけで、あれだけ暴れていた娘が暴れなくなり、自分から宿題をやるようになりました。『あぁ、そこまでで良かったんだな』って。何より、私自身が楽になり、怒ることが減りました。専門家に相談していなければ、今も間違った方向に努力し続けていたと思います。『こういう場所って、本当に必要だな』と、心から感じています。
後悔しない!カウンセリング選びの3つのチェックポイント
実際にどうやって相談先を選べば良いのでしょうか。後悔しないための3つのポイントをご紹介します。
カウンセリング選びの3つのポイント
- アプローチと目的が合っているか: 今のご自身の気持ち(ただ聞いてほしいのか、行動したいのか)に合ったアプローチを選びましょう。
- 不登校支援の専門性と実績: カウンセラーの資格(公認心理師など)や、不登校に関する支援実績を確認しましょう。医師が監修しているかどうかも、信頼性の大きな指標です。
- カウンセラーとの相性: 理屈だけでなく、「この人になら安心して話せそう」という直感も大切です。初回相談などを活用して、雰囲気を確認することをおすすめします。
まとめ:一人で戦うのをやめて、専門家という「仲間」を頼りませんか?
ここまで、不登校に悩む親御さんのためのカウンセリングについて、様々な角度から解説してきました。
- カウンセリングは、悩みを整理し、解決策を探すための「専門家との作戦会議」です。
- アプローチには種類があり、ご家庭の状況や希望によって最適なものは異なります。
- 具体的な一歩を踏み出したい時、「問題解決型アプローチ」が大きな力になることがあります。
ここまで読んでくださった方は、きっと「この効果的なアプローチを、うちの子の場合はどう活かせるのだろう?」と感じていらっしゃるかもしれません。
ぜんとカウンセリングでは、「問題解決型アプローチ」を専門とするカウンセラー(全員が公認心理師)へ、ご自宅からオンラインで気軽に相談できます。
私たちは、不登校の状況を前に進めたいと願う親御さんの、具体的な「次の一手」を一緒に考えるパートナーです。
もちろん、カウンセリングの効果には個人差があり、回復のペースはお子様によって様々です。
焦らず、まずはお話を聞かせていただくことから始めさせてください。
—