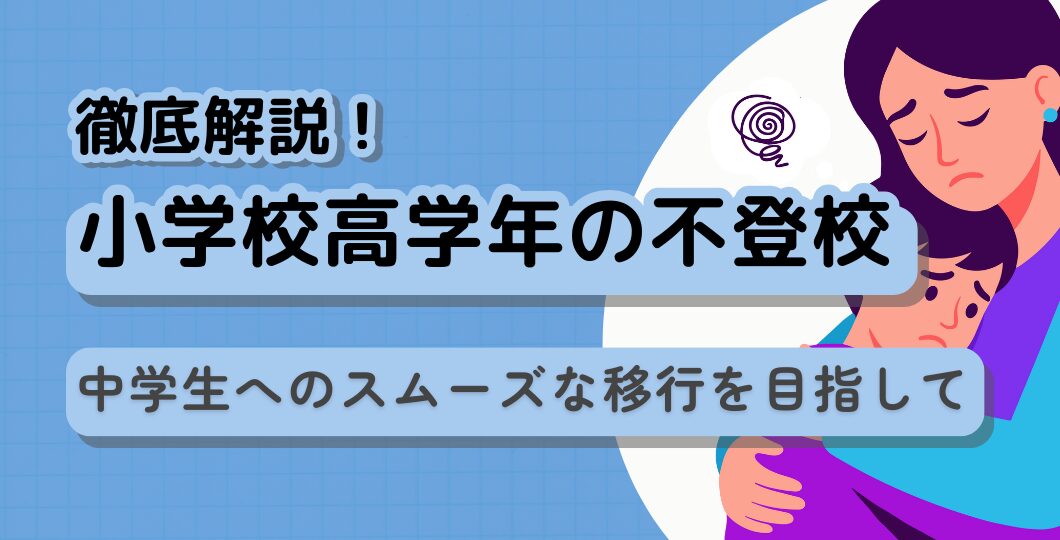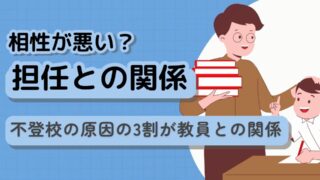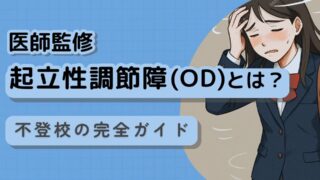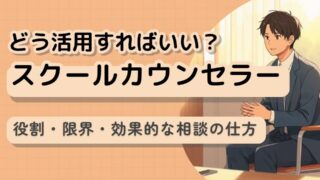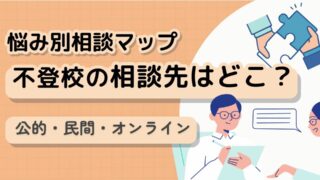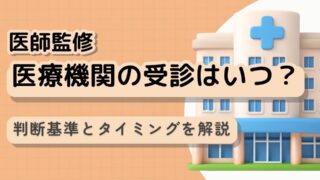小学校高学年になると、子どもたちは心も体も大きく変化し、思春期の入り口に立ちます。 この時期は、学業のプレッシャー、複雑化する友人関係、家庭環境の変化など、多くのストレス要因にさらされます。
「急に学校に行きたくないと言い出した」 「朝になるとお腹が痛いと訴える」 「理由を聞いても『わからない』としか言わない」
高学年のお子さんが不登校になると、保護者の方は「なぜ?」「どうすれば?」と戸惑うことが多いでしょう。
この記事では、25年以上にわたり不登校の家族支援に携わってきた公認心理師が、小学校高学年の不登校について、原因から具体的な対応、中学進学への準備まで徹底解説します。
この記事でお伝えしたいこと
小学校高学年の不登校とは
高学年(4〜6年生)の不登校の現状
小学校高学年は、低学年と比べて不登校の発生率が高くなる時期です。

データからもわかるように、学年が上がるにつれて不登校の児童数は増加傾向にあります。特に5年生・6年生は、中学生の不登校へとつながりやすい重要な時期です。
なぜ高学年は不登校になりやすいのか
高学年が不登校になりやすい背景には、この時期特有の発達的な変化があります。
10〜12歳頃は「思春期の入り口」と呼ばれ、ホルモンバランスの変化により心身が大きく揺れ動く時期です。
自分と他者を比較するようになり、「自分はダメだ」と感じやすくなります。また、抽象的な思考ができるようになることで、将来への漠然とした不安を抱えることも増えます。
こうした発達的な変化に加え、学習内容の難化、人間関係の複雑化、親からの自立心の芽生えなど、さまざまな要因が重なり合うことで、不登校につながりやすくなるのです。
小学校高学年の不登校の原因
高学年の不登校は、一つの原因だけでなく、複数の要因が絡み合って起こることがほとんどです。ここでは、主な原因を4つの側面から解説します。
学業面の要因
学習内容の難化とつまずき
高学年になると、算数では分数・小数の計算、割合、図形など抽象的な内容が増えます。
国語でも長文読解や作文の難易度が上がります。
低学年のうちは何とかついていけた子どもも、高学年で急につまずくことがあります。
「わからない」が積み重なると、授業を受けること自体が苦痛になり、学校に行く意欲を失ってしまいます。
中学受験のプレッシャー
中学受験を予定しているお子さんの場合、塾の宿題や模試の結果に追われる日々が続きます。
「合格しなければ」というプレッシャーは、大人が想像する以上に子どもの心を圧迫します。
学校の授業以外による遅くまで塾に通っていると疲れ切ってしまう子もいます。
また、塾で先取り学習をしている場合、学校の授業内容がつまらなく感じてしまいます。
わかりきった話を毎日5〜6時間聞き続けるのは、大人でもつらいこと。
子どもにとっては苦痛でしかありません。
成績への過度なこだわり
高学年になると、テストの点数や通知表の評価を気にする子どもが増えます。
完璧主義の傾向がある子どもは、少しの失敗でも「自分はダメだ」と強く落ち込みます。
「100点じゃないと意味がない」「1位じゃなければ価値がない」といった考え方は、不登校のきっかけになる場合があります。
人間関係の要因
友人関係の複雑化
高学年になると、友人関係は低学年の頃より複雑になります。
グループができ、その中での立ち位置や力関係を意識するようになります。
「仲良しグループに入れてもらえない」「昨日まで仲良くしていた子に急に無視された」といった出来事は、大人から見れば些細なことでも、子どもにとっては大きなストレスです。
いじめ・仲間外れ
いじめは、不登校の大きな原因の一つです。
高学年のいじめは、暴力よりも「無視」「陰口」「SNSでの悪口」など、周囲から見えにくい形で行われることが多くなります。
子どもは「親に心配をかけたくない」「言っても解決しない」「親にいじめられるというのは恥ずかしい」などと考え、いじめを受けていることを自分から話さない場合がほとんどです。
SNSトラブル
スマートフォンを持つ子どもが増え、LINEグループでの仲間外れ、悪口の拡散、個人情報の流出といったSNSトラブルも増えています。
SNS上でのトラブルは24時間続くため、学校にいる時間だけでなく、家にいても心が休まらない状態になります。
教師との関係
担任の先生との相性が合わない、厳しく叱られた経験がトラウマになっている、といったケースもあります。
特に、大勢の前で叱られた経験は、子どもの心に深く残ります。
「また怒られるかもしれない」という恐怖から、教室に入れなくなることもあります。
心身の要因
思春期特有の心身の変化
高学年は第二次性徴が始まる時期です。
体の変化に戸惑ったり、気分の浮き沈みが激しくなったりすることがあります。
自分の体や心の変化をうまく受け入れられず、「自分だけがおかしいのでは」と不安になる子どももいます。
起立性調節障害など体の不調
朝起きられない、立ちくらみがする、頭痛や腹痛が続く…こうした症状がある場合、起立性調節障害(OD)の可能性があります。
起立性調節障害は自律神経の機能不全によって起こる病気で、思春期に多く見られます。本人は学校に行きたい気持ちがあっても、体が言うことを聞かない状態です。「怠けている」と誤解されやすいため、正しい理解と対応が必要です。
発達特性の顕在化
ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)などの発達特性は、高学年になって初めて明らかになることがあります。
低学年のうちは周囲に合わせて何とか過ごせていた子どもも、人間関係や学習内容が複雑になる高学年で、困難さが目立つようになることがあります。
家庭環境の要因
家庭内の変化(転居・離婚・きょうだいの誕生など)
引っ越しによる転校、両親の離婚、きょうだいの誕生、祖父母の介護や死別など、家庭環境の変化は子どもに大きな影響を与えます。
子どもは家庭の変化を敏感に感じ取りますが、「親に心配をかけたくない」「自分がしっかりしなければ」と無理をする子もいます。
その結果、ストレスが限界に達し、学校に行けなくなる場合があります。
親の期待によるプレッシャー
「いい学校に行ってほしい」「将来困らないように」という親の願いは自然なものです。
しかし、その期待が子どもにとって過度なプレッシャーになることがあります。
「お母さんをがっかりさせたくない」「お父さんの期待に応えなければ」という思いが強すぎると、子どもは疲弊してしまいます。
不登校になったときに保護者がまずやるべきこと
お子さんが「学校に行きたくない」と言い始めたとき、保護者の方は戸惑い、焦りを感じることでしょう。しかし、この時期の対応が、その後の回復に大きく影響します。
子どもの安心・安全を最優先にする
不登校の初期に最も大切なのは、子どもが「安心・安全」だと感じられる環境を作ることです。
学校に行けないと、子どもは「自分はダメだ」「親に申し訳ない」と自分を責めます。
まずは、その苦しさを受け止め、「あなたは大切な存在だ」と伝えてください。
「学校に行かなくても大丈夫」と伝える
「学校に行かなくても、あなたのことが大好きだよ」 「今は休んでいいんだよ」
こうした言葉は、子どもの心を軽くします。
「学校に行くこと」よりも「子どもの心と体の健康」を優先する姿勢を見せれば、子どもは安心します。
原因を無理に聞き出そうとしない
「なぜ学校に行きたくないの?」「何かあったの?」と繰り返し聞くのは避けましょう。
子ども自身も理由がわからない場合が多いです。
もし、理由があっても言葉にできないことがあります。
問い詰められると、子どもは追い詰められた気持ちになり、かえって心を閉ざします。
家庭を安心できる居場所にする
学校に行けなくなった子どもにとって、家庭が唯一の居場所になります。
家の中では、学校のことを話題にしすぎず、子どもがリラックスできる雰囲気を作りましょう。
一緒にテレビを見たり、ゲームをしたり、何気ない時間を過ごすことが、子どもの心の回復につながります。
保護者がやってはいけないNG対応
良かれと思ってした対応が、逆効果になることがあります。避けたい対応を知っておきましょう。
無理に登校させようとする
「とりあえず行ってみよう」「行けば何とかなる」と無理に登校させることは、子どもをさらに追い詰めます。
一時的に登校できても、根本的な問題が解決しなければ、再び行けなくなることがほとんどです。
無理な登校刺激は、子どもの心に深い傷を残すことがあります。
原因を問い詰める
「何があったの?」「誰かに何かされたの?」と繰り返し聞くことは、子どもにとって尋問のように感じられます。
子ども自身も理由がはっきりわからないことが多く、「答えられない自分はダメだ」とさらに自分を責めてしまいます。
他の子どもと比較する
「〇〇ちゃんは毎日学校に行っているのに」「お兄ちゃんは大丈夫だったのに」といった比較は、子どもの自己肯定感を大きく傷つけます。
他の子どもと比較されると、「自分はダメだ」という思いが強まります。
その結果、自己肯定感が下がり回復が遅れる原因になります。
「怠けている」と決めつける
「本当は行けるのに甘えているだけ」「怠けているだけでしょ」という言葉は、子どもの心を深く傷つけます。
不登校の子どもは、「行きたいのに行けない」という苦しみを抱えています。
怠けではなく、心や体がSOSを出している状態です。
先回りして解決しようとする
学校で何かトラブルがあったとしても「先生に言ってあげる」「相手の親に話をつける」と、子どもの了解を得ずに動くことは避けましょう。
親が先回りして解決しようとすると、子どもは「自分の気持ちを無視された」と感じたり、「親にいうと大変なことになる」と黙ってしまいます。
そのため状況がさらに悪化することがあります。
まずは子どもの話をよく聞き、どうしたいかを一緒に考えましょう。
学校との連携の進め方
不登校が続く場合、学校との連携は欠かせません。
ただし、子どもの状態を最優先に考えながら進めることが大切です。
担任への連絡と情報共有
まずは担任の先生に現状を伝え、情報を共有しましょう。
連絡する際は、「子どもの様子」「家庭での対応」「学校にお願いしたいこと」を整理しておくとスムーズです。電話が難しければ、連絡帳やメールでも構いません。
スクールカウンセラーの活用
学校に配置されているスクールカウンセラー(SC)は、不登校の相談に対応できる専門家です。
子ども本人が相談することもできますし、保護者だけで相談することも可能です。担任には話しにくいことも、スクールカウンセラーになら話せることがあります。
出席扱いになる条件の確認
学校に行けなくても、一定の条件を満たせば「出席扱い」になる場合があります。
出席扱いの条件は学校や自治体によって異なりますので、担任や教頭先生に確認しておきましょう。教育支援センター(適応指導教室)への通所や、ICTを活用した学習なども出席扱いの対象になることがあります。

コロナ禍以降、授業をオンラインで受講できる学校も増えました。担任の先生に確認してみましょう。
学校復帰を焦らない姿勢の共有
学校側と「今は無理に登校を促さない」という方針を共有しておくことが大切です。
先生によっては「早く戻れるように」と働きかけがありますが、子どもの負担になることもあります。
「今は休養が必要な時期です」と伝え、理解を求めましょう。
専門家への相談先と選び方
不登校の対応は、保護者だけで抱え込む必要はありません。
専門家の力を借りて、新しい視点や具体的なアドバイスを得ましょう。
学校内の相談先(担任・SC・SSW)
まずは学校内の相談先を活用しましょう。
担任の先生、スクールカウンセラー(SC)、スクールソーシャルワーカー(SSW)は、学校の状況を把握しているため、具体的な対応を一緒に考えてくれます。SSWは、福祉的な支援が必要な場合に力になってくれます。
公的な相談機関(教育支援センターなど)
教育支援センター(適応指導教室)は、不登校の子どもが学校以外で過ごせる場所です。学習支援や体験活動を通して、社会性を育む機会を提供しています。
そのほか、教育委員会の相談窓口、児童相談所、子ども家庭支援センターなども相談先として活用できます。
医療機関を受診する目安
以下のような場合は、小児科や児童精神科の受診を検討しましょう。
- 朝起きられない、頭痛や腹痛が続くなど、体の症状がある
- 「死にたい」「消えてしまいたい」といった言葉がある
- 食欲がない、眠れないなどの状態が2週間以上続く
- 日常生活に大きな支障が出ている
体の症状がある場合は、まずかかりつけの小児科を受診し、必要に応じて専門医を紹介してもらいましょう。
民間の支援機関・カウンセリング
民間のカウンセリングルームや不登校支援団体も選択肢の一つです。
公的な機関は予約が取りにくいことがありますが、民間の機関は比較的柔軟に対応してもらえます。費用はかかりますが、専門家に継続的に相談できるメリットがあります。
回復段階に応じた対応
不登校からの回復には、いくつかの段階があります。それぞれの段階に合った対応をすることで、子どもの回復をサポートできます。
初期(不登校直後):休息を優先する時期
不登校になった直後は、心身ともに疲弊している状態です。この時期は、とにかく休息を優先しましょう。
勉強や生活リズムの安定は後回しにして、子どもが安心して過ごせる環境を整えましょう。可能であれば「何もしなくていい」「ゆっくり休んでいい」と伝えてください。
中期(安定期):エネルギーを蓄える時期
十分に休息が取れると、子どもは少しずつ落ち着きを取り戻します。この時期は、好きなことをして過ごす時間を大切にしましょう。
ゲーム、動画、漫画など、大人から見ると「遊んでばかり」に見えるかもしれません。しかし、これは心のエネルギーを蓄えている大切な時間です。焦らず見守りましょう。
後期(回復期):少しずつ活動を広げる時期
エネルギーが蓄えられてくると、多くの子どもは自分から「何かしたい」と言い始めます。この時期は、子どもの「やりたい」を大切にしましょう。
外出、習い事、フリースクールへの見学など、本人の興味に合わせて少しずつ活動の幅を広げていきます。ただし、無理は禁物です。一歩進んで二歩下がることもありますが、それも回復の過程です。
学習の遅れへの対応
学習の遅れは、子ども以上に保護者の方が気になるでしょう。
ただし、学習を再開するタイミングは慎重に見極める必要があります。
学習より心の安定が先
不登校の初期や、心がまだ不安定な時期に勉強を促すことは逆効果です。
「勉強しなさい」というプレッシャーは、子どもの心をさらに追い詰めます。
まずは心の安定を最優先にし、子どもが「勉強してみようかな」と自分から思えるまで待ちましょう。
本人のペースに合わせた学習再開
子どもが勉強に興味を示し始めたら、本人のペースに合わせて少しずつ再開しましょう。
「毎日1時間」などの目標を押し付けるのではなく、「今日は何をやってみたい?」と本人に選ばせることが大切です。10分でも5分でも、できたことを認めてあげてください。
家庭学習の進め方
家庭で学習を進める場合は、まず「わかるところ」から始めましょう。
学年を戻って、確実にできる内容から取り組むことで、「自分にもできる」という自信を取り戻すことができます。間違いを責めず、取り組んだこと自体を褒めましょう。
オンライン教材・個別指導の活用
自宅で学習を進める方法として、オンライン教材やオンライン個別指導があります。
オンライン教材は、自分のペースで学習を進められるメリットがあります。動画で解説を見られるものや、ゲーム感覚で取り組めるものなど、さまざまな種類があります。お子さんに合った教材を選びましょう。
高学年の自己肯定感を育てる関わり方
不登校の子どもの多くは、自己肯定感が低くなっています。
「自分はダメだ」「価値がない」という思いを抱えている子どもに、どう関わればよいでしょうか。
結果より過程を認める声かけ
テストの点数や成績ではなく、「努力したこと」「取り組んだこと」を認める声かけを心がけましょう。
「100点すごいね」ではなく、「毎日コツコツ頑張っていたね」と伝えることで、結果に関わらず「自分は認められている」と感じることができます。
小さな成功体験を積み重ねる
大きな目標ではなく、小さな目標を設定し、達成感を味わう機会を作りましょう。
料理を手伝う、ペットの世話をする、買い物に行くなど、日常の中でできることを任せてください。
「ありがとう」「助かったよ」という言葉掛けも忘れずに。子どもの自信につながります。
得意なこと・好きなことを伸ばす
絵を描く、ゲーム、音楽、スポーツなど、子どもの趣味や特技を応援しましょう。
「勉強以外のことばかり」と思うかもしれません。
好きなことに打ち込む経験は、子どもの自己肯定感を高めます。
中学進学を見据えた準備
小学校高学年の不登校で気になるのが、中学進学のことでしょう。
進路の選択肢を知り、余裕を持って準備を進めましょう。

経済的な理由や地域的に公立中学校以外考えられない場合もあります。
その場合は、特に学校との連携を密にしましょう
進路の選択肢を知る(公立・私立・フリースクールなど)
中学校の進路には、さまざまな選択肢があります。
地元の公立中学校だけでなく、私立中学校、中高一貫校、不登校経験者を受け入れている学校、フリースクール、教育支援センターへの通所など、お子さんに合った環境を検討しましょう。
中学校への引き継ぎ
中学校へ進学する際は、小学校から中学校へ情報が引き継がれます。
引き継ぎの内容について、事前に小学校の先生と相談しておくと安心です。「共有してほしいこと/ほしくないこと」があれば、遠慮なく伝えましょう。
本人の意思を尊重した進路選択
進路を決める際は、必ず本人の意思を尊重しましょう。
保護者の方が「この学校がいい」と思っても、本人が納得していなければ、入学後に再び不登校になる可能性があります。学校見学や体験入学を活用し、本人が「ここなら行けそう」と思える場所を一緒に探しましょう。
保護者自身の心のケア
子どもが不登校になると、保護者の方も大きなストレスを抱えます。
子どもを支えるためにも、保護者自身の心のケアが大切です。
自分を責めすぎない
「私の育て方が悪かったのでは」「もっと早く気づいていれば」と自分を責める保護者の方は少なくありません。
しかし、不登校は保護者のせいではありません。
さまざまな要因が複雑に絡み合って起こるものです。
自分を責め続けるのは、心身の健康を損なうだけでなく、子どもにも不安が伝わってしまいます。
相談できる人・場所を持つ
一人で抱え込まず、相談できる人や場所を持ちましょう。
配偶者、家族、友人、職場の同僚など、話を聞いてくれる人がいると、気持ちが楽になります。
身近に相談できる人がいない場合は、専門家やカウンセラーに相談することも選択肢です。
保護者同士のつながり
同じ経験をしている保護者同士のつながりは、大きな支えになります。
「親の会」や「保護者の集まり」など、不登校の子どもを持つ保護者が集まる場に参加してみるのもよいでしょう。「自分だけじゃない」と感じられることで、気持ちが軽くなることがあります。
よくある質問
Qいつになったら学校に行けるようになりますか?
回復にかかる時間は、子どもによって異なります。数週間で回復する子どももいれば、数年かかる子どももいます。
大切なのは、「いつ行けるようになるか」よりも、「今、子どもが安心して過ごせているか」に目を向けることです。焦らず、子どものペースを尊重しましょう。
Q勉強の遅れは取り戻せますか?
勉強の遅れは、取り戻すことができます。ただし、心が安定してからです。
心が不安定な状態で勉強を強いても、効果は上がりません。まずは休息を十分に取り、エネルギーが回復してから、本人のペースで学習を再開しましょう。小学校の学習内容であれば、中学・高校になってからでも十分に取り戻せます。
Q中学進学に影響しますか?内申点はどうなりますか?
不登校の子どもにかかりきりになると、きょうだいが寂しい思いをすることがあります。
きょうだいにも個別に関わる時間を作り、「あなたのことも大切に思っている」と伝えましょう。また、きょうだいにも状況を年齢に合わせて説明し、「お兄ちゃん(お姉ちゃん/弟/妹)は今、心が疲れて休んでいるんだよ」と理解を求めることも大切です。
Q本人は「行きたいけど行けない」と言います。どうすればいいですか?
「行きたいけど行けない」という言葉は、子どもの本心です。怠けているわけではなく、心や体が「行けない」状態なのです。
「行きたい気持ちがあるんだね」「つらいね」と気持ちを受け止め、今は無理をしないように伝えましょう。本人が「行きたい」という気持ちを持っていることは、回復に向けた大きな力になります。
まとめ:高学年の不登校は「次のステップへの準備期間」
小学校高学年の不登校は、決して珍しいことではありません。この時期特有の発達的変化や環境の変化により、誰にでも起こりうることです。
不登校の期間は、子どもが心と体を休め、自分自身と向き合う大切な時間です。「学校に行けないこと」をマイナスに捉えるのではなく、「次のステップへの準備期間」と考えてみてください。
保護者の方にできることは、子どもの安心・安全を守り、焦らず見守ることです。一人で抱え込まず、専門家や周囲の力を借りながら、お子さんのペースに合わせたサポートを続けていきましょう。
- 高学年の不登校は、学業・人間関係・心身・家庭環境など複数の要因が絡み合って起こる
- 初期対応では「安心・安全」を最優先に、無理に登校させない
- 学校との連携、専門家への相談を活用する
- 学習の遅れは心が安定してから対応する
- 中学進学に向けて、本人の意思を尊重した進路選択を
- 保護者自身の心のケアも忘れずに