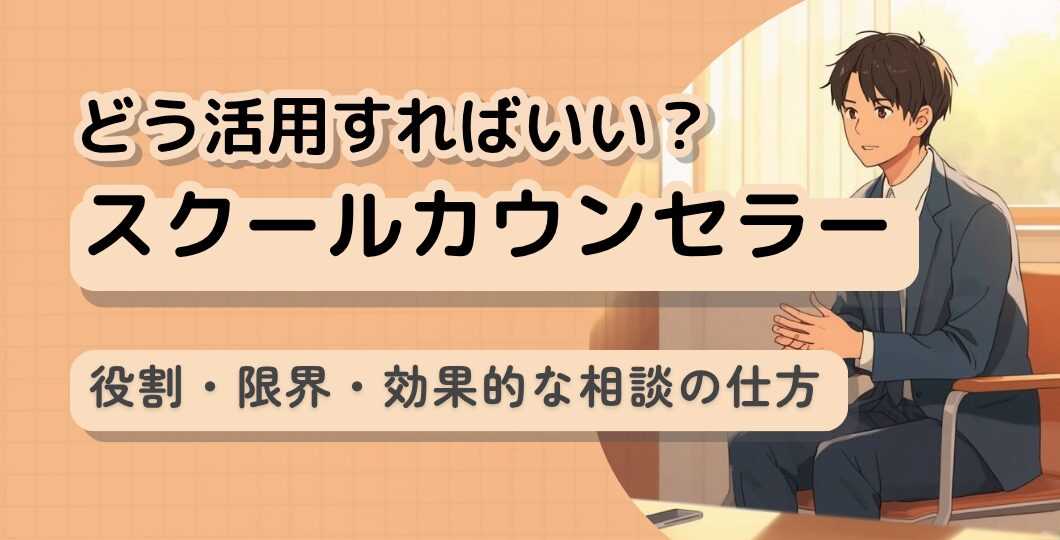「もしかして、うちの子、学校で何かあったのかしら…」 子どものちょっとした変化に気づいた時、「誰かに相談したい」そう思うことはありませんか?
学校には「スクールカウンセラー」という心の専門家がいます。
でも、普段あまり接点がないと、「どんな時に相談していいの?」「話したことが学校に知られたら…」と、不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、スクールカウンセラーの役割から、具体的な相談内容、予約方法、そして気になる守秘義務まで、保護者の方が知りたい情報を網羅的に解説します。
子どもの心の健康は、保護者の方の不安解消から始まります。
スクールカウンセラーを上手に活用して、お子さんとご家族が安心して学校生活を送るための第一歩を踏み出しましょう。

私は20年以上前からスクールカウンセラーとして活動してきました。
また、小学生、中学生の子どもを持つ保護者の立場として、スクールカウンセラーに対する疑問や相談することの不安なども理解しています。
執筆・編集責任:吉田克彦(合同会社ぜんと代表 公認心理師、精神保健福祉士)
- 不登校の家族支援25年以上、3000家庭以上の支援実績
- スクールカウンセラー歴20年以上。小学校、中学校、高校(全日制、定時制、通信制)全ての校種で勤務経験あり。
→詳しいプロフィールはこちら
スクールカウンセラーへの相談、こんな悩みはありませんか?
「相談しても意味がない」と感じている方へ
「学校の中だから相談しにくい…」
「どうせ役に立つアドバイスなんてもらえない…」
保護者の多くはそう感じて、スクールカウンセラーへの相談をためらいます。
でも使い方次第で価値は変わります。
▶ スクールカウンセラーが意味ない5つの理由と上手な活用法
「仕事が忙しくて相談に行けない」という方へ
学校にいるスクールカウンセラーは平日の日中にしか相談ができません。
週1〜2日程度で、毎日勤務しているわけではないので、相談しにくい状況です。
でも、共働き家庭でも相談できる5つの解決策があります。
▶ 仕事を休めない…相談しにくい時の解決策5選
「相談すべきか迷っている」という方へ
相談するタイミング、相談する内容、家庭の状況、担当するスクールカウンセラーによってスクールカウンセラーへの相談が適切かどうかが変わります。
スクールカウンセラーのメリット・デメリットを客観的に理解してから判断しましょう。
▶ SCに相談するメリット・デメリット|相談前に知っておきたいこと
なぜ、学校にカウンセラーが配置されるようになったのか
スクールカウンセラーは、学校に配置された心理の専門家です。
でも、「心理の専門家」と聞くと、なんだか敷居が高く感じてしまいますよね。
まずは、スクールカウンセラーがどんな存在なのか、基本的なことからご説明します。
阪神淡路大震災をきっかけに子どもの「こころのケア」が注目された
スクールカウンセラーが導入させる、きっかけの一つは、1995年1月に発生した阪神淡路大震災です。
震災後、不安や不眠を訴える子どもたちの心のケアが課題となりました。
そこで兵庫県では震災後の子どもたちの心のケアのために、13名のカウンセラーを配置。
被災地の学校を訪問し、子どもたちこころのケアに貢献しました。
その後2001年度から全国の公立中学校への本格的な配置事業がスタートしました。
現在では、ほとんどの公立学校にスクールカウンセラーが配置されています。
主に週に1~2日程度の勤務する、臨床心理士や公認心理師などの資格を持つ専門家です。
- 1995年度(平成7年度):文部省の調査研究事業として全国154校で試験的配置開始
- 2001年度(平成13年度):全国公立中学校への本格配置補助事業スタート
- 2017年度(平成29年度):カウンセラーの国家資格「公認心理師」が誕生
2023年度(令和5年度)には、小学校の96.9%、中学校の98.8%、高等学校の95.2%にスクールカウンセラーを配置
文部科学省の報告より
スクールカウンセラーの主な役割
スクールカウンセラーは、学校現場における唯一の心理職として、さまざまな「こころのケア」に関する取り組みを行っています。
- 児童・生徒への直接的な支援
- 保護者へのカウンセリング
- 教職員へのコンサルテーション
- 心理教育・予防的な取り組み
1. 児童・生徒への直接的な支援
子どもたちの悩みを聞いたり、ストレスへの対処法を一緒に考えたりします。
カウンセリング室で1対1で話を聞くこともあれば、休み時間に声をかけて様子を見ることもあります。
2. 保護者へのカウンセリング
お子さんの不登校や問題行動で悩む保護者の相談にも応じます。
「子どもにどう接したらいいかわからない」「このままで大丈夫だろうか」といった不安を受け止め、一緒に対応を考えます。
3. 教職員へのコンサルテーション
担任の先生や他の教職員に、子どもへの接し方についてアドバイスをします。
「この子にはこういう配慮が必要です」「こんな風に声かけをしてみてください」など、専門的な視点から助言を行います。
4. 心理教育・予防的な取り組み
研修会の講師を務めたり、「スクールカウンセラーだより」を発行したりして、メンタルヘルスに関する情報を発信します。
問題が起きてからではなく、予防的な観点からも活動しています。
相談できる具体的テーマ
スクールカウンセラーには、子どもの成長や学校生活に関することなら、基本的に何でも相談できます。「こんなこと相談していいのかな?」と迷う必要はありません。
- 不登校・登校しぶり
- 学習意欲の低下
- いじめや友人関係のトラブル
- 家庭の問題
不登校・登校しぶり
最も多い相談の一つです。「朝になると体調が悪くなる」「学校に行きたくないと泣く」「教室に入れない」など、さまざまな形の不登校に対応します。学校に行けないことは、生活リズムの乱れや人間関係の悪化、学習の遅れなど、二次的な問題につながることもあるため、早めの相談が大切です。
学習意欲の低下
「宿題をやりたがらない」「テストの点数が急に下がった」「授業についていけない」といった学習面の悩みも相談できます。勉強がわからないことは、自己肯定感の低下や将来への不安につながることもあるため、心理面からのサポートが有効な場合があります。
いじめや友人関係のトラブル
「仲間はずれにされている」「SNSでの嫌がらせを受けている」「友達ができない」など、人間関係の悩みは子どもの心に大きな影響を与えます。最悪の場合、自殺などの深刻な事態につながる可能性もあるため、スクールカウンセラーは慎重に、でも迅速に対応します。
家庭の問題
「両親の不仲」「経済的な困難」「虐待の疑い」など、家庭内の問題が子どもの学校生活に影響することもあります。デリケートな内容ですが、守秘義務を守りながら適切に対応します。
発達の心配
「落ち着きがない」「こだわりが強い」「集団行動が苦手」など、発達に関する心配事も相談できます。ただし、診断はできないため、必要に応じて医療機関を紹介することもあります。
相談までのながれ―いつ・どこで・どうやって予約する?
「スクールカウンセラーに相談したい」と思っても、実際にどうすればいいのかわからないという声をよく聞きます。
ここでは、相談を決めるタイミングから、予約方法、当日の流れまで、順を追って詳しく説明します。
相談の適切なタイミング
「まだ相談するほどではないかも…」と迷っている間に、問題が大きくなってしまうことがあります。
相談のタイミングは「違和感を感じたらすぐ」がベストです。
- 登校を嫌がり始めた時
- 家庭学習で極端な変化が見られた時
- 対人トラブルの初期段階
早めの相談には多くのメリットがあります。
問題が小さいうちなら、簡単なアドバイスで改善することも多いです。
また、「何かあったらすぐ相談できる」という安心感を持てることも、保護者の精神的な支えになります。
利用できる予約方法
スクールカウンセラーへの相談予約には、主に3つの方法があります。
学校によって利用できる方法は異なりますが、多くの場合、複数の方法が用意されています。
1. 教職員を通じて申し込む
最も一般的な方法です。担任の先生、養護教諭(保健室の先生)、教頭先生などに「スクールカウンセラーに相談したい」と伝えれば、予約を取ってくれます。
2. 相談室直通の電話で申し込む
学校によっては、カウンセリング室に直通の電話が設置されています。スクールカウンセラーの勤務日に直接電話をかけて予約を取ります。
3. メールで申し込む(対応してない学校も多い)
一部の学校では、メールでの予約も受け付けています。学校のホームページや配布物で、メールアドレスが公開されているか確認してみてください。
相談当日の流れと準備物
初めての相談は誰でも緊張するものです。当日の流れを知っておくことで、少しでも不安を和らげることができます。
- これまでの経緯をまとめたメモ
- カウンセラーに聞きたいことリスト
- 子どもの作品や成績表などの資料
これらは「あれば便利」なものなので、何も準備せずに行っても問題ありません。
カウンセラーが丁寧に話を聞き出してくれます。
スクールカウンセラーが対応できないこと・注意点
スクールカウンセラーは心理の専門家ですが、万能ではありません。
制度上の制約や、専門性の違いから、対応できないこともあります。
事前に知っておくことで、過度な期待や誤解を防ぐことができます。
スクールカウンセラーにはできないこと
スクールカウンセラーとしては、学校で活動している、医師ではなく心理の専門家「だからできないこと」や「だからこそできること」があります。
医療的な診断や治療
「うちの子は発達障害でしょうか?」「ADHDの薬を処方してもらえますか?」といった医療に関することは、スクールカウンセラーの業務範囲外です。
心理検査を実施することはありますが、それをもとに診断を下すことはできません。
医療的な対応が必要と判断した場合は、適切な医療機関を紹介してもらえます。
成績や進路の保証
「カウンセリングを受ければ成績が上がりますか?」「希望の高校に入れるようになりますか?」といった学業成績や進路に関する保証はできません。
ただし、学習意欲を高めたり、進路選択の不安を和らげたりする心理的なサポートは可能です。
学校のルールを変更すること
「うちの子のために特別ルールを作ってください」「テストを受けなくても進級させてください」といった学校の規則に関する要求には応えられません。ただし、子どもの状況を学校側に伝え、配慮を求める橋渡し役は担ってくれます。
即効性のある解決策の提供
「いま不登校なので、明日から学校に行けるようにしてください」といった即効性を求められても困難です。
心理的な問題の改善には時間がかかることが多く、じっくりと取り組む必要があります。
家庭内の問題への直接介入
夫婦関係の問題や経済的な困難など、純粋に家庭内の問題には直接介入できません。
ただし、それらが子どもに与える影響については相談に乗り、必要に応じて他の支援機関を紹介してもらえます。
制度・守秘義務・情報共有のルール完全解説
スクールカウンセラーには、法律で定められた守秘義務があります。
公認心理師法では、正当な理由なく相談内容を他人に漏らしてはならないと定められており、違反した場合は資格を失うこともあります。
守秘義務で守られること
- 相談者(保護者や子ども)が話した内容
- 家族のプライベートな情報
- 相談者の心理状態や診断に関する情報
- 面談の記録や心理検査の結果
つまり、カウンセリングで話された内容は、原則として相談者の許可なく他の人に伝えることはありません。これは、相談者が安心して本音を話せる環境を作るために、とても重要なルールです。
守秘義務の例外
ただし、以下のような場合は、守秘義務よりも優先される事項があります:
- 生命の危険がある場合(自殺の具体的な計画、自傷行為、摂食障害など)
- 虐待が疑われる場合(身体的虐待、ネグレクト、性的虐待)
- 犯罪に関わる場合(暴力行為、違法薬物、重大ないじめ)
- 法令に基づく場合(裁判所命令、警察・児童相談所からの要請)
これらの場合でも、可能な限り事前に相談者に説明し、了解を得るよう努めます。「あなたの安全を守るために、この情報は共有する必要があります」といった形で、丁寧に説明してもらえるはずです。
情報共有の範囲と流れ
守秘義務を守りつつも、子どもの支援のためには学校内での適切な情報共有が必要な場合があります。どのような情報が、どのように共有されるのか、具体的に見ていきましょう。
必要最小限の情報共有
- 面談の有無(○○さんの保護者が相談に来ています)
- 見立てと今後の方針(様子を見守ってください など)
- 担任が知っておいた方が良い配慮事項(グループの組み合わせなど)
情報共有の基本的な流れ
- 相談者との面談
- 共有すべき情報の整理
- 相談者への確認(できる範囲で)
- 関係者に必要最小限の情報を伝える
- 共有後の対応をフォローアップ
重要なのは、「子どもを支援するために必要な情報」だけが共有されるという点です。たとえば、「お母さんが仕事のストレスで…」などの家庭の詳しい事情は共有されません。
情報共有の確認方法
「どこまで情報が共有されるか心配」という場合は、遠慮なくスクールカウンセラーに確認してください。守秘義務について質問することは、まったく失礼ではありません。
- この話は担任の先生に伝わりますか?
- どの範囲まで情報を共有する予定ですか?
- 共有する前に確認してもらえますか?
- 子どもには相談したことを伝えないでほしい
情報共有を最小限にしたい内容
- 家族のプライベートな問題
- 過去のトラウマ体験
- 他の保護者との人間関係
- 関係者の実名など具体的な内容
- 経済的な事情
これらの内容は、聞かれない限りは応えなくて構いません。
もし聞かれた場合でも「なぜ、その情報が必要なのですか?」などと、確認をすると説明をしてくれるはずです。
説明に納得できなかったり、そもそも説明をしてもらえない場合は応える必要はありません。
- 最初は一般的な相談から始める
- 他の相談機関も検討する(学校外のカウンセリングなど)
- 「カウンセラーから見て学校の様子はどんな状況ですか」などとたずねる
→ここでうわさ話や個人情報をぺらぺら話すカウンセラーは信用してはいけません。
スクールカウンセラーは、相談者との信頼関係を何より大切にしています。
情報共有についての不安や要望は、率直に伝えることで、より安心して相談できる環境を作ることができます。
相談しにくいと感じたら?理由別の対応法
「スクールカウンセラーに相談したいけれど、なんだか相談しにくい…」そんな気持ちを抱える保護者は少なくありません。相談をためらう理由は人それぞれですが、その理由に応じた対応方法があります。
カウンセラーに対する不安
「どんな人かわからない」「話が合うか心配」「批判されたらどうしよう」など、カウンセラーに対する不安から相談をためらうケースがあります。
カウンセラーを信用できるか不安なため相談できない気持ちは良くわかります。
でも、相談せずに時間だけが過ぎてしまうのは、お子さんとご家族の人生にプラスにはなりません。
カウンセラーに対する不安をどのようにして解決すればよいか、紹介します。
対応方法①:保護者同士や教職員から評判を聞く
他の保護者に「相談したことある?」と聞いてみたり、担任や養護教諭に「どんな先生ですか?」と雰囲気を確認してみましょう。
対応方法②:相談室だよりなど配布物でプロフィールを確認する
多くの学校ではカウンセラーからの自己紹介文や相談室便りが配布されています。経歴や専門、得意分野なども書かれていることがあります。
そもそも相談室だよりなどを発行していないスクールカウンセラーもいますが、そういうカウンセラーはおすすめしません。
対応方法③:実際に一度会ってみる
「学校に届け物があったので、少しご挨拶をしたくて」とか「相談室の場所を確認しに来ました」、「相談の予約をしたくて」という形で一度訪問してみるのも一つの方法です。

私が新しい学校に着任すると「相談室だよりを出すカウンセラーさんに初めてだったので、感激してご挨拶をしたくて」という保護者の方がけっこういらっしゃいます。
もちろん、そこから相談につながりました。
制度面での相談のしにくさ
スクールカウンセラー制度には、構造的に相談しにくい面があることも事実です。これらの制約を理解した上で、対応方法を考えましょう。
平日の昼間しか相談できない
学校の相談室は、平日の昼間だけ開室します。
したがって、フルタイムで働かれている方などには相談がしにくい状況です。
特定の日しか勤務していない
スクールカウンセラーは週1~2回の勤務が多いため、早めの予約やスケジュール調整が必要です。
対面相談が基本でオンラインに対応していない
コロナ禍の時期はオンラインカウンセリングも行っていました。
現在はほとんどの学校のスクールカウンセリングではオンラインでの面接は行っていません。
学校に来て相談をする必要があるため、どうしても人目が気になってしまうことがあります。
特に不登校の相談の場合、オンラインや家庭訪問ならお子さんも話せるけれど、学校だと来れないため話ができない場合もあります。
特にお子さんが不登校について保護者の方が相談をされる場合、「学校に行くと子どもの同級生が学校で過ごしているのを見ると胸が締め付けられる」「比較しても仕方がないとわかってはいるけれど、どうしても自分の子どもの様子と比べてしまう」といった声を聴きます。
時間帯をずらす、人目につかない出入口を使う、またはオンライン対応の民間機関の利用を検討しましょう。
「相談したくてもできない」という状況に陥ることがあります。そんな時は、無理に学校のシステムに合わせる必要はありません。他の選択肢も含めて、自分に合った相談方法を見つけることが大切です。
保護者向け相談事例集
ここでは、よくある相談内容について、「相談前→面談→結果」の流れを具体的に紹介します(個人情報保護のため、複数の事例を組み合わせて再構成しています)。
相談前の状況
小学5年生の男子。夏休み明けから登校しぶりが始まり、朝になると腹痛を訴えてトイレから出てこないが、昼過ぎには元気にゲームをする様子。母親は仕事を休んで対応するが、父親は「甘やかすな」と対立。
初回面談の内容
母親が一人で来談し、涙ながらに現状を説明。カウンセラーは共感的に話を聞き、身体症状は心理的ストレスの可能性が高いと見立て。無理な登校よりも安心感を優先し、夫婦の意見統一を提案。
フォローアップ
2回目面談では両親が来談し、父親も子どもの辛さを理解。月2回のペースで継続面談を行い、保健室登校からスタート。数か月後には週に数回登校できるように。
成功のキーポイント
- 子どものペースを尊重し焦らなかった
- 両親の対応が一致した
- スモールステップで進めた
- 担任と柔軟に連携できた
相談前の状況
中学2年生の女子。1年生の後半から成績が急降下。「どうせできない」が口癖となり、提出物を出さなくなる。保護者は焦りを感じるが、本人は無関心な様子。
初回面談の内容
母親と本人で来談。本人は最初こそ口数が少なかったが、カウンセラーの工夫により徐々に話を始め、「わからなくなってから全部が嫌になった」と本音を語る。
個別支援プラン
- 目標設定を小さく具体化(例:「今週は英語の単語を3つ覚える」)
- やったこと記録シートで「できた」を可視化
- 保護者の声かけを「結果」から「過程」重視に切り替え
3ヶ月後の変化
提出率が向上し、数学のテストで初めて平均点を超える。本人の自己肯定感も回復し、親子関係も改善。
スクールカウンセリングの効果・メリット検証
スクールカウンセリングを利用することで、いろいろな効果が得られます。ここでは、具体的なメリットと、知っておくべきデメリットについても紹介します。
スクールカウンセラーに相談するメリット
1. 心理的な安定と安心感の向上
最も大きな効果は、「一人で抱え込まなくていい」という安心感です。
否定や批判をせず、ありのままを受け止めて、子どもも保護者も心理的に安定します。
2. 学習意欲の向上
心理的な問題が改善されると、自然と学習面にも良い影響が現れます。
「勉強しなさい」と言うよりも、学習を妨げている心の問題にアプローチすることで、学習意欲が回復します。
3. 人間関係の改善
カウンセリングを通じて自己理解が進むことで、他者との関係も改善されます。
自己表現や感情コントロールの力を養うことができ、人間関係のトラブルが減少します。
①早期発見・早期対応が可能
学校に常駐している(または定期的に訪問している)カウンセラーだからこそ、日々の小さな変化に気づきやすく、早期に対応が可能です。
いじめ対応の例:表情の変化に気づいた担任がカウンセラーに相談。面談の結果、SNSでの嫌がらせが発覚。早期に対応できたことで不登校を未然に防ぐことができました。
②継続的な支援が受けられる
卒業まで継続して支援を受けることができ、月に1〜2回の定期面談で成長を見守ってもらえる安心感があります。
定期面談の効果:不登校だった生徒が、中1から中3まで面談を継続。少しずつ登校日数が増え、高校は全日制に進学。「3年間見守ってもらえたから頑張れた」と本人が語っています。
③学校全体での支援体制強化
スクールカウンセラーを軸とした、チームでの支援体制が構築され、教職員間の連携が強化されます。
全校支援体制の例:発達障害のある生徒に対し、カウンセラーがコーディネーターとして支援会議を開催。各教科担当と配慮事項を共有し、統一対応で学校生活が改善。
スクールカウンセラーに相談するデメリットと注意点
スクールカウンセリングは万能ではありません。制度上の制限もあるため、過度な期待は禁物です。
- 面談回数の制限:月1〜2回が限度、頻繁には相談できない
- 時間的制約:1回45〜50分、複雑な話は時間が足りないことも
- 予約困難:人気カウンセラーは予約が取りづらい
- 長期休暇中の対応困難:勤務日が減り、緊急対応不可な場合も
- 引き継ぎの課題:カウンセラー交代時に履歴がうまく引き継がれないことも
これらのデメリットに備えるためには、自宅でできる対応を工夫したり、外部機関の併用を検討したりすることも大切です。
スクールカウンセラーを知って、上手に活用しよう
ここまで、スクールカウンセラーの基本から、具体的な活用方法まで詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめておきます。
スクールカウンセラーは、こんな時に頼れる存在です
- 子どもの不登校や登校しぶりに悩んでいる時
- 学習意欲の低下や成績不振が心配な時
- いじめや友人関係のトラブルがある時
- 発達の特性について相談したい時
- 子育てに行き詰まりを感じた時
相談のハードルを下げるポイント
- 「ちょっと気になる」程度で相談してOK
- 初回は「顔合わせ」と考える
- 合わなければ無理に続けなくていい
- 守秘義務があるので安心して話せる
効果的に活用するコツ
- 定期的に相談することで効果が高まる
- 学校との連携を意識する
- 家庭でのフォローアップを大切に
- 過度な期待はせず、長期的な視点で
こんな場合は他の選択肢も検討を
- 平日の相談が難しい
- もっと頻繁に相談したい
- 学校に知られたくない内容がある
- オンラインで相談したい
- より専門的な支援が必要
スクールカウンセラーは、子どもたちの健やかな成長を支える重要な存在です。しかし、万能ではありません。制度の限界を理解した上で、上手に活用することが大切です。
もし、「学校のカウンセラーには相談しにくい」「もっと気軽に相談したい」と感じている方は、オンラインカウンセリングという選択肢もあります。自宅から相談できる、時間の融通が利く、学校に知られる心配がないなど、多くのメリットがあります。
私たち「ぜんとカウンセリング」では、不登校をはじめとする子育ての悩みに特化したオンラインカウンセリングを提供しています。公認心理師の資格を持つカウンセラーが、じっくりとお話を伺います。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
子育て中に悩みは尽きないと思います。
自分一人で考えても答えが出ず、家族に相談しても具体的なアドバイスがない場合もあるでしょう。
そんな時は専門家に相談してみましょう。
少しでも子育てが楽になり、お子さんが元気になるために使えるものはどんどん使いましょう。