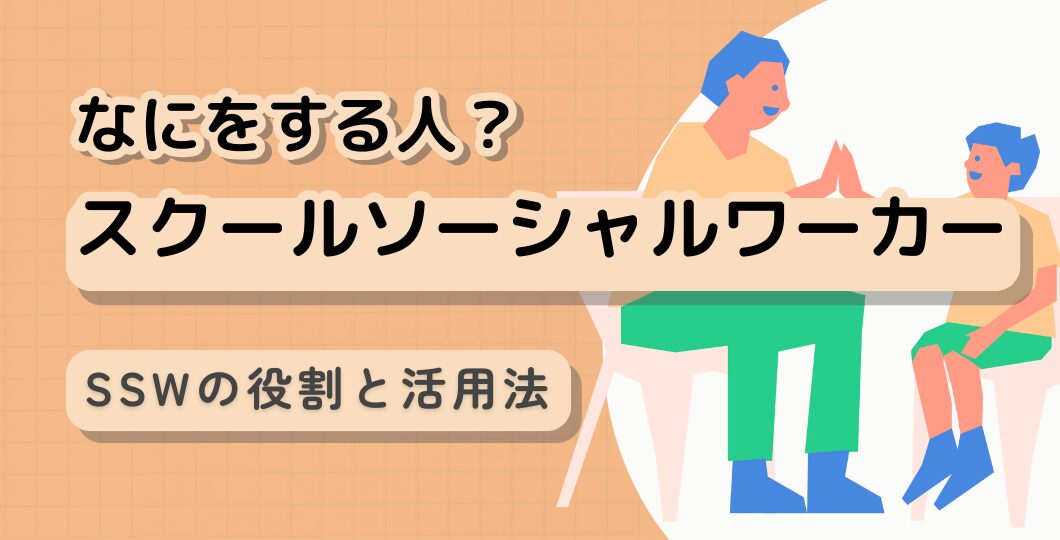「SSWって何する人?」
「スクールカウンセラー(SC)との違いは?」
「どうやって会うの?」
「家庭の経済的問題も相談できる?」
・・・などなど、
スクールソーシャルワーカー(SSW)について、疑問を持つ保護者の方は非常に多くいます。
スクールソーシャルワーカー(SSW)は、学校に配置されている福祉の専門家です。
しかし、スクールカウンセラー(SC)と比べて認知度が低く、分からない方も多いでしょう。
この記事では、公認心理師として25年以上の経験から、SSWとは何か、SCとの違い、SSWに相談すべきケース、具体的な支援内容、学校への依頼方法、活用の成功事例まで、実践的に解説します。
この記事でお伝えしたいこと
執筆・編集責任:吉田克彦(合同会社ぜんと代表 公認心理師、精神保健福祉士)
- 不登校の家族支援25年以上、3000家庭以上の支援実績
- スクールカウンセラー歴20年以上。小学校、中学校、高校(全日制、定時制、通信制)全ての校種で勤務経験あり。
→詳しいプロフィールはこちら
スクールソーシャルワーカー(SSW)は、福祉面から支援する専門家
◆用語解説:スクールソーシャルワーカー
学校に配置されている、社会福祉の専門家です。社会福祉士、精神保健福祉士などの資格を持ち、子どもや家庭が抱える福祉的な問題を解決するために、様々な支援を行います。
2008年から文部科学省の事業として始まり、現在では全国の多くの学校に配置されています。常駐ではなく、多くて週に1〜2回、少ないと数か月に1回、複数の学校を巡回する形が一般的です。
資格:
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- その他、福祉に関する資格・経験
活動内容:
- 子どもや家庭の抱える問題の把握
- 関係機関(児童相談所、福祉事務所、医療機関など)との連携
- 保護者への情報提供、助言
- 子どもの環境改善への働きかけ
SSWの特徴: 心理的な支援だけでなく、福祉的な視点から、子どもや家庭を取り巻く環境全体にアプローチします。
スクールカウンセラー(SC)との違い【比較表】
SSWとスクールカウンセラー(SC)の違いを、表で比較します。
| 項目 | スクールソーシャルワーカー(SSW) | スクールカウンセラー(SC) |
|---|---|---|
| 専門分野 | 社会福祉(環境調整) | 心理学(心理支援) |
| 主な資格 | 社会福祉士、精神保健福祉士 | 臨床心理士、公認心理師 |
| 主な支援対象 | 子ども+家庭+環境 | 子ども+保護者 |
| 支援内容 | 福祉的支援、環境調整、関係機関連携 | 心理的支援、カウンセリング |
| 相談内容 | 経済的困難、虐待、家庭の問題など | 心の悩み、対人関係、学習の悩みなど |
| 勤務回数 | 週1〜2回から数か月に1回程度 | 週1〜2回から月1回程度 |
SSWは、経済的な問題や家庭内での困難といった「福祉的な視点からの環境調整」が得意です。
一方、SCは不安やストレスといった「心理的な問題」の解決を得意とします。
SSWに相談すべき具体的なケース
不登校の背景には、メンタル面だけでなく、家庭の環境や経済的な問題が潜んでいることが少なくありません。以下のような「福祉的な支援」や「外部機関との連携」が必要なケースは、SSWに相談することが適切です。
1. 経済的困難に関する問題
子どもの学校生活に必要な費用が準備できない、生活自体が困窮しているといった問題は、SSWの最も得意とする分野です。
- 就学援助制度の利用や申請方法を知りたい
- 給食費、修学旅行費、教材費などの支払いが困難である
- 生活保護の検討や申請をしたい
- その他、必要な制服や学用品が買えない状況にある
2. 家庭内での生活環境に関する問題
家庭内での困難が子どもの生活や学習に大きな影響を与えている場合も、SSWが支援を主導します。
- ひとり親家庭で、育児と仕事の両立が困難を極めている
- 保護者が病気や障害があり、子育てに支障が出ている
- 家族の介護や世話で、子どもに手が回らない(ヤングケアラーの可能性)
- 家庭内暴力(DV)や虐待が疑われる状況にある
3. 福祉サービスと関係機関の利用・調整
利用できる福祉制度がわからない、または複雑な手続きのサポートが必要な場合、SSWは強力な窓口となります。
- 利用できる福祉サービス(児童扶養手当、放課後児童クラブなど)について知りたい
- 児童相談所や福祉事務所への相談方法が分からない、または連携が必要である
- 医療機関(児童精神科など)、学校、家庭、福祉機関の多機関連携が必要である
4. 子どもの生活環境の変更・調整
子どもの生活の基盤となる環境自体の変更が必要な場合も、SSWがサポートします。
- 転校を検討しているが、手続きや情報収集に困っている
- 住居の問題(転居など)があり、学校生活への影響が心配である
- 地域の居場所(フリースクール、適応指導教室、NPOの学習支援など)の情報を知りたい
SSWの具体的支援内容:問題解決への道筋
SSWは、相談者の話を聞くだけでなく、具体的な行動を通じて問題の解決を目指します。その支援内容は多岐にわたりますが、特に福祉的な手続きや外部連携において強みを発揮します。
1. アセスメントと情報提供
- 状況把握(アセスメント):家庭訪問や面談を通じて、子どもや家庭の抱える問題を福祉的な視点から詳細に把握します。
- 情報提供:利用可能な公的な福祉制度、手当、サービス、専門の相談先など、具体的な情報を提供します。
2. 関係機関との連携・調整
- 連携・調整:児童相談所、福祉事務所、医療機関、ハローワーク、NPOなど、問題解決に必要な全ての関係機関と連携し、支援内容や役割分担を調整します。
- ケース会議の開催:学校、家庭、関係機関が一堂に会し、支援の具体的な方針を話し合う場を設け、主導します。
3. 申請手続きの支援
- 申請サポート:生活保護、就学援助、児童扶養手当など、複雑な行政手続きや申請書類の作成を具体的にサポートします。
4. 環境の改善への働きかけ
- 学校への働きかけ:担任や管理職に対し、家庭の状況を説明し、子どもの学習や生活における具体的な配慮を促します。
- 環境調整:転校の手続きや、地域の居場所の紹介など、子どもの環境を改善するための調整を行います。
SSWの支援は、家庭全体、環境全体にアプローチする包括的な支援であり、不登校の原因が根深い場合に特に有効です。
学校への依頼方法
依頼のタイミング
適切なタイミング:
- 家庭の経済的問題で困っている時
- 福祉サービスの利用を検討している時
- 関係機関との連携が必要な時
- 家庭の問題が、子どもの不登校に影響している時
早めに相談すべき: 問題が深刻化する前に、早めに相談することをおすすめします。
依頼の方法
ステップ1:担任に相談 まず、担任に「SSWに相談したい」と伝えます。
相談例:
「お世話になっております。○○の母です。
現在、家庭の経済的な問題があり、
スクールソーシャルワーカーの方に相談したいと思っています。
どのように連絡を取れば良いでしょうか?」ステップ2:学校がSSWに連絡 担任から、SSWに連絡が行きます。
ステップ3:SSWとの面談 SSWの来校日に、面談を設定します。学校で会うことが多いですが、場合によっては家庭訪問もあります。
ステップ4:支援の開始 面談で状況を把握した後、必要な支援が開始されます。
注意点:
- SSWは常駐していないため、すぐに会えないこともあります
- 緊急の場合は、直接関係機関(児童相談所、福祉事務所など)に連絡することも検討してください

SSWがほとんど巡回していない学校もあります。また、教職員がSSWについて十分理解できていない場合もあります。その時は、一度、スクールカウンセラーに相談するのもアリです。
専門機関や制度に関する情報であれば、スクールカウンセラーが教えてくれることもありますし、SSWと連携してもらえることもあります。
SSW活用の成功事例:福祉的支援が不登校を改善したケース
スクールソーシャルワーカー(SSW)は、福祉の専門的な視点とネットワークを活かし、不登校の根底にある家庭環境や経済的な問題にアプローチすることで、状況の改善に貢献します。ご提供いただいた文部科学省の事例集を参考に、SSWの活用が成功した3つの事例を紹介します。
友人トラブルをきっかけに不登校になった中学生のケースです。背景には、母親不在、父親・祖父母との関係の困難さ、自室がないこと、祖父母の介護負担など、複雑な家庭環境がありました。
SSWは、本人専用の居場所(自室)確保を支援し、祖父母の介護認定取得とデイサービス利用につなぎました。さらに、市委託の学習支援事業と連携し週1回の学習機会を提供。保健センターとも連携し、精神医療受診を勧めました。
登校再開には至っていませんが、家庭環境が改善され、学習支援につながり、家族との信頼関係も構築できました。
発達面や精神面に課題のある生徒のケースです。家庭は発達支援センターの支援を受けていましたが、さらに小児医療機関ともつながりたいと学校に相談しました。
SSWは保護者と面談を行い、ケース会議を開催。学校、SSW、スクールカウンセラー(SC)がそれぞれの役割を明確にしました。学校は生徒との信頼関係づくり、SCは保護者への継続面談と助言、SSWは保護者面談と医療機関への橋渡しを担当しました。
その結果、生徒の登校リズムや対人関係に良好な変化が見られ、保護者も安定。SSWが医療機関につなぎ、さらに市町村福祉部局とも連携することで、子育ての相談先が広がり、家庭全体の困り感が軽減されました。
小学校から不登校が続く中学1年生の男子生徒のケースです。
家の中は不衛生で物が散乱し、母親は精神疾患が疑われるものの未治療。父親は多忙で、家庭訪問しても保護者は出てこない状況でした。
SSWは校内ケース会議を提案し、情報を整理。父親と面談を重ね、母親の受診に向けて医療機関との連携に同意を得ました。SSWが医療機関と情報共有を行い、母親の入院治療が実現。入院当日は祖父母がサポートに入りました。
母親の入院後、市役所障害福祉課や子ども家庭センターともつながり、家庭環境が改善。生徒は校内教育支援センターに毎日登校できるようになり、多忙だった父親も子どもとの時間を優先できるようになりました。家庭全体の環境を整えることで、子どもの生活が安定しました。
ここで紹介した事例は、文部科学省の資料(令和5年度スクールソーシャルワーカー活用事業実践活動事例集)の事例を元に作成しています。
よくある質問(FAQ)
QSSWは全ての学校にいますか?
多くの学校に配置されていますが、小規模校では配置されていないこともあります。担任に確認してください。配置されていない場合は、教育委員会に問い合わせましょう。
QSSWに相談すると、学校に知られますか?
SSWは学校の一員のため、担任や管理職には情報が共有されることがあります。ただし、守秘義務があり、不必要に情報が広がることはありません。
気になる場合は、申し込みの際に内容を確認しましょう。
QSSWとSCの両方に相談できますか?
はい、できます。SSWとSCが連携して、支援することも多いです。
QSSWに相談するのに、お金はかかりますか?
いいえ、無料です。
QSSWに相談できない場合はどうすればいいですか?
福祉事務所や保健所などにもソーシャルワーカーがいます。また大きな病院では「医療福祉相談室」が設置されています。病院に通院していなくても無料で相談できます。まずは、地元の病院に問い合わせてみましょう。
また、弊社での初回無料相談ではSSWとして活動経験のある精神保健福祉士の資格のある心理師が相談に乗ります。お気軽にお問い合わせください。
まとめ:福祉的視点での支援が強み
スクールソーシャルワーカー(SSW)の役割と活用法について、詳しく解説してきました。
最も大切なこと:
- 福祉的な問題は、SSWに相談
- 早めに相談する
- 一人で抱え込まない
- SCとSSWを使い分ける、または両方に相談
- 恥ずかしがらず、率直に相談する
スクールソーシャルワーカー(SSW)は、認知度が低いですが、非常に頼りになる専門家です。
特に、経済的困難、家庭の問題、福祉サービスの利用など、福祉的な視点での支援が必要な場合、SSWは強い味方になります。
スクールカウンセラー(SC)が心の問題を扱うのに対し、SSWは環境全体にアプローチします。
関係機関(児童相談所、福祉事務所、医療機関など)との連携・調整は、SSWの最も得意とするところです。
「家庭の問題を学校に相談するのは恥ずかしい」と感じるかもしれません。
でも、SSWは様々な家庭の問題を見てきた専門家です。恥ずかしがらず、率直に相談してください。
問題を一人で抱え込まず、早めにSSWに相談することで、子どもや家庭の状況が改善する可能性が高まります。
ぜひ活用してください。
もし、SSWの勤務日が少ないなど、スムーズに相談できない場合でもご安心d下さい。
弊社のでは初回無料相談では、SSWとして活動経験のある代表(吉田)が相談に応じます。
まずは、お気軽にご相談ください。