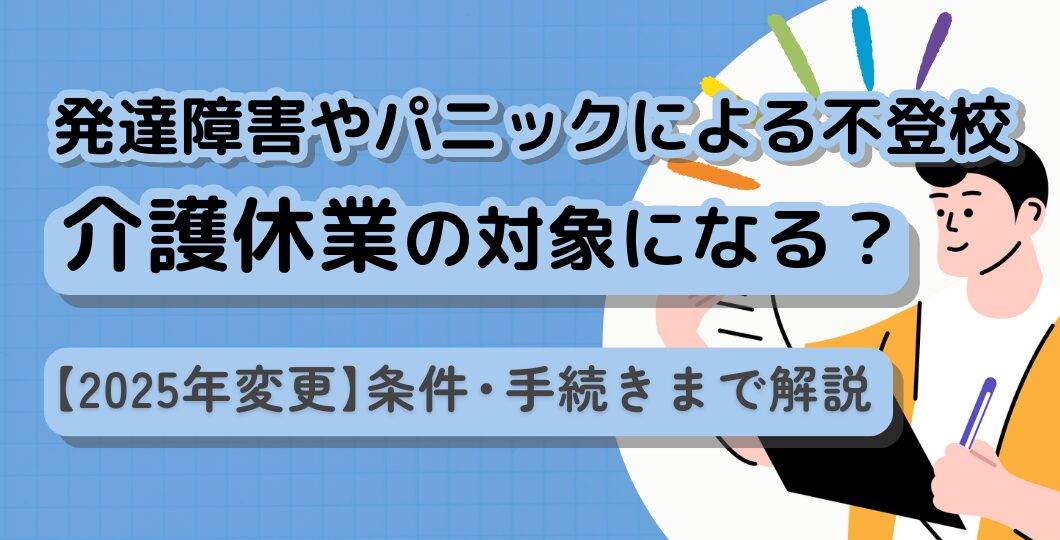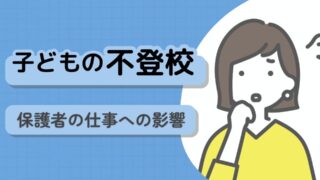「仕事を続けるべきか、それとも辞めるべきか…」
お子さんが不登校になったとき、多くの親御さんが直面する悩みです。
特に小学校低学年のお子さんの場合、一人で留守番をさせるのは難しく、仕事と家庭のバランスに悩む方は少なくありません。
「子どものそばにいてあげたい」「でも、経済的な不安もある」――
その葛藤の中で、仕事を続ける選択肢を模索する保護者も多いでしょう。
あまり知られていませんが、不登校の背景に発達障害や精神的な不安定さがあり、
ご家庭での常時見守りが必要な場合、介護休暇・介護休業の対象になる可能性があります。
この記事でお伝えしたいこと
執筆・編集責任:吉田克彦(合同会社ぜんと代表 公認心理師、精神保健福祉士)
- 不登校の家族支援25年以上、3000家庭以上の支援実績
- スクールカウンセラー歴20年以上。小学校、中学校、高校(全日制、定時制、通信制)全ての校種で勤務経験あり。
→詳しいプロフィールはこちら
不登校の子どもを支える親の仕事と生活の両立
子どもが不登校になると、親の生活や仕事に大きな影響を及ぼします。
特に小学校低学年など幼いお子さんの場合、昼間に一人で過ごさせることは危険です。
共働き家庭やひとり親家庭で仕事のためとはいえ、昼間子供だけで過ごすことはできません。
誰かが仕事を休み、お子さんの面倒を見なければなりません。
その結果、仕事を続けられず退職するケースも少なくありません。
親として子どもへの対応を考える
子どもが安心して過ごせる環境を整えることが最優先ですが、仕事を続けながらどのように対応するかを考える必要があります。短期的な対応だけでなく、長期的な視点を持って選択肢を検討しましょう。
介護休暇と介護休業制度の仕組みと取得方法
介護休暇と介護休業があります。
似ていますが、それぞれの内容は違いますので、きちんと理解して正しく使いましょう。
| 介護休暇 | 介護休業 | |
| 休める日数 (対象家族1人につき) | 年5日 ※時間単位での所得も可能 | 通算93日 ※3回まで分割が可能 |
| 申し出方法 | 当日の申請が可能 | 2週間前までの申請が必要 |
| 賃金 | 原則無給 | 原則無給 |
| 雇用保険の給付 | なし | 介護休業給付の受給が可能 (賃金の67%相当額) |
| 詳細 | 介護休暇について | 介護休業について |
※上記の表は、フルタイム勤務の従業員向けの条件です。パートやアルバイトなどの場合は該当しないこともありますので、ご注意ください。
短期間の休みなら介護休暇
介護休暇は、年間5日(対象家族が2人以上なら10日)取得できる制度です。
1日単位または時間単位での取得が可能です。
不登校の子どもの対応が必要なときに柔軟に利用できます。
しっかり休むなら介護休業
介護休業は、最大93日間(3か月)取得できる制度で、原則として要介護状態の家族が対象です。
要介護状態とは
育児・介護休業法に定める「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のこと(障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む。ただし、乳幼児の通常の成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合は含まない。)をいい、要介護認定を受けていることが必ずしも要件ではありません。
常時介護を必要とする状態については、判断基準が定められており、この基準を参照しつつ判断することとなります。
【常時介護を必要とする状態に関する判断基準】
注意:以下の内容は、わかりやすく説明するために実際の表現と変えております。正確には、厚生労働省の説明をご確認ください。
以下の項目の中で、「できないことがある」が2つ以上、あるいは「できない」が1つ以上ある。「できない」状況が継続すると認められる場合。
- 10分間一人で座っていることができない
- 立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩くことができない
- ベッドと車いす、車いすと便座の間を移るなどの乗り移りの動作ができない
- 水分・食事摂取が1人でできない
- 排泄が1人でできない
- 衣類の着脱が1人でできない
- 意志の伝達ができない
- 外出すると戻れないことや、危険回避ができないことがある
(発達障害等、知的障害などにより危険の認識に欠けることがある子どもが、自発的に危険を回避できない状態) - 物を壊したり衣類を破くことがある
(「自分や他人を傷つけることがときどきある」状態を含む。) - 周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れなど日常生活に支障を来すほどの認知・行動上の課題がある
(例:急な予定の変更や環境の変化が極端に苦手な子どもが、周囲のサポートがなければ日常生活に支障を来す状況(混乱・パニック等や激しいこだわりを持つ場合等)をいう。) - 医薬品又は医療機器の使用・管理
- 毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定ができない
上記の12項目のうち、太字になっている部分が特に不登校のお子さんには関係する場合が多いです。
以下は、実際によくある不登校の例を元に、判断基準に該当する可能性を考えています。
なお、実際にはそれぞれの状況に応じて判断されるため、あくまで”該当する可能性”と表現します。
小学生低学年で不登校になり、声かけや見守りがないと食べない(または過食する)ため、昼ご飯の管理が必要である(4.水分・食事摂取が1人でできないに該当する可能性あり)。
何か気に入らないことがあると、壁に頭を打ち付けたり、物を投げたりすることがある(9.物を壊したり衣類を破くことがあるに該当する可能性あり)。
不登校になってから、「消えたい」ということがあり、実際にリストカットをすることがある(9.物を壊したり衣類を破くことがあるに該当する可能性あり)。
「学校に行く」と家を出たものの、学校に登校せずにSNSで知り合った大人に会いに行ってしまった(8.外出すると戻れないことや、危険回避ができないことがあるに該当する可能性あり)。
基準に該当する“可能性”の例を紹介しました。
実際に介護休暇・介護休業の対象になるかどうかは、医師の判断や会社の就業規則によって異なります。
企業の対応によっては取得が難しい場合があるため、事前に職場と相談することが重要です。

会社によっては、医師の診断書の他に、カウンセラーの意見書が参考資料として扱われることもあります。
まずは、初回無料のカウンセリングを利用してみませんか?
不登校の子どもを支えるために仕事を辞めようと考えたらやること
仕事を辞める前に知るべき制度と選択肢
離職を考える前に、短時間勤務制度、フレックスタイム制、テレワークなどの選択肢を確認しましょう。
また、自治体によっては不登校支援のための助成金や相談窓口があります。
どのような制度を活用できるか調べることも重要です。
学校との連携と専門家への相談の必要性
学校のスクールカウンセラーや教育委員会のサポートを受けることで、家庭だけでの負担を軽減できます。また、専門的なカウンセリングを受けることで、子どもの心理的な負担を減らす手助けになります。
家庭と仕事のバランスを見直す判断ポイント
仕事を続けるかどうかを判断する際には、家庭の経済状況や子どもの状況を総合的に考えましょう。
また、親自身の心身の負担を軽減するためのサポート体制も重要です。
必要な手続きと診断書提出の方法
介護休業を取得するためには、精神科や小児科での診断を受け、医師の診断書を発行してもらう必要があります。
また、企業が介護休業を不登校にも活用できると知らない場合もあります。
介護休業中にやるべきこと
状況を正しく把握する
子どもが不登校になった理由や、現在の心理状態を正確に理解することが重要です。
専門家の助言を受けながら、冷静に状況を把握しましょう。
方向性と見通しを立てる
介護休業中の3か月間を有効に活用し、子どもが安心して生活できる環境を整えることが大切です。
ただし、3か月の間に完全な解決を目指すのではなく、長期的な視点でサポートを続けることが重要です。
ブリーフセラピーや認知行動療法などのカウンセリングを活用し、具体的なステップを踏んで回復を目指しましょう。

介護休業中(最大3か月)で、不登校の問題がすべて解決することは難しいでしょう。
この期間を有効に使って、休業明けの体制を作ることが大切です。
子どもの不登校で介護休業を利用する際のQ&A
介護休業制度を利用する際のよくある疑問にお答えします。
Q子どもの不登校について職場に知られたくありません。
人事担当部署などに相談して、プライバシーを守りながら申請することが可能です。
ただし、介護休暇・介護休業を取る際には職場の理解が必要です。どうしても理由を隠し続けるのは難しい職場もあるでしょう。
一番重要なのは「お子さんのケア」です。例えば、直属の上司には伝えるた上で協力を仰ぐなど、柔軟に考えることが必要です。
Q利用したいが職場が認めてくれない
担当者が充分に制度を理解できていない場合などもあります。その場合は、丁寧に説明することが大事です。また、パートやアルバイトなど有期雇用の場合は該当しないこともあります。
まずは、自治体の相談窓口などに相談してみましょう。
Q介護休業の間だけで問題が解決するでしょうか
それぞれのご家庭の状況によって異なりますが、焦りは禁物です。
介護休業の間に長期的な見通しと方針を考えることが重要です。
▶ 25年超のカウンセリングでわかった!親に必要な思考法
自分と家族のために正しい情報収集と冷静な判断を
子どもの不登校は親の生活に影響を与えます。
制度を活用しながら適切に対応することで、無理なく支えることが可能です。
まずは、お子さんの状態を確認して条件に当てはまるかを確認しましょう。
必要な情報を集めることで、家族にとって最善の選択ができます。
不明な点や疑問点があれば、後回しにせず専門家に確認しましょう。
私たちもお手伝いいたします!!