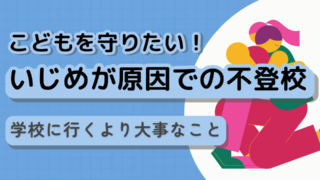- なぜSNSトラブルが起きるのか、その背景にある子どもの心理がわかる
- 実際に起きている、小学生から高校生までのトラブル具体例がわかる
- 子どもを追いつめる「二次被害」を防ぐ、親が今すぐ取るべき初期対応がわかる
- 子どもへの「言ってはいけない言葉」「かけるべき言葉」の具体的な使い分けがわかる
- トラブルを繰り返さないための、家庭での具体的なルール作りと関わり方がわかる
「友だちと何かあったのかな」
「またスマホばかり見てる…」
SNS上でのトラブルは、大人が考える「友だちとのケンカ」とは次元が異なります。
子どもの自己肯定感を根底から揺るがし、結果として「不登校」につながる、重大なサインとなります。
この記事でお伝えしたいこと
SNSトラブルの主な原因とは?不登校につながる3つの心理
「たかがSNS」と甘く見てはいけません。
SNSは人の心理を(良くも悪くも)非常を上手に利用しています。
ここでは、不登校の引き金ともなる3つのメカニズムを、心理の専門家として解説します。
承認欲求と自己肯定感の罠:「いいね」が子どもの価値を決めてしまう
SNSは、子どもの「認められたい」という自然な欲求を過度に刺激します。自己肯定感を著しく低下させる危険な構造を持っています。
その中心にあるのが、「いいね」やフォロワー数といった「社会的報酬」です。心理学的に見ると、これらの通知を受け取るたびに、脳内では快楽物質であるドーパミンが放出されます。これは非常に強力な報酬システムであり、子どもたちはこの快感を求めて、何度もSNSをチェックするようになります。
問題は、このシステムが「他者からの評価」を「数値」として可視化してしまう点にあります。思春期の子どもたちの自己肯定感は、まだ発達途上で非常に不安定です。多くの場合、自分自身の内側からではなく、他者からの評価によって自分の価値を測ろうとします。そこにSNSが登場すると、「いいねの数 = 自分の価値」という危険な方程式が、いとも簡単に成立してしまうのです。
思ったより「いいね」がつかなかった投稿は、単に「この投稿は人気がなかった」のではなく、「自分は人気がない、価値がない人間なんだ」という深刻な自己否定につなげるお子さんもいます。友人たちの楽しそうな投稿と自分の生活を比較し、劣等感を抱き、さらに承認を求めてSNSにのめり込む…この悪循環が、子どもの健全な自己肯定感の土台を崩します。
オンラインの同調圧力:「仲間はずれ」の恐怖が「No」を言えなくさせる
オンラインの世界、特にLINEのような閉鎖的なグループチャットでは、現実世界以上に強い「同調圧力」が働きます。
その理由は、子どもたちの社会が24時間365日、常に接続された状態にあるためです。学校の教室であればチャイムと共に解放されますが、LINEグループには終わりがありません。この閉鎖された空間からの「仲間はずれ」は、子どもにとって社会的な死を意味するほどの恐怖です。
この恐怖を増幅させるのが、LINE特有の「既読」機能です。「既読スルー(読んだのに返信しないこと)」は、意図的な無視、つまり攻撃や排除のサインとして受け取られがちです。そのため、「すぐに返信しないと仲間はずれにされるかもしれない」という強迫観念に駆られ、深夜まで続くグループチャットに、本当は嫌でも返信し続けてしまうのです。
このような経験が続くと、子どもは「自分の意見を言ってはいけない」「嫌だと感じてはいけない」という無力感を学習します。自分の意志で行動できないストレスが積み重なり、特定の友人グループやSNSそのもの、ひいてはそれらと繋がる学校生活全体が苦痛の対象となっていくのです。
攻撃性の伝染と「オンライン脱抑制効果」の罠
SNS上でのいじめは深刻化しやすいのが特徴です。心理学で「オンライン脱抑制効果」と呼ばれる現象にあります。これは、対面でのコミュニケーションでは働くはずの「抑制」、つまり「こんなことを言ったら相手が傷つくだろう」という歯止めが、オンラインでは効きにくくなる現象からです(心理学で「オンライン脱抑制効果」とよびます)。
この効果は、主に以下の3つの要因によって引き起こされます。
- 非対面性(Invisibility): 相手の顔が見えないため、相手への共感が著しく欠如し、普段なら絶対に言えないような残酷な言葉を投げつけることができてしまいます。
- 匿名性(Anonymity): 「どうせバレない」という匿名性は、自分の言動に対する責任感を希薄にし、罪悪感なく攻撃的な行動に加担しやすくなるのです。
- 非同期性(Asynchronicity): やり取りがリアルタイムではないため、「言い逃げ」が可能です。相手が傷つく様子を目の当たりにすることなく、一方的に攻撃的なメッセージを送りつけられるため、行動への歯止めがかかりにくくなります。
これらの要因が組み合わさることで、一つの悪口が集団心理によって瞬く間にエスカレートし、深刻なネットいじめへと発展するのです。
ここまでのポイント
- SNSトラブルの原因は、子どもの承認欲求や自己肯定感の低さといった心理に根差している。
- 「仲間はずれ」への恐怖から生まれる同調圧力が、子どもを精神的に追い詰める。
- 顔が見えないSNS特有のオンライン脱抑制効果が、いじめや攻撃を深刻化させる。
【年齢別】SNSの人間関係トラブル、実際の具体例
SNSトラブルと一言で言っても、その内容は子どもの年齢や利用するSNSの特性によって様々です。ここでは、実際にどのようなトラブルが起きているのかをご紹介します。ご自身のお子様の状況と照らし合わせながらご覧ください。
小学生に多い「LINEグループいじめ」とゲーム内トラブル
小学生のSNSトラブルは、日常的な連絡手段であるLINEや、人気のオンラインゲーム内など、比較的閉鎖的なコミュニティで発生する傾向があります。仲間意識が強い分、一度標的になると逃げ場がなく、いじめが深刻化しやすいのが特徴です。
- LINEでの仲間はずれ: クラスの公式LINEグループとは別に、特定の子だけを招待しない「裏グループ」を作成し、その子の悪口を言う。本人がいるグループで、わざと裏グループの話題を出して孤立感を煽る、といった陰湿な手口が報告されています。
- 既読無視・スタンプいじめ: グループ内で特定の子の発言だけを全員で「既読無視」する。また、「キモい」「ウザい」といった意味合いのスタンプを連打して、言葉を使わずに相手を攻撃するケースもあります。
- オンラインゲームでの口論: チームでプレイするオンラインゲームのチャット機能で、ゲームのミスを執拗に責めたり、「死ね」「消えろ」などの暴言を吐いたりするトラブルも少なくありません。
中高生に広がる「インスタ・TikTok」での無断投稿と誹謗中傷
中学生・高校生になると、InstagramやTikTokといった、よりオープンなSNSの利用が増え、トラブルの影響範囲も格段に広がります。友人同士の悪ふざけが、取り返しのつかない事態に発展する危険性をはらんでいます。
- 無断での写真・動画投稿: 本人の許可なく、変な顔や失敗した瞬間の写真、恥ずかしい動画などを投稿する。特にTikTokなどでは、面白いと思って投稿した動画が瞬く間に拡散され(炎上)、学校中に悪評が広まる深刻なケースも発生しています。
- 「ストーリーズ」の罠: 24時間で投稿が消えるInstagramの「ストーリーズ」機能は、「すぐに消えるから大丈夫」という誤った安心感を与えがちです。しかし、制服姿などが写り込んだ顔出し写真を安易に投稿した結果、スクリーンショットで保存・拡散され、個人情報が特定される危険性があります。
- 匿名暴露アカウントによる誹謗中傷: 特定の学校の生徒に関する嘘の噂や悪口を、匿名で投稿する「暴露アカウント」が作られることがあります。誰が書いているか分からないため、疑心暗鬼に陥り、人間不信になってしまう子どもも少なくありません。
いじめを超えた犯罪ケース:なりすまし・個人情報特定・自画撮り被害
SNSトラブルの中には、いじめの範疇を超え、警察が介入すべき「犯罪」となる悪質なケースも存在します。保護者として、これらの危険性を明確に認識しておくことが重要です。
- なりすまし: 他人になりすましてSNSアカウントを作成し、本人の社会的信用を失墜させるような悪意のある投稿を行う行為です。
- 個人情報の特定・拡散(doxing): SNSの投稿内容から本人の氏名、住所、学校などを特定し、インターネット上に晒す行為です。
- 自画撮り被害: SNSで知り合った相手に騙されたり脅されたりして、自分の裸や下着姿の写真・動画(自画撮り)を送らされてしまう被害です。
これらの行為は、お子様の心の安全だけでなく、身体的な安全をも脅かす重大な問題です。万が一、その兆候が見られる場合は、後述する専門機関や警察に速やかに相談する必要があります。
SNSの人間関係トラブルのまとめ
- 小学生はLINEグループなど閉鎖的な空間での仲間はずれが起こりやすい。
- 中高生はインスタやTikTokでの無断投稿など、より広範囲に影響が及ぶトラブルが増える。
- なりすましや自画撮り被害など、犯罪となりうる悪質なケースも存在する。
親の対応が鍵!子どもを二次被害から守るための初期対応5ステップ
お子様が勇気を振り絞って「SNSで嫌なことがあった」と打ち明けてくれた時。保護者様の対応が、その後の子どものメンタルヘルスを大きく左右します。
ここで最も重要なのは、「二次被害」を防ぐという視点です。一次被害がSNS上の加害者から受けた心の傷であるならば、二次被害とは、信頼する親からの良かれと思った言動によって、子どもがさらに深く傷つけられてしまうことです。この最初の対応を誤ると、子どもは「親にも分かってもらえない」と心を固く閉ざし、問題はより深刻化してしまいます。
ここでは、お子様を二次被害から守り、安全な避難場所となるために、保護者様が今すぐ取るべき具体的な5つのステップをご紹介します。
ステップ1:冷静に証拠を保存する – スクリーンショットの正しい撮り方
感情的に相手に抗議のメッセージを送ったりする前に、まず何よりも先に、トラブルの客観的な証拠を保存してください。
スクリーンショットを撮る際は、「誰が、いつ、どのような内容を」が必ず含まれるように撮影することが極めて重要です。アカウント名、投稿日時、投稿の全文が明確に写るように、画面全体を撮影してください。可能であれば、その投稿のURLも一緒にメモしておくと、後々、学校や専門機関に経緯を説明する際に、極めて強力な証拠となります。
ステップ2:子どもの話を「聴く」- 決して否定せず、気持ちを受け止める
証拠を確保したら、次はお子様の心に寄り添います。ここでの鉄則は、「評価せず、否定せず、ただ聴く」ことです。
【公認心理師が解説】子どもの心を閉ざすNG言動・安心させるOK言動
| NG言動(子どもを追い詰める言葉) | なぜNGなのか(心理的影響) | OK言動(子どもの心が軽くなる言葉) |
|---|---|---|
| 「あなたにも悪いところがあったんじゃ?」 | 典型的な被害者非難です。子どもに親から見捨てられたという絶望感を与えます。 | 「話してくれてありがとう」 |
| 「SNSなんてやめなさい!」 | 問題の単純化であり、子どもの世界を理解していないことの表明です。解決策の押し付けになります。 | 「一番つらかったのはどんなこと?」 |
| 「そんなこと気にするな」 | 子どもの感情の否定です。「自分の感情は間違っているんだ」と感じ、本音を話さなくなります。 | 「お母さん(お父さん)は、あなたの味方だからね」 |
まずは「そうだったんだね」「つらかったね」と、子どもの気持ちを丸ごと受け止める姿勢を見せてください。子どもが安心して話せる環境を作ることが、問題解決の最も重要な第一歩です。
ステップ3:冷静に事実を確認し、子どもの感情を言語化させる手伝い
子どもが少し落ち着き、安心して話せる状態になったら、何が起きたのかを一緒に冷静に整理していきます。
重要なのは、事実関係を時系列で整理すると同時に、「その時、どう感じた?」と、一つ一つの出来事に伴う感情に焦点を当てることです。子ども自身も自分の感情をうまく言葉にできず混乱していることが多いため、「それは悔しかったのかな」「すごく悲しかったんだね」と、保護者様が気持ちを代弁してあげることで、子どもは自分の感情を客観的に理解し、落ち着きを取り戻すことができます。
ステップ4:学校や信頼できる大人と連携・相談するタイミングの見極め方
家庭内だけでの解決が難しい、あるいはトラブルの相手が同じ学校の生徒である場合は、外部との連携が不可欠です。担任の先生やスクールカウンセラーに相談しましょう。
学校に相談する際は、ステップ1で保存した客観的な証拠と、ステップ3で整理した事実関係のメモを準備しておくと、迅速かつ的確な対応を促すことができます。感情的に訴えるのではなく、客観的な事実に基づいて冷静に相談することが、学校側を協力者として巻き込むための鍵となります。
ステップ5:物理的にSNSから距離を置く – 「デジタルデトックス」の賢い進め方
トラブルが起きているSNSから物理的に距離を置くことは、これ以上心を傷つけないために非常に有効な応急処置です。ただし、一方的な「禁止」は逆効果です。
「トラブルのことで心がすごく疲れていると思うから、少しの間だけ、SNSから離れて心を休ませてあげない?」など、子どもの気持ちを気遣う形で提案しましょう。その間に、親子で一緒に楽しめることや、子どもが好きなことに没頭できる時間を提供することで、SNSへの執着を和らげ、他の世界にも楽しさがあることを再発見するきっかけになります。
トラブルを繰り返さないために:家庭で育むSNSとの健全な付き合い方
目の前のトラブルへの対応と並行して、今後同じような問題を繰り返さないための長期的な対策を始めることが、根本的な解決には不可欠です。応急処置だけでなく、お子様が今後健全に付き合っていくための「心の免疫力」と「正しい知識」を家庭で育んでいきましょう。
親子で一緒に作る「我が家のスマホ・SNSルール」とは?
ルールは、親が一方的に押し付けて管理するためのものではありません。
子どもが自らの意志で自分を守るために、その必要性を理解し、納得して守れるものであるべきです。
例えば、子どもにだけ厳しいルールを設定して、保護者がずっとスマホを見ているようでは、反発されるのも当然です。
最も重要なのは、ルールを守るかどうかではなく、ルールを「親子で一緒に作る」というプロセスです。
【成功のコツ:親子ルールの作り方 5ステップ】
- 話し合いの場を設ける: 「スマホのルールを決めよう!」ではなく、「使い方について、一緒に考えてみない?」と対等な立場で話し合いの場を設けます。
- まず子どもの意見を聞く: 「どんなことをしたい?」と、まずは子どもの希望を否定せずに全て聞き出します。
- 親の懸念を正直に伝える: 「お父さん・お母さんは、こういうことが心配なんだ」と、なぜルールが必要なのか、その理由を具体的に伝えます。
- 一緒にルール項目を決める: <ソフトバンクなどが提供するテンプレートを参考資料として紹介>などを参考に、利用時間や課金など、お互いが納得できる着地点を探ります。
- 契約書として明文化し、見直し時期を決める: 決まったルールは紙に書き出し、親子で署名をします。「まずは3ヶ月やってみて、また見直そうね」と、定期的な見直しの機会を設けることが重要です。
SNSに依存しない「自己肯定感」を育む、親子の日常的な関わり
SNSトラブルの最も根源的な原因は、多くの場合、子どもの自己肯定感の低さにあります。「自分は自分のままで価値がある」とお子様が心から思えるようになれば、それが最大の防御策となります。
- 結果(doing)ではなく、存在(being)を認める: テストの点数といった「結果」だけでなく、「毎日コツコツ練習していたね」といった**努力の「過程」**を具体的に認め、褒めてあげましょう。そして何よりも、「あなたがいてくれるだけで嬉しい」という無条件の愛情を伝え続けることが、子どもの心の安全基地を築きます。
- 子どもの「好き」を応援する: 親の価値観で判断せず、お子様が夢中になっていることを尊重し、一番の理解者・応援者でいてあげてください。
- 小さな成功体験を積ませる: 家庭内でのお手伝いなど、子どもが「自分にもできる」「役に立てた」と感じられる役割を与え、成功体験を積ませることも有効です。
トラブルを繰り返さないポイント
- 再発防止には、親子で一緒に**「スマホ・SNSルール」**を作成し、運用することが有効。
- 日々の関わりの中で子どもの自己肯定感を育むことが、最も根本的な対策となる。
SNSトラブルに関するよくあるご質問(FAQ)
- Q親が子どものスマホやSNSをチェックしても良いですか?プライバシーとの境界線は?
- A
無断でスマホを見ることは、子どもの信頼を著しく損なうため避けるべきです。チェックする場合は、必ず事前に子どもと話し合い、「親子で一緒に作るルール」の一部として合意しておくことが不可欠です。「安全を守るために、週に一度、一緒に投稿内容を確認する時間を作ろう」など、目的と範囲、頻度を明確にした上で、子どもの納得を得るプロセスを何よりも大切にしてください。
- Q子どもが「アカウントを消したい」と言い出しました。どう対応すれば良いですか?
- A
子どもが「アカウントを消したい」と言うのは、それだけ精神的に追い詰められている深刻なSOSサインです。まずは、「そう思うほどつらかったんだね」と、その気持ちを全面的に受け止めてあげてください。その上で、「アカウントを消すのはいつでもできるから、その前に何があったか少しだけ教えてくれないかな?」と、問題の背景に耳を傾ける姿勢を見せることが大切です。焦ってアカウントを削除してしまうと、いじめの証拠が消えてしまうリスクもあります。
- Qネットいじめと、ただの悪ふざけの違いは何ですか?
- A
最も重要な判断基準は**「相手がどう感じているか」**です。加害者側に悪ふざけの意識しかなくても、受け取った側が「不快だ」「つらい」と感じていれば、それは「いじめ」になり得ます。加えて、「継続性(繰り返し行われている)」「集団性(複数人が一人に対して行っている)」といった要素があれば、いじめである可能性が高いと判断できます。
解決の糸口が見えない時は、心の専門家にご相談ください
公的な窓口に相談しても、一般的なアドバイスに留まってしまったり、具体的な状況に踏み込んだ解決策が見出せなかったりすることもあるかもしれません。
そんな時、最後の砦となるのが、一人ひとりの状況に深く寄り添うことができる、心理の専門家です。
ぜんとカウンセリングでできること:心理の専門家だからこそ提供できる支援
私たち「ぜんとカウンセリング」は、不登校をはじめとする子どもの心の問題に特化した、公認心理師によるオンラインカウンセリングサービスです。私たちは、単に話を聞くだけでなく、心理学的な知見に基づいた具体的な解決策をご家族と一緒に見つけ出します。
- 保護者様への支援: お子様のことで悩み、ご自身を責めてしまっている保護者様の心のケアも、私たちは最優先に考えます。保護者様の心が安定することが、お子様の安心に繋がります。
- お子様へのアプローチ: お子様本人のカウンセリングを通じて、SNSによって歪んでしまった認知を修正し、自己肯定感を内側から育むお手伝いをします。
- 親子関係の再構築: ギクシャクしてしまった親子関係を修復し、お互いが信頼し合えるコミュニケーションを取り戻すための具体的な方法を、ご家族と一緒に実践していきます。
まずは初回60分無料相談で、現状をお聞かせください
もし今、どうすれば良いか分からず途方に暮れているのであれば、まずは一度、あなたのそのお気持ちを、私たち専門家にお聞かせください。
「ぜんとカウンセリング」では、通常60分13,200円の初回無料でご提供しています。
この60分間で、私たちが一方的に何かを判断したり、解決策を押し付けたりすることは決してありません。あなたの最も良き理解者として、混乱した状況を丁寧に整理し、暗闇の中に希望の光を見出すためのお手伝いをさせていただきます。無理な勧誘は一切ございませんので、どうぞ安心してお申し込みください。