 基礎知識
基礎知識
【没収は危険】不登校でゲームばかりしている子への理由と対処法
「うちの子は最近、学校に行かなくなって、ゲームばかりしているの…」。このような悩...
 基礎知識
基礎知識
「うちの子は最近、学校に行かなくなって、ゲームばかりしているの…」。このような悩...
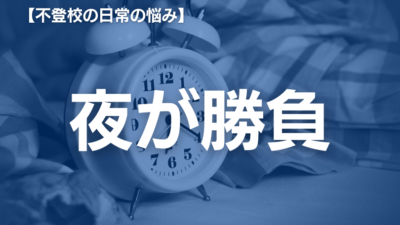 基礎知識
基礎知識
お子さんが不登校になると、毎朝、「学校に行きたい」「行きたくない」という子どもの...
 基礎知識
基礎知識
不登校の子どもが朝食を食べない理由は、非常に多面的で複雑です。心理的な問題、身体...
 基礎知識
基礎知識
お子さんの不登校を支援する際に大きなポイントになるのが生活リズム、特に起床時間で...
 基礎知識
基礎知識
この記事では不登校と関連のある「家族との関係」についてご紹介します。 家族と不登...
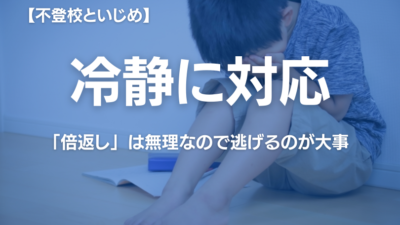 基礎知識
基礎知識
この記事でわかること どのようないじめがあるかがわかる いじめに対して、学校に期...
 基礎知識
基礎知識
家での時間が長くなる不登校の子どもたちの中には、食生活が乱れがちなケースが少なく...
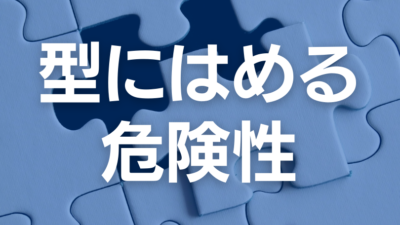 基礎知識
基礎知識
教育虐待とは何か?定義・子どものSOSサイン・親が陥る背景・今日できる防止策を公...
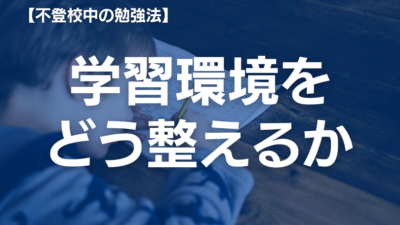 基礎知識
基礎知識
学校に行けない期間が長くなると、勉強への不安や焦りを感じるのは当然のことです。も...
 中学生
中学生
不登校の中には、HSPやHSCといった特性を持つ子どもたちもおり、彼らは特に繊細...
 基礎知識
基礎知識
「うちの子が学校に行かないのは、育て方が間違っていたのか」このように思う保護者の...
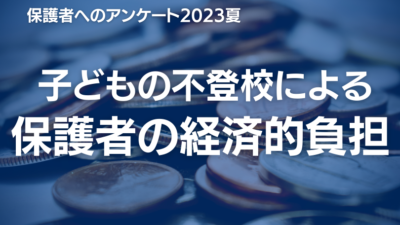 基礎知識
基礎知識
お子さんが不登校になることで、保護者のおよそ4割が「経済的負担が重くなった」と感...