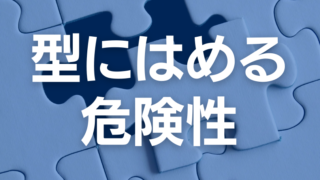お子さんが不登校になると「私の育て方が悪かったのでは?」と考えてしまう保護者さんは少なくありません。
特に、父親に比べて母親の方がお子さんの側にいる時間が長いご家庭が多いため、自分を責めがちです。
でも、不登校の原因は決して母親だけの問題ではなく、もっと複雑で多様な背景があります。
この記事では、不登校の原因を幅広い視点から解説しながら、母親が自分を責めすぎずに、子どもの気持ちに寄り添い、少しずつ前を向いていくための考え方や具体的なサポート方法をお伝えします。
「子どものために何ができるか」を一緒に考えていきましょう。
不登校の原因は複雑かつ多様
学校環境の問題
不登校の原因として、学校でのいじめ、教師との関係、学業不振などが挙げられます。
子どもにとって学校が居心地の悪い場所になっていないか、注意深く観察することが大切です。
子ども自身の特性や性格傾向
子どもの気質や性格、発達の特性なども不登校に影響を与えます。
内向的な性格、感受性の高さ、自己肯定感の低さなどは、不登校のリスクを高める要因となり得ます。
家庭環境や家族関係の問題
家族関係の不和、親の離婚、経済的困難など、家庭環境の問題も不登校の原因になることがあります。
ただし、これらは母親だけの責任ではなく、家族全体で取り組むべき課題です。
母親が不登校の原因が自分のせいだと感じてしまう理由
母親への社会的プレッシャーと固定観念
「子育ては母親の仕事」という社会的な固定観念から、母親は不登校の責任を感じやすくなります。
このプレッシャーが、母親の自責感を高めてしまうのです。
子育ての責任を母親が負いすぎている
母親は子育ての第一人者として、子どもの成功も失敗も自分の責任だと考えがちです。
しかし、子育ては母親だけでなく、父親や周囲の大人たちと協力して行うものです。
周囲の評価を気にしすぎる
「うちの子に限って不登校なんて…」と周囲の目を気にするあまり、母親は自分を責めてしまいます。
しかし、不登校は誰にでも起こり得る問題であり、恥ずかしいことではありません。
母親が自分を責めることのデメリット
「自分は悪くない、周りが悪いのだ」と考えるよりも「自分のせいかもしれない」と、主体的に考える方が解決に結びつきやすいことが多いです。
なぜなら、過去と他人は変えられませんが、自分と未来は変えられるからです。
しかしながら、あまりに「自分が子どもの育て方を間違えたのだ」などと責め続けてばかりいても問題解決には結び付きません。
問題を解決どころか悪化させてしまう危険があります。
母親のメンタルヘルスの悪化
自分を責め続けると、母親はストレスを抱え、うつ症状などのメンタルヘルス不調を来たすリスクが高まります。
母親の健康が損なわれれば、子どものサポートにも支障が出てしまいます。
子どもへの悪影響
母親が自責感にとらわれていると、子どもに対して過干渉になったり、逆に放任主義になったりと、一貫性のない対応になりがちです。
これは子どもの不安を増幅させ、不登校の改善を妨げます。
問題解決の遅れ
母親が自分を責めることに集中するあまり、不登校の真の原因究明や具体的な解決策の検討が遅れてしまう恐れがあります。
子どもの気持ちを理解することの重要性
子どもの話に耳を傾ける
不登校の子どもは、自分の気持ちを言語化するのが苦手なことがあります。
母親は忍耐強く、子どもの話に耳を傾け、そのメッセージを読み取りましょう。
子どもの感情を受け止める
子どもが不安や怒り、悲しみなどの感情を表出したら、それを否定せずに受け止めましょう。
「学校に行かなければ」と急かすのではなく、子どもの感情に寄り添うことが信頼関係の構築につながります。
【関連記事】
▶ 子どもの自己肯定感を高めるために親ができるアプローチ
▶ 【過干渉】不登校の子どもに口出しをしすぎる問題点と改善方法
子どもの立場に立って考える
大人の価値観で子どもを判断するのではなく、子どもの目線に立って物事を見ることが重要です。
学校に行けない辛さ、友人関係の難しさなど、子どもなりの苦悩を想像してみましょう。
母親ができる具体的なサポート
安心できる家庭環境を作る
子どもが安心して過ごせる家庭環境を整えることが、母親の重要な役割です。
子どもの話に耳を傾け、受容的な態度で接して、家庭を心の拠り所を作りましょう。
学校以外の居場所を見つける
学校に代わる楽しみや学びの場を提供することで、子どもの自尊心を回復することができます。
学校以外の習い事、地域のイベントへの参加など、子どもが興味を持てる活動を一緒に探してみましょう。
子どものペースを尊重する
不登校の改善には時間がかかります。
子どものペースを尊重し、焦らずに見守ることが大切です。
小さな変化や頑張りを見逃さず、褒めて励ましながら、子どもの主体性を育てていきましょう。
専門家に相談する
必要に応じて、カウンセラーや医師などの専門家への相談をおすすめします。
専門的な助言は、母親の不安を和らげ、具体的な解決策を見出す大きな助けになります。
母親自身のメンタルヘルスケア
自分の気持ちを大切にする
不登校の子どもを支えるには、母親自身が心身ともに健康でなければなりません。
母親の気持ちも大切にし、無理をせず、自分のペースで子育てに取り組むことが重要です。
ストレスマネジメントを実践する
母親のストレスは子どもにも伝わります。ストレス解消法を見つけ、実践すると、母親の心の余裕が生まれ、子どもにも良い影響を与えられます。
サポートを求める
母親が一人で悩みを抱え込まないことが大切です。
父親や祖父母、信頼できる友人など、周囲の人にサポートを求め、悩みを共有することで、心の負担が軽減します。
母親が心掛けるべきこと
不登校の原因を客観的に見る
不登校の原因を母親の育て方だけに帰結させるのは適切ではありません。
学校環境、子ども自身の特性など、様々な要因を客観的に見つめ、必要な支援を検討することが重要です。
子どもの自立心を尊重する
不登校の子どもを過保護にするのは逆効果です。子どもの自立心を尊重し、できることは子ども自身にやらせるなど、将来に向けた成長を促すことが大切です。
最近では、勉強を無理強いさせたり、子どもの要望を無視して保護者のエゴだけで受験先を決めてしまうといった教育虐待が社会問題化しています。
自分自身の人生も大切にする
母親は子育てだけでなく、自分自身の人生も大切にする必要があります。
子育ての合間に自分の時間を持ち、自分らしさを発揮できる場所を見つけることで、母親としてのエネルギーを取り戻せるでしょう。
おわりに
不登校の子を持つ母親は、自分を責める必要はありません。
子どもの気持ちに寄り添い、適切なサポートを提供することが大切です。
母親一人で抱え込まず、周囲の助けを借りながら、子どもの成長を見守っていきましょう。