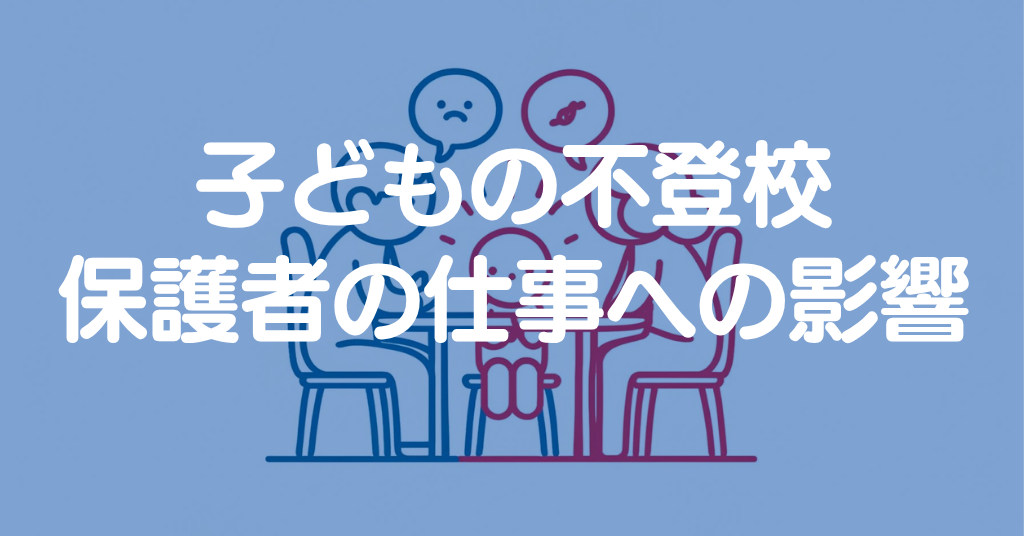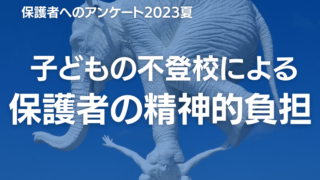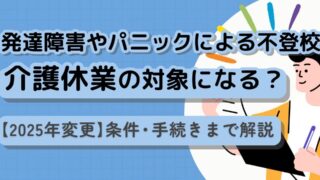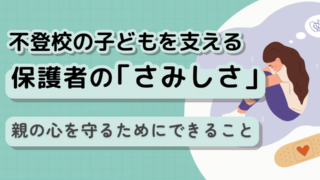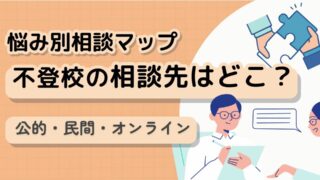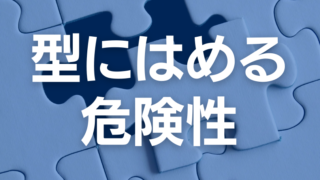子どもが不登校になると、多くの保護者が「仕事を辞めるべきだろうか」という悩みに直面します。
子どもに寄り添いたい気持ちと、収入や職場への責任感の間で心は揺れ動きます。
答えが見つからず苦しんでいる方も少なくありません。
この記事では、小学2年生と年長のお子さんを育てながら、ファイナンシャルプランナー2級の資格を持つライターさんに、実際の子育て経験と家計管理の専門知識を活かして執筆いただきました。
ライターさん自身も、仕事と育児の両立に悩みながら家計の見直しや資産形成に取り組んできた経験があります。
記事では、仕事を辞めることで得られるものと失いやすいもの、判断のポイント、そして辞める前にしておくべき準備など。
保護者目線と家計の専門家としての視点の両方から丁寧に整理しています。
また、仕事と不登校の子育てを両立させる工夫や、経済的な不安を軽減するための具体的な方法も紹介します。
執筆・編集責任:吉田克彦(合同会社ぜんと代表 公認心理師、精神保健福祉士)
- 不登校の家族支援25年以上、3000家庭以上の支援実績
- スクールカウンセラー歴20年以上。小学校、中学校、高校(全日制、定時制、通信制)全ての校種で勤務経験あり。
→詳しいプロフィールはこちら
不登校小学生を抱える親は仕事辞めるべき?
学校の行き渋りが増えると、親は「仕事を辞めたほうが良いかも」と考えてしまいます。
子どもを優先したいけれど、同僚や上司の目や収入が減ることが気になり、離職の判断に迷う保護者さんも多いです。
不登校の小学生を持つ親が仕事の両立で生じる悩み
仕事で忙しい保護者にとって、登校を渋る子どものサポートは大きな負担となります。
小学生の不登校の保護者が抱える具体的な悩みを整理しました。
仕事を休まざるを得ない日が増える
朝の登校渋りの対応や、日中に1人で家にいることへの不安から仕事の勤務調整や休みのお願いをする機会が増えます。
特に在宅勤務ができない仕事は、調整がつきにくいでしょう。
子どものためとはいえ、職場の方に勤務調整をすることに負担を感じるでしょう。
欠勤や早退が評価や職場の人間関係に影響する
頻繁な欠勤や早退は、職場での評価や人間関係に影響をし始めます。
同僚に業務のフォローを頼む回数が増えると、申し訳なさを感じるでしょう。
また子どもを理由に、昇進や昇給の機会を逃すこともあります。
また家族の事情を職場に話すかも悩ましい問題です。
職場によっては、「家庭と仕事は別」と思われる場合もあります。
こうした状況が続くと、仕事をすること自体がストレスになるでしょう。
学校や行政との連絡・対応に時間と手間がかかる
状況確認のため、学校や相談機関との連絡・面談に時間を要します。また適応指導教室を検討する場合、見学や手続きも必要です。
これらは平日日中に対応する必要があるため、仕事中に対応をしないといけません。
支援を受けるための書類作成や申請手続きは、保護者にとって大きな負担です。
時間のやりくりに疲弊し「仕事か子どもか、どちらかを選ばなければ」と追い詰めてしまうでしょう。
子どもを家に1人ぼっちにさせる不安
仕事中、家で過ごすお子さんが気になりますよね。
「今日は大丈夫だろうか」「何かあったらすぐに駆けつけないと」など、仕事中も気が気でないでしょう。
特に気持ちが不安定な時期は、お子さんの孤立感が深まり、状況が悪化するかもしれません。
不安を抱えながらの仕事は、親の精神面にも影響を与えます。
「不登校=親のせい」と罪悪感を感じる
多くの保護者は「不登校の原因は自分だ」と罪悪感を感じています。
仕事を頑張る保護者ほど、「仕事で子どもとの時間が少なかった」「早く気づいてあげられたら」と自分を責めてしまいます。
時には「子どもが不登校になったのは親が仕事中心で子どもに愛情をかけていないから」などと心無い言葉をかけられた方も、多いようです。
こうした罪悪感は、仕事を続けることへの迷いを強めます。
実際には不登校の原因は複雑で、親だけの責任ではないことが多いです。
一方で、親自身の精神的余裕がないと、仕事を続けるかも冷静に判断できません。
親が仕事を辞めるかどうか判断するポイント
仕事を辞めるかは、慎重に判断しましょう。焦りや不安の感情で判断すると、後悔する可能性もあります。
判断の際は、子どもの状況、親自身の心身の健康、家計状況の3つから総合的に考えましょう。
1. 子どもの状況・状態はどうか
まずは、子どものメンタル状態や生活の安定度を確認しましょう。
常に親のサポートが必要な状態か、自分で気持ちを整理できる段階かで対応は変わります。
また、フリースクールや習い事などの「家以外の居場所」の有無も重要なポイントです。
家以外の居場所があると、平日日中も子どもは孤立せずに過ごせます。
専門家の意見も参考にしつつ、子どもに必要なサポートを考えると判断しやすいでしょう。
2. 自分の心身の健康を保てるか
保護者自身の心身の状況も振り返りましょう。
睡眠不足や食欲不振、常に不安やイライラ感がある場合は、頑張り過ぎているサインかもしれません。
仕事が気分転換になったり、職場での人間関係が心の支えになっていたりする場合は、健康維持のために両立を検討しましょう。
3. 家庭の経済状況の把握
仕事を辞めた場合、家計への影響を不安に感じる方は多いでしょう。
家計への影響を知るために必要なのが毎月の収支とライフプランの把握です。
現在の収支を整理し、離職後に生活が成り立つか、貯蓄で耐えられる期間を確認します。
一般的には、万が一のための貯蓄は3~6ヵ月分あれば安心と言われます。
しかし、お子さんの不登校が長引く可能性を踏まえ、1年分の収入を備えましょう。
ただし、住宅や車のローンや自分自身の奨学金返済がある場合は、特に慎重な検討が必要です。
不登校の子の親が仕事を辞めて得られるもの
仕事を辞めることは大きな不安が伴いますが、同時に得られるものもあり、家族にとって新しいスタートになる可能性もあるのです。
子どもに寄り添う時間を確保できる
仕事を辞めると、子どもの気持ちに寄り添う時間を増やせます。朝夕の慌ただしさから解放され、子どものタイミングでゆっくり話を聞いてあげられます。
家庭の安心感につながり子どもの回復を助ける場合もある
親が家にいることで、安心感を持つお子さんもおられます。
特に不安や恐怖を感じやすいお子さんは、親がいることで心が安定し、前向きな気持ちを取り戻すケースもあります。
心身の負担を減らし自分の健康を守れる
両立の疲弊から解放され、親自身の心身の健康を守れます。
仕事を辞めたことで、慢性的な睡眠不足や精神的な緊張から解放され、体調が回復した方もおられます。
また自分の時間がもてるため、趣味や運動、カウンセリングもできます。
仕事を辞める前に知っておきたいこと
仕事を辞める前に準備しておくべきことを確認しましょう。
支出の見直し、お金の見通しをたてる
離職すると収入が減るため、支出の見直しやお金の見通しをたてましょう。
1. 支出の見直し
支出を見直すために、まずは家計簿をつけて支出を把握しましょう。
家計簿をつけると、毎月どこにいくら使ったかを把握でき、さらに節約できる部分がわかります。
家計の見直し経験がない方や何を見直せば良いか分からない方は、以下の項目を見直しましょう。
| 見直し項目 | 具体例 |
| 光熱費 | 契約会社の変更 |
| 保険費 | 内容・契約会社の見直し |
| 通信費 | 格安キャリアへの乗り換え |
| サブスク | 不要なものの解約 |
これらは、1度の見直しで、その後の支出を抑えられるためおすすめです。
2. お金の見通しをたてる
離職期間が長くなると、経済的な不安は大きくなります。不安を軽減するために、長期的なお金の見通しをたてましょう。
以下のサイトを活用するのがおすすめです。
お金の見通しをたてると、収入が無くても、どのくらいの期間なら生活できるか、パート収入がどの時点で必要になるかなども把握できます。
また、失業手当や母子父子寡婦福祉資金貸付制度など、金銭的な支援制度も確認するとさらに安心です。
こうした準備は、離職後の経済的な不安を和らげます。
利用できる支援制度やサービスを知る
仕事を辞めると子どもとの時間は増えますが、1人の時間がとれないため疲れを感じます。
以下の支援制度やサービスを活用しましょう。
- ファミリーサポート: 地域の会員同士で子どもの預かりや送迎をサポートしてくれる。
- スクールソーシャルワーカー: 学校と家庭、福祉機関をつなぐ専門職に相談できる。
- 家事代行サービス: 掃除や料理などを依頼でき、親の家事負担を軽減できる。
- 食材宅配サービス: 注文した食材を家まで配送する。買い物の手間を省ける。
- 放課後等デイサービス: 発達に課題があるお子さんの居場所として利用可能。
- 訪問看護: 医療的なサポートが必要な場合、自宅で看護を受けられる。
これらを活用することで保護者だけで抱え込まず、心身の余裕をもてます。
空いた時間は将来につながる準備にできる
離職後は、自分の将来につながる準備もできます。
例えば、キャリアチェンジを見越した資格取得やオンライン講座での学習、在宅でできる仕事へ挑戦するなど、新しい働き方を模索することも可能です。
再就職やキャリアアップを見据え、この期間を有効に使うことで、将来の不安を前向きな行動に変えられます。
不登校の子の親が仕事を辞めると失いやすいもの
仕事を辞めることで得られるものがある一方で、失うものもあります。
デメリットを理解した上で、自分と家族にとって最適な選択を考えましょう。
収入減により生活が不安定になる
仕事を辞めると、当然ですが収入が大幅に減ります。
貯蓄があっても、不登校が長期化すれば、経済的な余裕はどんどん失われます。
社会的なつながりを失うリスクがある
仕事は収入だけでなく、社会とつながれる場です。
仕事を辞めると、職場の方との会話や仕事の達成感なども失い、孤立を感じる保護者も少なくありません。
再就職が難しくなる可能性がある
一度仕事を辞めると、再就職が難しくなります。
元職場と同じ条件で働くことは簡単ではありません。
また不登校の子どもがいると伝えると「休みがちになるのでは」と敬遠される可能性もあります。
不登校と仕事の両立を可能にする方法も
工夫をすることで、家庭と仕事の両立継続は可能です。
| 方法 | 詳細 |
| 勤務形態や働き方を柔軟に見直す | フルタイムから時短勤務への転換、在宅勤務やフレックスタイム制度の活用などを検討。 |
| 家族や職場の理解を得る工夫をする | パートナーや家族と家事分担や子どものサポートについて話し合う。職場では信頼できる上司に相談し、勤務調整への理解を得る。 |
| 支援制度や学校外の居場所を活用する | 適応指導教室や習い事、地域の児童館などを利用し、子どもが孤立しないようにする。 |
| 家事サポートのサービスを活用する | 家事代行サービスや食材宅配などを利用し、家事負担を減らす。 |
資産運用(投資)を始める
両立する中でも「辞めたほうがよいかも」「大変な状況がいつまで続くのか」と不安になることもあるでしょう。 両立の不安を減らすためにも「資産運用(投資)を始める」こともおすすめです。
投資と聞くと「危ない」「怖い」と感じる方も多いですが、以下のポイントを踏まえ運用すれば、着実に増やすことができます。
(1)生活防衛資金をつくる
怪我や病気・葬儀など万が一のことがあった時のための備えを作ってから投資をスタートしましょう。会社員であれば、収入の3~6ヵ月分が目安です。
(2)NISAを活用する
NISAは「少額投資非課税制度」のことで、投資から得られる利益が非課税になる国の制度です。通常であれば、利益に対し約20%の税金がかかるため、お得な制度といえます。
(3)「長期・積立・分散」を意識する
運用する際は「長期・積立・分散」を意識しましょう。長期投資で時間を味方につけ、積立投資で株価の変動リスクを小さくできます。さらに、分散投資で様々な資産に投資することで経済状況による影響を抑えられ、安定した資産運用ができます。
会社員以外の収入ができると、離職に対する不安が減り、両立し続けることへの精神的な負担を減らすこともできるでしょう。
仕事を辞めるかを少しでも迷ったら、まずは両立できる方法を検討しよう
今回は、小学生のお子さんがいらっしゃるファイナンシャルプランナーに具体的なアドバイスを書いて頂きました。
仕事を辞めるか迷ったときは「保護者自身が安心できる選択」をしましょう。
親の不安が強いと、十分に子どもをフォローできません。
すぐに仕事を辞める決断ができないのは自然なことです。
まずは家族、学校、職場、支援機関などに相談しながら、両立の道を探してみましょう。
両立する中で限界を感じても、離職準備をしつつ「辞める」選択を検討できます。