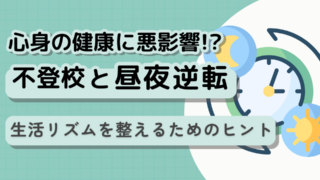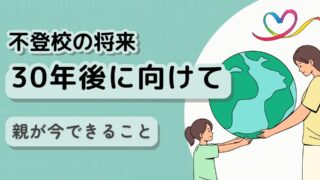- 不登校の子どもにとって夏休みが大切な理由がわかる
- 不登校の子どもと親子で楽しめる夏休みの過ごし方を知れる
- 夏休み明けの学校復帰に向けての準備と心の準備の仕方がわかる
「昼夜逆転している」
「ゲームばかりしている」
「勉強を全くしない」など、
お子さんの夏休みの過ごし方に不安を感じている保護者の方は多くいらっしゃいます。
でも、安心してください。
実は、夏休みは不登校の子どもにとって、心と体を休める大切な「回復の時間」でもあるのです。

この記事では、心理学の視点から、不登校のお子さんとそのご家族のために、夏休みを安心して過ごすヒントをわかりやすく解説します。
執筆・編集責任:吉田克彦(合同会社ぜんと代表 公認心理師、精神保健福祉士)
- 不登校の家族支援25年以上、3000家庭以上の支援実績
- スクールカウンセラー歴20年以上。小学校、中学校、高校(全日制、定時制、通信制)全ての校種で勤務経験あり。
→詳しいプロフィールはこちら
不登校の子どもにとって夏休みが「特別な期間」である理由
学校に行かなくていい夏休みは、子どもにとって「プレッシャーから解放される時間」です。
普段の学校生活では、朝起きられないことで「なんでちゃんと起きないの?」と言われたり、友達との関係がうまくいかなくて毎日気を使ったり、勉強の遅れを先生や周りの人に指摘されたりと、たくさんのストレスを抱えています。
でも夏休みは違います。
朝起きなくても誰にも怒られませんし、苦手なクラスメイトに会う心配もありません。 「みんなについていけない」という焦りからも、しばらく離れることができるのです。
このように、安心して過ごせる時間があることは、子どもの心の安定につながります。
ただし、孤独や無力感を感じやすくなる時期でもあるため、「何もしない=悪いこと」ではないということを、まずはご家族が理解してあげることが大切です。
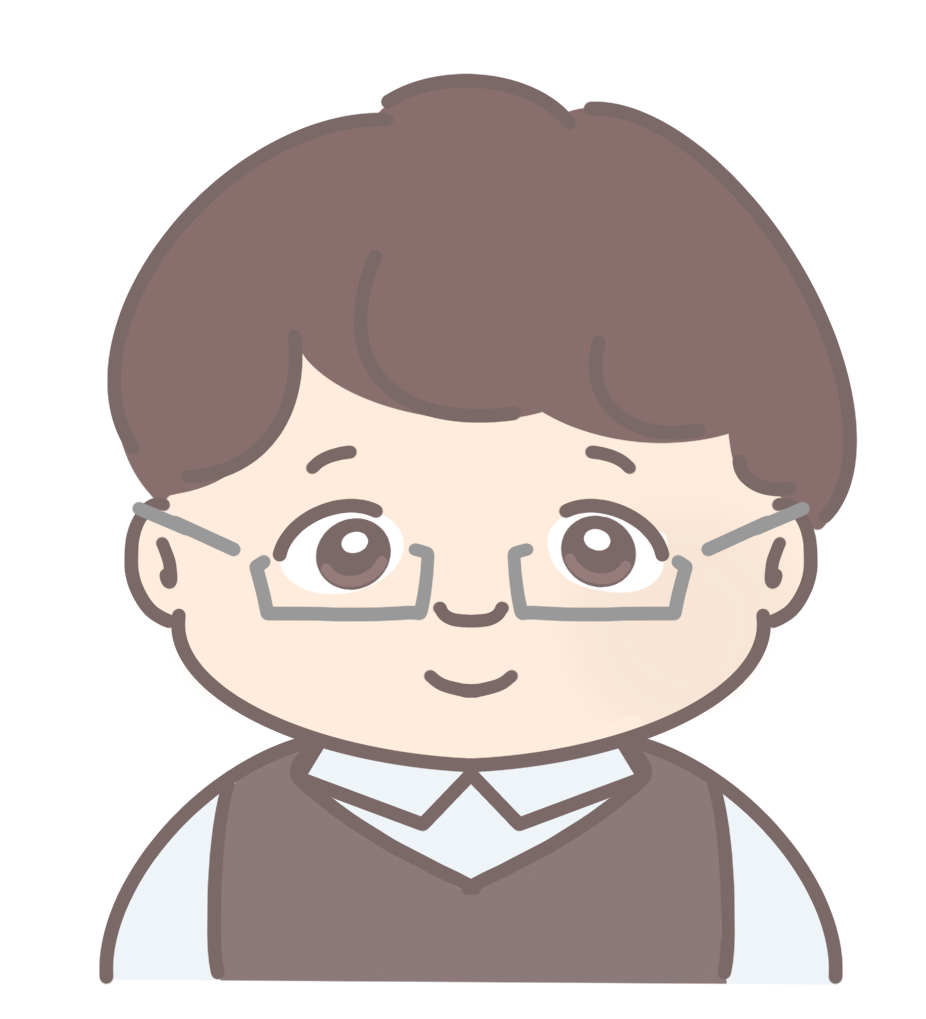
休息は、心と体のエネルギーを取り戻すために必要不可欠です。無理に動かすより、安心して休める環境を整えることが、回復への第一歩です。
「ダラダラしてよい」と話をすると、保護者さんはとてもビックリされます。
しかし、とても大事なことです。
夏休みにやりがちなNG行動と親の心構え
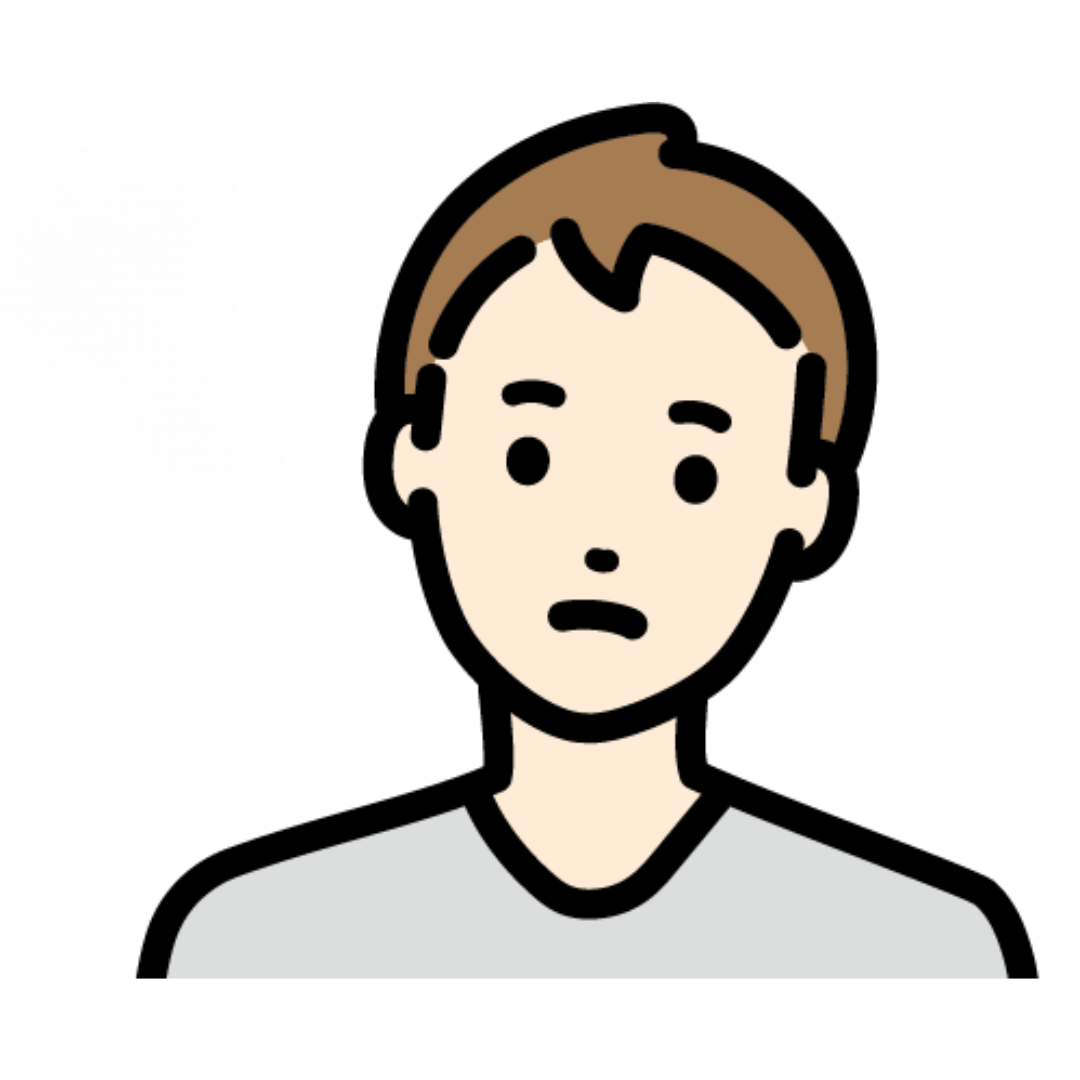
休息が大事だという意見はわかるけれど、毎日ゴロゴロしている子供を見ていると「このままでいいのか」「もっとプッシュしないとだめじゃないか」と思ってしまう。
夏休みは、子どもたちに平等に与えられたダラダラしてよい期間です。
不安な気持ちから、つい子どもに対して厳しく接してしまうことがあります。
たとえば、家でゴロゴロしている子どもを見ると「少しでも外に出なさい」と無理に外出を促したくなったり、勉強する様子が全く見えないと「このままで大丈夫なの?勉強しなさい」と強く言ってしまったりします。
また、元気に学校に通っている他の子どもの話を聞くと、つい「○○ちゃんは毎日頑張ってるのに」と比べてしまうこともあるでしょう。
ご家族の気持ちは本当によくわかります。
でも、これらの言葉は子どもにとって大きなプレッシャーとなり、かえって心を閉ざす原因になってしまうことが多いのです。
まずは、「焦らなくていい」「今は回復の時間なんだ」と、保護者さん自身にも言い聞かせてください。
大人にも当てはまりますが、「これ見て!」と言われるよりも「見ちゃダメ!!」と言われる方が気になって、覗いてみたくなりますよね?
勉強、特に宿題などは「宿題やりなさい!」と言われると「今やろうと思ってたのに、言われたからやる気なくなった」という経験ありませんか?こ
「~~しなさい!」ということで、本人のやる気(内発的動機付け)を下げてしまうことがあります。
子どものタイプ別・夏休みの過ごし方5つのヒント

① 無気力タイプ:「何もしない」を許すことから始める
何もしたくないときは、「休むこと」が大切な行動です。
「今日は何もしなくていいよ」と伝えることで、安心してエネルギーを回復できます。
② 昼夜逆転タイプ:生活リズムを整える小さな工夫
昼夜逆転は、不登校の子どもによく見られる現象です。 夜中までゲームをしたり動画を見たりして、昼間は眠っているという生活になってしまうことがあります。
いきなり「明日から朝7時に起きなさい」と言っても、体がついていきません。 大切なのは、少しずつ自然に戻していくことです。
まずは、朝起きたときにカーテンを開けて、お日様の光を浴びる習慣を作ってみましょう。 太陽の光は体内時計を整えてくれる効果があります。 そして、お昼頃に「ちょっと玄関まで一緒に歩かない?」と声をかけて、短い時間でも外の空気を吸う機会を作ってみてください。
寝る前にスマホやタブレットを見ると、明るい光で眠りにくくなってしまいます。 「寝る30分前はスマホをお休みしよう」と、お子さんと一緒に決めてみるのもいいでしょう。
無理に「早起きさせる」ことにこだわらず、自然に戻せるような環境づくりが大切です。
③ ゲーム・ネット好きタイプ:「好き」を学びや自信につなげる
「うちの子はゲームやYouTubeばかり見ていて心配」という声をよく聞きます。 実はそれも悪いことではありません。理由は大きく2つあります。
つらいことを思い出さないための安全地帯
お子さんがゲームやYouTubeに夢中になっているなら、「もし、ゲームも動画も見なかったら他に何をしているだろう」と考えてみてください。 「そんなの勉強するに決まっているでしょ!」と思うなら、本当にそうでしょうか? 自分が子どもの頃、何もすることがなかったからとバリバリ勉強をしていましたか? もちろん、バリバリ勉強をしていた人もいるでしょうが、多くのお子さんは何もすることが無いとグダグダ過ごします。 そして、そういう時に嫌な経験を思い出してしまうのです。
特に不登校になったお子さんは「友人関係のトラブル」や「将来への不安」「勉強ができず悔しい思いをしたこと」などを反芻する(繰り返し思い出してしまう)ことがあります。
実は、ゲームやYouTubeに夢中になるのは、「嫌なこと思い出したくないから、何か他のことで気を紛らわしている」という状態です。
だからこそ、夢中になる時間は必要な時間ともいえるのです。 もし、ゲームやYouTubeの時間を減らしたいのであれば、やらなくなった時間に何をすればいいか(勉強をするとか、将来について考えるなどということではなく)楽しい代替行為を考える必要があります。
夢中になることで関連する知識が増える
ゲームやYouTubeが好きな子には、「それを通じて何かを学ぶ」という視点を持ってみてください。
海外のゲームをプレイしていれば、自然と英語の単語を覚えることができます。
面白い動画を見て「自分も作ってみたい」と思ったら、動画編集に興味を持つかもしれません。
好きなアニメのキャラクターを描いてみることで、絵の才能が開花することもあります。
大切なのは、「好きなこと」を否定するのではなく、そこから何かプラスのものを見つけることです。
子どもが夢中になれることがあるということは、とても素晴らしいことなのです。
「好きなこと」は、自己肯定感を育てるきっかけになります。
④ 勉強の遅れが気になるタイプ:小さな成功体験を大切に
「このまま勉強しないでいると、どんどん遅れてしまう」という不安は、多くの保護者の方が抱えています。
しかし、今は無理に追いつこうとしなくても大丈夫です。
大切なのは、勉強に対する「嫌な気持ち」を取り除くことです。 ここで、強引に勉強を強制すると、勉強に対してさらに苦手意識を持ってしまうだけでなく、家族との関係も悪くなってしまいます。
まずは「1日5分だけ」というように、本当に短い時間から始めてみてください。 長時間勉強させようとすると、子どもは「やっぱり無理だ」と感じてしまいます。また、子ども自身が「これならできそう」と思える教材を選ばせてあげることも大切です。
そして、どんなに小さなことでも「できたね!」「頑張ったね!」と声をかけてあげてください。「漢字を一文字覚えた」「計算問題を一問解けた」、そんな小さなことでも、子どもにとっては大きな成功体験になります。
📘【おすすめ教材】 オンライン教材を使えば、家にいながら自分のペースで学べます。 —
⑤ 孤立しがちなタイプ:家庭以外の「居場所」を見つける
不登校になると、同年代の友達と会う機会が減ってしまいます。そのため、「自分だけが取り残されている」という孤独感を感じやすくなります。
そんなときは、学校以外の「居場所」を探してみることも大切です。フリースクールの中には、夏休み中に体験プログラムを開催しているところもあります。また、最近では、オンラインで同じような悩みを持つ子どもたちがつながれるコミュニティも増えています。
「家族以外の誰かとつながれる場所」があると、子どもは「自分一人じゃない」と感じることができます。すぐに参加するのが難しくても、「そういう場所があるんだ」と知っているだけでも、心の支えになります。
他にも、キャンプやツアーなどの企画もあります。もし、お子さんが興味があるならば、利用するのもおすすめです。

私は学生時代に、キャンプのボランティアリーダーをやっていました。不登校のお子さんも多く参加していました。同年代と交流をしたり、普段できないような経験をしたりとても楽しんでいました。
夏休みの声掛けのポイント

親自身のセルフケアも忘れずに
子どものことを考えるあまり、保護者自身が疲れきってしまうこともあります。 毎日「この子は大丈夫だろうか」「私の関わり方が悪いのかも」と悩み続けていると、心も体も疲れてしまいます。
でも、親が疲れていると、その不安は子どもにも伝わります。だからこそ、あなた自身のケアがとても大切なのです。
一人で抱え込まずに、信頼できる友人や、不登校の支援をしているカウンセラーなどに話を聞いてもらいましょう。「話すだけで気持ちが楽になった」ということは、本当によくあることです。
また、1日のうちでほんの少しでも、自分だけの時間を作ってみてください。お風呂にゆっくり浸かる、好きな音楽を聴く、そんな小さなことでも構いません。
そして、「今日は子どもが笑顔を見せてくれた」「一緒にご飯を食べることができた」など、「できていること」にも目を向けてみてください。親が元気でいることが、子どもにとって一番の安心材料です。

最近、保護者の方と面接では頻繁に「ハーゲンダッツを食べましょう」と伝えることがあります。もちろん、ハーゲンダッツじゃなくてもいいですが、おいしいアイスやケーキなど自分へのご褒美タイムを作りましょう。もちろん、リラックスできるのであれば、うまい棒でも構いません(笑)
よくあるご質問(FAQ)
Q夏休みの宿題はやらせるべきですか?
無理にやらせる必要はありません。できる範囲で、本人の気持ちを尊重しましょう。最近は宿題について「必ずしも子どものためにならない」という意見も増えてきました。「学校のルールに合わせる」とか、「保護者の期待に応える」よりも「子ども自身の自信をつける」ことを優先しましょう。もし、宿題を強制することで子どもの自信を無くしたり勉強嫌いが加速するなら、やらない方がましです。
Qスマホやゲームの時間はどう決めればいい?
一方的に制限するのではなく、子どもと一緒にルールを考えるのが効果的です。 例えば、「今週はこのルールを試してみよう」と、小さいステップのルール設定をおすすめします。いきなりガチガチに守れないルールを設定するなら、ルールを決めない方がましです。
Q夏休み明けが不安です。今からできることは?
生活リズムを少しずつ整えたり、気持ちを聞いてあげるだけでも十分です。
▶ 夏休み明けに不登校が増える|原因と対処法を心理師が解説
もう一度言います!夏休みは親子にとっての「回復期間」です
夏休みの過ごし方に「正解」はありません。
大切なのは、子どもが安心して過ごせること、そして親も無理をしないことです。
周りの子と比較せず、お子さんのペースに合わせて夏休みを過ごしましょう。
そして、何よりも大切なのは、家族が笑顔でいることです。
保護者さんの笑顔は、お子さんの心の支えになります。
【あわせて読みたい】
▶ 夏休み明けに不登校が増える|原因と対処法を心理師が解説
▶ 不登校のゴールは再登校ではなく子どもの自立(自律) カウンセラーが提案するGTNとは?