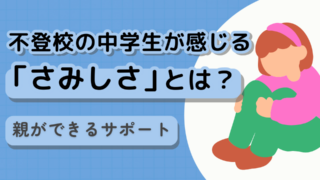不登校の子どもを支える毎日は、思っている以上に心がすり減るものです。
「このままでいいのかな」「誰にもわかってもらえない」――
そんな気持ちに押しつぶされそうになったことはありませんか?
子どものために頑張ろうと思う一方で、ふとした瞬間に感じる「さみしさ」や「孤独感」。
実は、それは多くの保護者が抱えている自然な感情です。
この記事では、不登校の子どもを育てる中で保護者が感じやすい孤独感に焦点をあて、
その背景や乗り越え方、今日から実践できる7つの工夫、そして支援の活用方法まで、やさしく丁寧に解説します。
保護者ではなく子どもの「さみしさ」についてはこちらの記事をご覧ください。
執筆・編集責任:吉田克彦(合同会社ぜんと代表 公認心理師、精神保健福祉士)
- 不登校の家族支援25年以上、3000家庭以上の支援実績
- スクールカウンセラー歴20年以上。小学校、中学校、高校(全日制、定時制、通信制)全ての校種で勤務経験あり。
→詳しいプロフィールはこちら
「私だけが苦しい?」——保護者が感じる孤独の実態
親しい人に相談しても「気にしすぎ」と言われてしまう
不登校について悩んでいるとき、最も頼りたい存在である配偶者が理解を示さないことは大きな孤独感を生みます。
「そんなに気にしなくてもいい」「そのうち学校に行くよ」といった言葉をかけられると、相談したはずが逆に傷ついてしまうこともあります。
他の人にとっては「まだ様子を見る段階」かもしれませんが、毎日子どもと向き合う保護者にとっては「今この瞬間がつらい」のは間違いありません。
この気持ちのズレが、家庭内の距離を広げ、孤独を深めてしまいます。
保護者同士と話が合わなくなり、距離ができる
子どもが不登校になると、これまで気軽に話していた保護者とも距離ができることがよくあります。
周囲の話題が「受験」「習い事」「学校行事」などになると、自分の状況と比較してしまい、「私だけ違う世界にいる」と感じることが増えます。
不登校の話をすると気まずい空気になることもあり、結果的に誰にも本音を話せなくなってしまうのです。
家族には「甘やかしすぎ」と言われてしまう
不登校について家族や親せきに話すと、「もっと厳しくしないとダメ」「昔はこんな子どもはいなかった」と否定されることがあります。
特に祖父母世代は「学校に行くのが当たり前」という価値観が根強く、現代の変化についていけません。
そのため、助言のつもりで厳しい言葉をかけてくることがあります。
否定的な言葉を受けると、「誰も私の気持ちをわかってくれない」と孤独を深めてしまいます。
▶ 「不登校は母親のせい」は本当?母親の育て方と不登校の関係を解説
誰にも本音を話せない苦しさ
学校の先生やスクールカウンセラーにも相談しにくい
学校の先生やスクールカウンセラーも、いろいろな人がいます。全員が不登校支援の正しい知識を持って、役立つことを言ってくれるわけではありません。
不登校支援に関する知識はあっても、立場的に保護者の気持ちに寄り添うことが難しい場合もあります。
教員やスクールカウンセラーから
「もっと、●●した方がいいのでは」
「あんまり××しないで」
などと助言をすることがあります。
その言葉を聞くと、これまでの子育てを否定されているかのように思い、「自分の育て方が悪かったのでは?」と罪悪感を抱えてしまうこともあります。
くわしくはこちらの記事へ
▶ 担任との関係が悪く不登校になった場合の適切な対応は?
▶ スクールカウンセラーは本当に意味ない?効果的な相談方法と成功のコツ
他の保護者の話を聞くのがつらい
周囲の子どもが学校での出来事を楽しそうに話す姿を見たり、他の保護者が学校行事の話をしていると、「うちの子はどうして…?」と苦しくなることがあります。
この比較によって、孤独感はより強まります。
「この子が学校に戻れないと、私は孤独のまま?」という不安
「子どもが学校に戻れば、また普通の生活が送れる」と思い込むと、保護者自身の精神的負担が大きくなります。
もし子どもがこのまま長期的に不登校だったら? 自分はこの孤独感を一生抱えていくのか?
そんな不安が心を締め付けてしまいます。
関連記事
▶ 不登校の子どもを持つ保護者への緊急アンケート 何が負担か
▶ 不登校経験者110名から保護者へのメッセージ!子どもが不登校になった時に心掛けること
なぜ私はこんなに孤独を感じるのか?
「保護者だから頑張らなきゃ」と思い込んでしまう
保護者が、「すべてを自分の責任だ」「私が何とかしなければ」と思い込むと、過度な責任感を抱えてしまいます。
この考えが孤独感を生み、「自分が頑張らないと誰も助けてくれない」という錯覚に陥ります。
「子どものために自分を犠牲にする」のが当たり前になっている
保護者が自分の時間や感情をすべて子どものために捧げることが当たり前になると、無意識のうちに孤独を感じるようになります。
心の余裕がなければ、子どもに対しても適切なサポートが難しくなるため、「自分の時間を大切にすること」は決してわがままではありません。
「このままでは疲れてしまう…」——保護者の心を守るためにできること
表面的な付き合いは減らし、安心できる関係を優先する
不登校の話題を出しにくい環境では、無理に人間関係を維持しようとすることがストレスになります。
本音を話せない関係に疲れを感じたら、一度距離を置いてみるのも選択肢の一つです。
その代わりに、心から信頼できる人とつながることを意識しましょう。
安心して話せる相手がいることで、孤独感が軽減されることがあります。
「同じ経験をしている保護者」と出会うことで、孤独が軽減する
不登校の子どもを持つ保護者が集まるコミュニティやオンラインのグループに参加すると、「自分だけではない」と感じることができます。同じ悩みを抱える人たちとつながることで、気持ちが楽になり、解決策のヒントを得ることもあります。
SNSの情報に振り回されないためのルールを作る
SNSでは、他の子どもたちが学校で楽しんでいる様子や、順調に育っている家庭の話題が多く見られます。そうした情報を見続けることで、「どうしてうちの子は…」と落ち込んでしまうこともあるでしょう。
SNSを見る時間を減らしたり、情報の選択を意識することで、心の負担を軽くすることができます。
「理想の子育て」に影響されすぎない方法
「子どもを○○すれば解決する」といった断定的な意見や、「成功事例」を強調する投稿を見ると、焦りや罪悪感を感じることがあります。
しかし、子どもそれぞれに合った対応は異なり、一つの方法がすべての子どもに通用するわけではありません。
「うちの子にとってベストな道を考えることが大切」と意識することで、他者の情報に振り回されることを防ぐことができます。
関連記事
▶ 【必読】学校に行きたくない、理由がわからない。背景と対処法を完全解説
「話すだけで気持ちが軽くなる」——カウンセリングの効果
不登校の問題は、すぐに解決するものではありません。
保護者自身が気持ちを整理し、落ち着いて対応できることが大切です。
カウンセリングは、具体的なアドバイスをもらうだけでなく、「話すことで気持ちを整理する」場としても大きな役割を果たします。
「孤独を感じたときに相談できる場があること」の大切さ
不登校の悩みを話せる場所がないと、保護者は孤独を感じやすくなります。
カウンセリングを利用することで、「ひとりで抱え込まなくてもいい」と思えるようになり、心の余裕が生まれることがあります。
今日からできる!保護者のさみしさ改善法7選
その1:「ひとりじゃない」ことを知る
不登校で悩んでいるのは、決してあなた一人ではありません。
一人で悩みを抱え込むと、どんどん追い詰められてしまいます。
同じように苦しんでいる人はたくさんいます。まずはそのことを知ってください。
暗闇の中を手探りで歩いている状況を想像してみてください。
誰かに「そっちだよ」と声をかけてもらえるだけで、どれほど心強く感じることでしょう。
同じ悩みを抱える人との繋がりは、あなたにとって大きな支えとなるはずです。
まずは「ひとりじゃない」ことを知ることが、孤独を克服する第一歩となるのです。
その2:「話せる場所」を見つける
誰かに話を聞いてもらうだけでも、気持ちは驚くほど楽になります。
人は言葉にすることで、自分の気持ちを整理できます。
信頼できる人に、今の気持ちを話してみましょう。
モヤモヤとした感情を抱えている時、誰かに話すことで「ああ、私はこういうことで悩んでいたんだ」と気づくことがあります。
溜まっていたものを吐き出すことで、すっきりとした気持ちになれるのです。
このように、「話せる場所」を見つけることは、孤独を解消する上で非常に大切なのです。
その3:「自分の気持ち」を大切にする
不登校のお子さんを支えるためには、まずご自身の心の状態を整えることが何よりも大切です。
ご自身の心と体にも、しっかりと目を向けてあげてください。
自分が元気でなければ、誰かを支えることは難しいからです。
体調が優れない時に、家族の世話をするのは大変ですよね。
心も同じです。心に余裕がなければ、子どもに優しく接することも大変です。
まずは「自分の気持ち」を大切にすることが、結果的に子どものためになります。
その4:「情報」と「距離」を上手にとる
インターネットやSNSには、様々な情報があふれています。
情報過多になると、不安や焦りを感じやすくなります。
上手く距離を取り、必要な情報だけを取り入れるようにしましょう。
情報は使い方を間違えると、人を惑わす凶器にもなり得るからです。
不登校に関する情報の中には、「〇〇をすれば必ず治る!」といった誇張表現も少なくありません。
こうした情報に振り回されると、かえって不安が募ってしまうことがあります。
「情報」と「距離」を上手にとることが、心の平穏を保つ上で重要なのです。
その5:「できること」から始める
不登校の解決には時間がかかることもあります。
不登校の理由は人それぞれであり、解決策も一つではないからです。
焦らず、お子さんのペースに合わせて、できることから始めていきましょう。
お子さんが学校に行きたくない理由が、友達関係にある場合もあれば、学習内容にある場合もあります。
原因は複雑に絡まっていて一つには特定できない場合もとても多いです。
保護者も子どもも「できること」しかできません。
その6:「周りの人」に頼る
一人で抱え込まずに、周りの人に頼りましょう。
困った時は、遠慮なくSOSを出してください。
人間は誰かに支えられて生きているからです。
風邪を引いた時、家族に看病してもらうと心強く感じますよね。
精神的な苦しみも同じです。
誰かに頼ることで、気持ちが楽になるだけでなく、新たな視点や解決策が見つかることもあります。
「周りの人」に頼ることは、決して恥ずかしいことではないのです。
その7:「未来」に目を向ける
不登校は、決してマイナスな経験ではありません。
経験をバネにして、お子さんは大きく成長することができます。
困難を乗り越えた経験は、人を強くするからです。
子どもの頃に自転車に乗る練習をしたことを思い出してください。
何度も転んで挫けそうになりながらも、最終的に乗れるようになった時の達成感は格別だったはずです。
不登校も同じです。この経験を乗り越えることで、お子さんはきっと大きく成長できます。
「保護者の心の余裕が、子どもの安心につながる」

まずは「保護者自身の気持ちをケアすること」が大切
「保護者は我慢すべき」と思わず、自分を大切にする
子どもの苦しんでいる姿をみると、「子どものためにすべてを我慢しなければならない」と考えがちです。保護者自身の心のケアができていなければ、子どもにとってもよい影響を与えることができません。
保護者が元気でいることが、子どもにとって一番の安心になる
保護者が笑顔でいることが、子どもにとっての安心につながります。
自分自身を大切にすることが、結果的に子どもを支える力になるのです。
カウンセリングは「余計なもの」ではなく「必要なもの」
「カウンセリングは特別な人が受けるもの」という誤解を解く
カウンセリングは、心に余裕を持たせるための大切な場です。
「特別な状況でなければ利用できない」と考えずに、気軽に活用することが重要です。
不安や孤独を抱え込まずに、早めに相談するメリット
問題が深刻化する前に、早めに相談することで気持ちの負担を軽減できます。
気持ちを整理するだけでも、大きな安心感が生まれるでしょう。
子どもを支えるには、まずは保護者のメンタル安定が大事
この記事では、保護者の「さみしさ」を感じる背景や対策について紹介しました。
お子さんの気持ちが安定するためには、まずは保護者の気持ちが安定することが大事です。
保護者が動揺したり不安定な状態では、精神的にも未熟な子ども立ちの気分が安定するはずがありません。
何の支えもない不安定な状態で安定しようとするのは難しいものです。
一方で、保護者が安定していれば、お子さんもしっかりと落ち着いた行動ができるでしょう。
保護者にとっての支柱が必要な場合は、ぜひカウンセリングを利用してください。