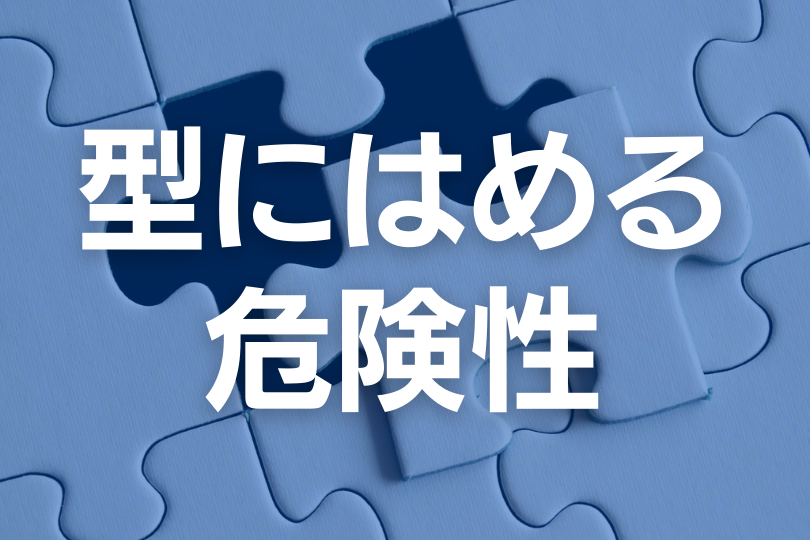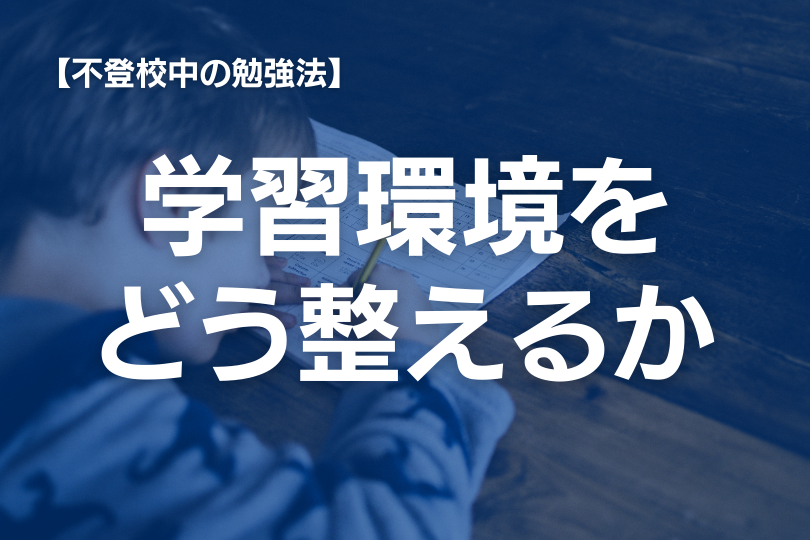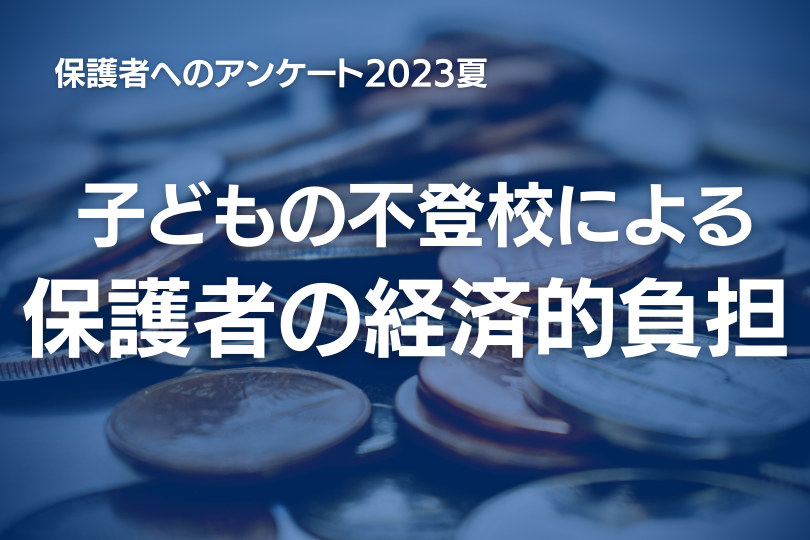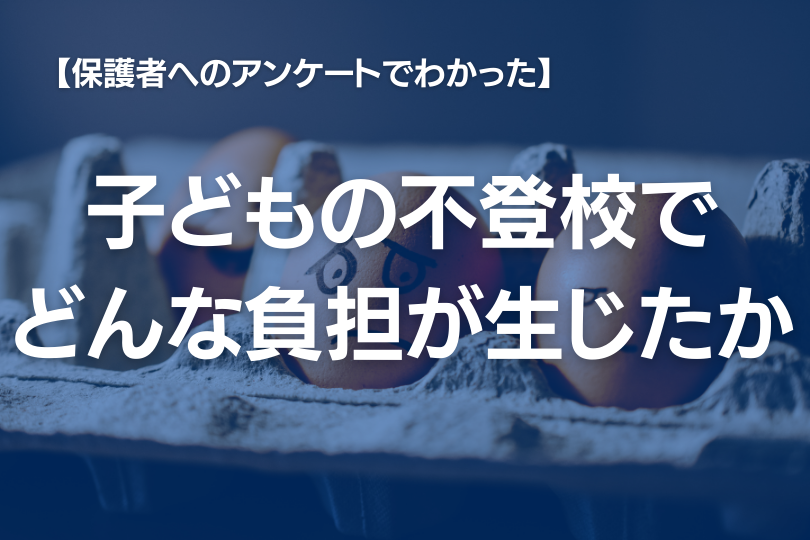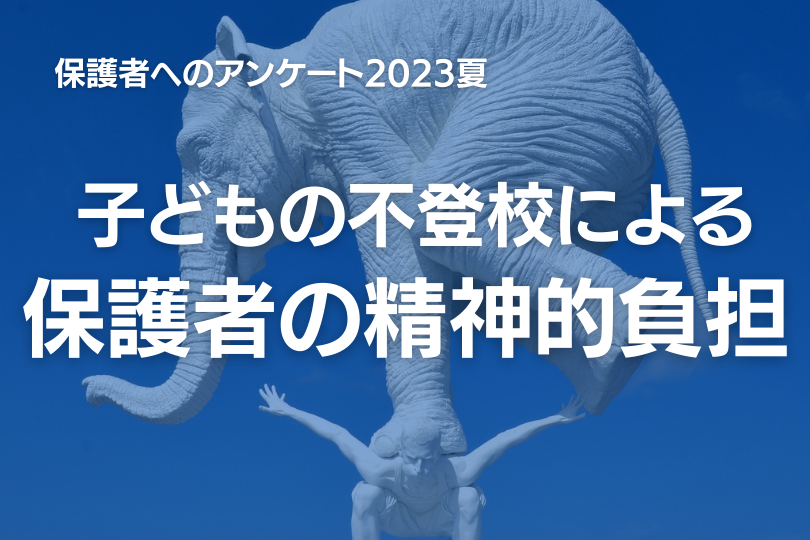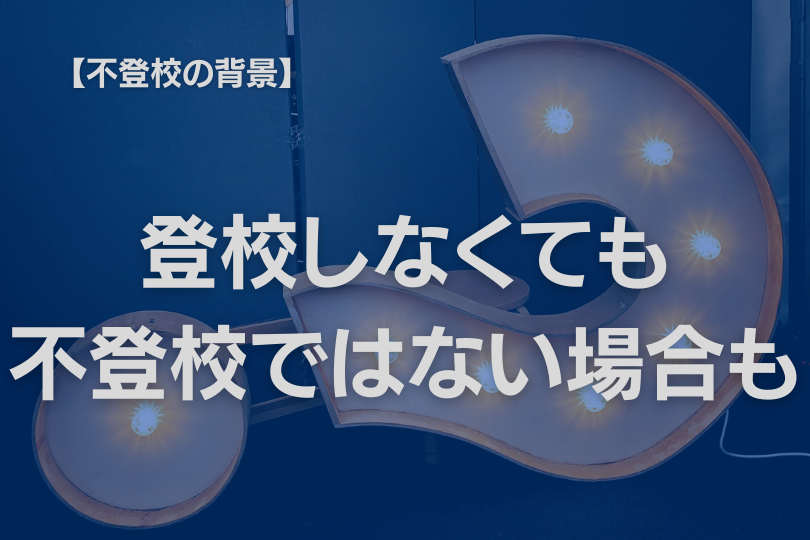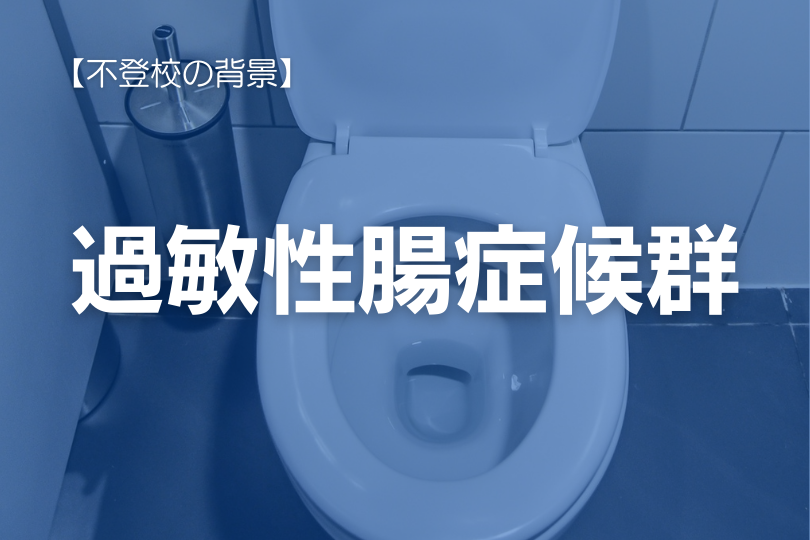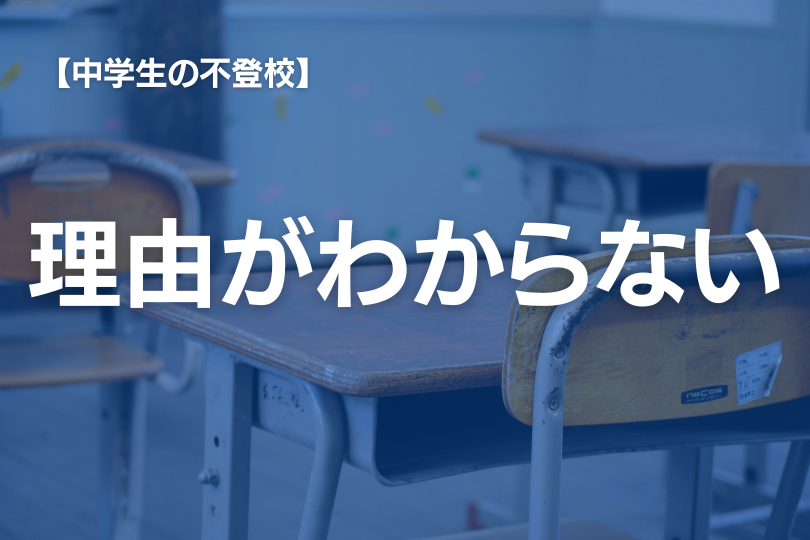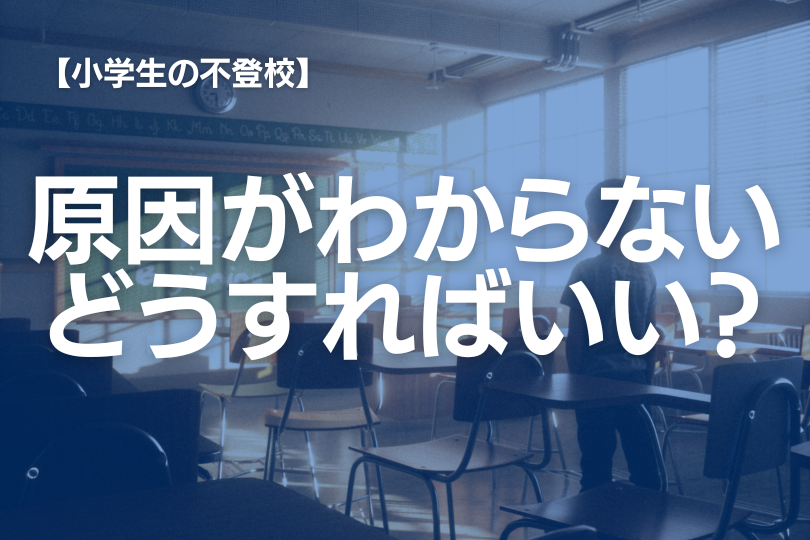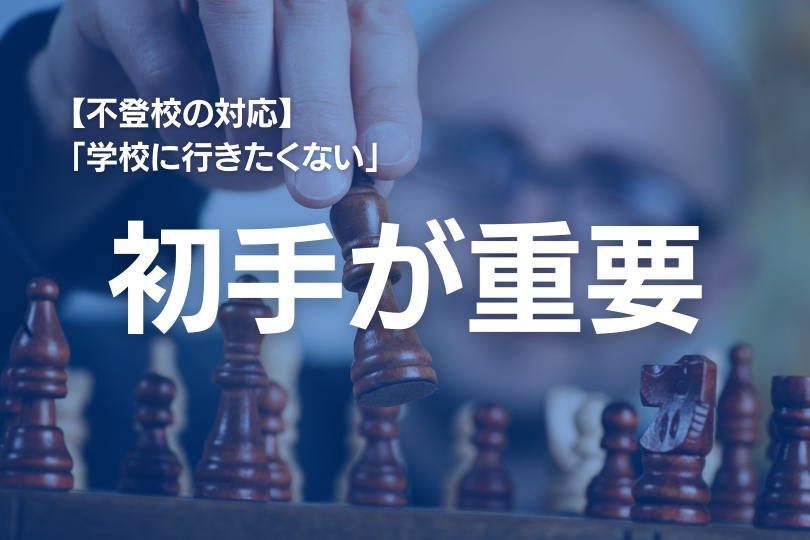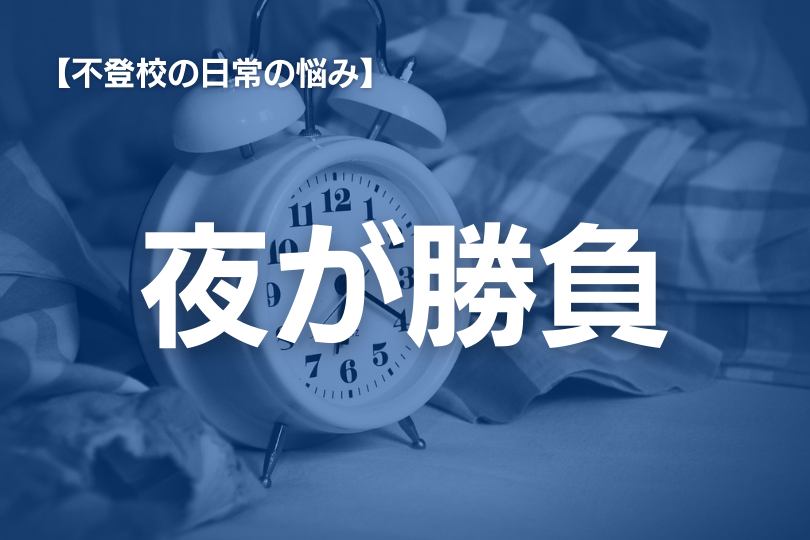吉田克彦(公認心理師)– Author –
 吉田克彦(公認心理師)
吉田克彦(公認心理師)
-

教育虐待と不登校の関係
「教育虐待」とは子どもに無理な勉強を強制すること 教育虐待とは、子どもが学習する環境や過程において大人が過度な期待やプレッシャーをかけ、子どもの心身に害を与える行為を指します。 親や教師が子どもの能力を過大評価し、達成できない目標を設定す... -

学校に行かなくても大丈夫!子どもが不登校の時に家でできる勉強法とは?
学校に行けない期間が長くなると、勉強への不安や焦りを感じるのは当然のことです。もちろん、不登校でも勉強はできます。むしろ、自分自身のペースで、個性を伸ばしながら学習を進める貴重な機会で、学び直しやさらに先に進むこともできます。 この記事では、不登校の中学生が直面する学習の課題と解決策、家庭での勉強の進め方とサポートの仕方、子どものモチベーション向上と学習意欲の喚起、オンライン教育と通信教育の活用方法、学習環境の整備について、わかりやすく解説します。 -

「繊細過ぎて学校に行けない」HSCの不登校、要因と乗り越え方
不登校の中には、HSPやHSCといった特性を持つ子どもたちもおり、彼らは特に繊細で敏感なため、学校生活がストレスとなることがあります。しかし、これらの子どもたちに対する適切な理解とサポートが必要です。 -

不登校になりやすい家庭の特徴!家族心理学の視点から心理師が解説
「うちの子が学校に行かないのは、育て方が間違っていたのか」このように思う保護者の方も多いようです。確かに家庭環境が不登校に影響することもありますが、家庭だからこそできる対策もあります。家族カウンセリングの事例を交えて紹介します。 -

【保護者アンケート】不登校はお金がかかる?保護者の本音と対策を調査!
お子さんが不登校になることで、保護者のおよそ4割が「経済的負担が重くなった」と感じています。 実際に、どのような負担が増えたのか、また軽くなったと考える人はどんな状況なのか、独自のデータから読み解きます。 -

不登校の子どもを持つ保護者への緊急アンケート 何が負担か
お子さんが不登校になることで、生活にはさまざまな影響が出てきます。そこで、当サイトでは独自のアンケートを実施しました。2023年のアンケートでは、保護者の負担について、精神面・経済面・時間の面から調査を行いました。 経済的負担については、保護者のおよそ4割が「重くなった」と回答しています。 実際に、どのような負担が増えたのか、また軽くなったと考える人はどんな状況なのか、独自のデータから読み解きます。 -

不登校の子を持つ保護者は「つらい」 独自アンケートから見えてきた保護者の精神的な負担の重さ
当サイトでは独自のアンケートで、保護者の精神的・経済的・時間的な負担を調査しました。 本記事は保護者の精神的な負担についての回答を見ながら、現状と改善方法を解説します。 -

【学校に行けない】パニック障害と不登校:症状・原因・対策を解説
パニック障害について症状や原因・対処法について解説いたします。 また、子どものパニック障害について、親が出来ることについても紹介します。 -

【必読】学校に行きたくない、理由がわからない。背景と対処法を完全解説
「うちの子が学校に行けない理由がわからない」と悩む保護者も多いでしょう。実は特定の理由がなくても不登校になる場合が多いのです。当事者の意見・保護者の視点・専門家の分析・厚生労働省などの調査から、理由のない不登校を考えます -

不登校の定義:登校していなくても不登校じゃない場合とは?
不登校にカウントされない長期欠席者の存在をご存知ですか? 本記事ではその理由と意味について解説します。 最新のデータによると不登校児童生徒数は、244,940人(2021年度)で、前年度よりも48,000人以上増えました。全児童生徒の中で不登校児童生徒の割合は2.57%となっています。実際の長期欠席者はさらに多く存在します。によると不登校児童生徒数は、244,940人(2021年度)で、前年度よりも48,000人以上増えました。全児童生徒の中で不登校児童生徒の割合は2.57%となっています。実際の長期欠席者はさらに多く存在します。 -

【スクールカウンセラーが解説】ADHD(注意欠陥多動症)と不登校の関係
この記事でわかること ADHDの特徴がわかる ADHDがなぜ不登校に関係することがあるのかわかる 子どもがADHDの場合にどのような支援をすれば良いかがわかる 【この記事に関連する読者からのお悩み相談】→ 第6回 ASD,ADHDの子どもに寄り添うのに疲れた 子ど... -

不登校と学習障害(LD)の関係|見分け方・特徴・対応策をスクールカウンセラーが解説
学習障害(LD)は、読み書きや計算の困難を引き起こし、不登校の原因となることもあります。この記事では、LDの特徴や見分け方、不登校との関連性、具体的な対応策などを詳しく解説します。
-

「繊細過ぎて学校に行けない」HSCの不登校、要因と乗り越え方
不登校の中には、HSPやHSCといった特性を持つ子どもたちもおり、彼らは特に繊細で敏感なため、学校生活がストレスとなることがあります。しかし、これらの子どもたちに対する適切な理解とサポートが必要です。 -

【担任との相性が悪い?】不登校の原因の3割が教員との関係
不登校の原因の約3割が「学校の先生」だとされています。特に、担任の先生との関係は重要です。どのような問題があるのか、子どもだけでなく保護者が担任と良い関係を築くにはどうすればいいか、スクールカウンセラー20年超の経験から解説します。 -

学校に行けないほどつらい、過敏性腸症候群:症状・原因・改善策を解説
過敏性腸症候群で学校に行けない…。そんな悩みを抱えるあなたに、症状を軽減する具体的な方法や、学校との適切なコミュニケーション術を詳しく解説。早めの対策で快適な生活を取り戻しましょう。 -

30日以上の欠席で不登校? 文部科学省の定義からわかる対策と現実
特別な理由がなく年間30日以上の欠席すると「不登校」に該当します。この記事では、不登校の本当の意味について、さまざまな角度から解説します。 -

【必読】学校に行きたくない、理由がわからない。背景と対処法を完全解説
「うちの子が学校に行けない理由がわからない」と悩む保護者も多いでしょう。実は特定の理由がなくても不登校になる場合が多いのです。当事者の意見・保護者の視点・専門家の分析・厚生労働省などの調査から、理由のない不登校を考えます -

【専門家解説】理由がわからない中学生の不登校:親の声掛けと解決法
不登校は、中学生時期に急増します。その理由は、勉強、部活、人間関係などさまざまですが「理由がわからない」場合も多いです。この記事では中学生の「理由がわからない不登校」について、背景や対応方法について心理師が解説します。 -

【理由がわからない】学校に行きたくない小学生に親ができることは?
小学生が「学校に行きたくない」と訴えるとき、その理由がはっきりしないことに悩む親御さんは少なくありません。子ども自身も、なぜ行きたくないのか説明できない場合が多く、漠然とした不安や不快感を抱えていることがあります。 -

【不登校と不安】子どもの不安の原因と今日から使える対策を心理師が解説
不登校の子どもを持つ保護者の方々に向けた、不安障害について解説する記事です。 不安障害とは何か、原因や症状の種類、対処法について詳しく説明します。 また、子どもたちが不安を抱えたまま学校に行けなくなってしまう場合があることも触れ、親御さんがどうサポートすればいいかをアドバイスしています。 正しい情報を得ることで、不安障害について理解を深め、子どもたちをサポートするための参考にしてください。 -

【学校に行けない】パニック障害と不登校:症状・原因・対策を解説
パニック障害について症状や原因・対処法について解説いたします。 また、子どものパニック障害について、親が出来ることについても紹介します。 -

「相談しても意味がない」と後悔を防ぐ、スクールカウンセラーの活用法
学校の雰囲気や生徒や教職員の様子も理解している場合が多く、より状況にあった解決策を検討できます。一方で、平日の昼間しか相談ができず、カウンセラーの力量に大きく左右され当たり外れが大きいなど、デメリットも大きいです。 -

子どもに「学校に行きたくない」と言われたら?
「子どもが学校に行きたくない」と急に言われたら、親はどうすればいい?不登校初期における保護者のNG対応例と、スクールカウンセラーが具体的な対処法を解説します。子どものSOSを見逃さず、適切なサポートがわかります。 -

毎朝の「学校に行く」「やっぱり行かない」の悩みを乗り越えるための3つのヒント
お子さんが不登校になると、毎朝、「学校に行きたい」「行きたくない」という子どもの心の揺れることがあります。例えば、前日には「明日は学校に行く」と言いながら、朝起きてこなかったり、逆に「明日も休む」と言いながらいざ朝になると「やっぱり学校に行ってみようかな」と言い出すこともあります。 そんな時に、どう対応すればいいのかと不安を感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、朝お子さんが学校に行くか行かないか決心がつかない状態の時に、保護者がどのような対応をすればよいか、不登校の家族支援を25年以上行っているカウンセラーの立場から解説します。